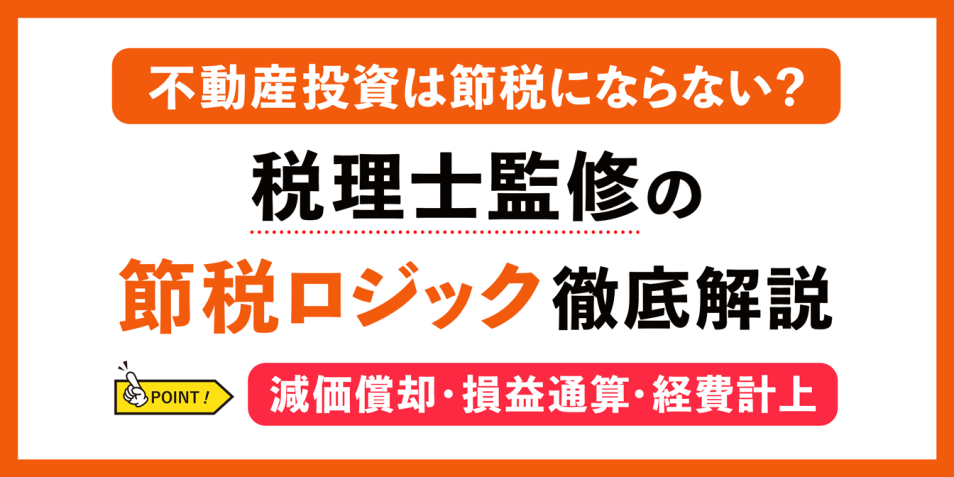- TOP
- 会社員のための不動産投資マガジン
- 記事一覧
- 不動産投資詐欺の5つの手口!悪徳業者の特徴や回避方法、相談先も解説
2026.02.09
ベルテックスコラム事務局
不動産投資詐欺の5つの手口!悪徳業者の特徴や回避方法、相談先も解説
- リスク
- 詐欺
- 弁護士
- 監修記事
不動産投資は、資産運用の有効な手段のひとつとして注目されています。一方で悪徳業者による詐欺被害が後を絶たないことも事実です。
2024年7月にNetflixで配信されたドラマ「地面師たち」が話題になったこともあり、あらためて不動産にまつわる詐欺事件への注目度が高まっています。投資する金額の大きな不動産投資は、一度詐欺師のターゲットになると大きな損害を負うことになりかねません。不動産投資詐欺に遭わないためには、悪徳業者の手口や特徴、回避方法などを十分に知っておくことが大切です。
不動産投資詐欺のよくある手口として、以下の5つが挙げられます。
|
手口 |
特徴 |
|---|---|
|
手付金を利用した詐欺 |
買い手に手付金を支払わせるが、物件を引き渡さずに音信不通になる。 |
|
婚活サイトやマッチングアプリを利用した詐欺 |
デートを重ねて信頼関係が構築されたタイミングで、収益性が見込めないような投資用不動産を購入するよう勧誘される。購入すると音信不通になる(ロマンス詐欺)。 |
|
サブリース方式による詐欺 |
過大なメリットがあるかのような説明を口頭で行い、実際はオーナーに不利な内容のサブリース方式契約(マスターリース契約)を結ぶ。 マスターリース契約はオーナーが賃貸人、サブリース会社が賃借人となるため、オーナーに不利な契約でも解除するのが難しくなる。 |
|
満室を偽装する詐欺 |
サクラを入居させて満室を装い、投資家に物件を購入させる。 |
|
海外不動産投資詐欺 |
海外の物件を |
この記事では、このような不動産投資で詐欺に遭わないために必要な情報をまとめて解説します。
そもそも詐欺罪とは?定義を確認
不動産投資詐欺を詳しく見ていく前に、まずは詐欺罪の定義や構成要件について確認しておきましょう。詐欺罪は、刑法第246条において次のように定められています。
第二百四十六条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
【引用】e-GOV 法令検索「刑法(明治四十年法律第四十五号)」2024年11月2日現在
上記より詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させる「1項詐欺罪」と、財産上不法な利益を得たり他人に得させたりした場合に適用される「2項詐欺罪(詐欺利得罪)」の2つから構成されます。
不動産投資の例では、「この物件を運用して利益を分配する」と偽って、投資家から資金をだまし取るといった場合が1項詐欺罪にあたります。一方、投資家から貸付を受けている業者が、貸金債権を架空の不動産投資に活用するよう勧誘し、不動産投資と引き換えに貸金の返還義務を免除させた、という場合には2項詐欺罪に該当します。
通説によると、詐欺罪が成立するには、次に挙げる4つの構成要件を満たす必要があります。
-
被害者を欺くこと(加害者による欺罔(ぎもう)行為)
-
被害者が欺かれること(被害者の錯誤)
-
被害者が加害者に対して金銭や財物を交付・移転すること(被害者による交付行為)
-
1〜3までに因果関係があり、連鎖的に起こっていること
とりわけ3において、被害者から加害者への金銭や財物の移転が完了すると、詐欺罪が成立したとみなされる可能性が高まります。なお、1〜3のうち、いずれか1つでも因果関係が認められない場合、詐欺罪ではなく「詐欺未遂罪」が成立するのが通説です。
詐欺罪と窃盗罪はどう違う?
加害者が被害者の金銭や財産を奪うという点では、詐欺罪と窃盗罪は共通しています。この2つの罪の大きな違いは、上で紹介した詐欺罪の構成要件③の部分です。詐欺罪は被害者が自分で金銭や財物を交付することが要件となっているのに対し、窃盗罪は「加害者が被害者の意思に反して金銭や財物を奪い取る」というのが要件です。
また、2項詐欺罪が犯罪として成立する一方、財物上の利益を奪う窃盗は「利益窃盗」と呼ばれ、処罰の対象にならないとされています。
詐欺罪と横領罪はどう違う?
詐欺罪と横領罪の違いは、対象となる財物を加害者が占有しているのか、被害者が占有しているのかという点です。被害者が占有する金銭や財物を加害者に交付させれば詐欺罪、被害者から占有を委託された金銭や財物を勝手に自分のものにすると横領罪が成立するのが通説です。
被害者から金銭を奪い取るケースを例に見ると、加害者が自分の口座に金銭を振り込ませれば詐欺罪、被害者の口座管理を委託された加害者が勝手に自分の口座へ送金すると横領罪が成立するのが通説です。
【参考】弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 札幌支部「詐欺罪とは?不動産投資での事例を交えて解説」2023年10月15日掲載
【参考】横浜ロード法律事務所「窃盗罪」2024年11月2日現在
【参考】ネクスパート法律事務所「横領罪とは何か?他の犯罪との違いや刑罰について解説」2023年10月26日掲載
不動産投資詐欺でよくある5つの手口
上記のように、詐欺の被害に遭うと大切な財産を奪われてしまいます。詐欺師は、1回の詐欺行為でできるだけ多くの財産を手に入れたいと考えるため、取引金額の大きな不動産投資はターゲットになるリスクが高いといえます。詐欺によるリスクを回避し、不動産投資を成功させるには、どのような手口があるのか十分に理解しておくことが大切です。
不動産投資に関する詐欺には、主に以下の5つの手口があります。
手口1.手付金を利用した詐欺
手付金を利用した不動産投資詐欺では、売買契約のために支払った手付金を「持ち逃げされる」「だまし取られる」「返してもらえない」などのパターンがあります。
事例紹介
具体的な手付金詐欺の一例として、手付金の支払いをして売買契約を結んだのに、物件が引き渡されることなく、売主が行方をくらますといったケースが挙げられます。
手付金とは、不動産の売買契約時に買主から売主に支払われるお金です。不動産売買契約における手付金は「解約手付」といわれるもので、契約成立後も物件引渡し前であれば、手付金を放棄することで損害賠償を負うことなく契約の解除が可能となります。また、売主側も手付金の倍額を支払えば契約を解除できます。
このケースでは、不動産の所有権を有する本来の買主が詐欺を働くのではなく、仲介業者などが連携し、グループで計画を企てる場合がほとんどです。後ほど紹介する2017年に大きな話題となった「積水ハウス地面師詐欺事件」のように、地面師と呼ばれる詐欺師が所有権者や仲介業者になりすまし、書類の改ざんや偽の手続きなどを行います。
取引に違和感があれば、不動産会社や所有権者の書類を細かく確認する、近隣の人に本来の所有権者について聞き込みを行う、弁護士や司法書士などの専門家に相談するなどの対策を講じて、詐欺被害を予防するようにしましょう。
有効な対策
悪徳業者に不動産投資の手付金をだまし取られた場合は、取り返すのが困難になるケースも少なくありません。そのため、信頼できない不動産会社などにはそもそも手付金を渡さないことが大切です。なお、手付金をだまし取られた場合、保証協会に加入している宅建業者に対する苦情解決や手付金の保全を行う保証協会に相談することで手付金を取り戻せるケースもあります。(詳細は記事の後半で解説)
手口2.婚活サイトやマッチングアプリを利用した詐欺
「デート商法」「恋人商法」と呼ばれる詐欺は、異性の恋愛感情を利用して不動産などの高額な商品を売りつける詐欺です。一般的に「ロマンス詐欺」とも呼ばれます。
事例紹介
デートを重ねて相手が信用した段階で「2人の将来のために」などの甘い言葉を駆使して物件の契約を結ばせて、その後連絡が途絶えるといった事例があります。デート商法は、昔からある古典的な詐欺手法です。近年では、婚活サイトやマッチングアプリを通して知り合った異性に不動産などの高額商品を購入させる事例が増えています。
デート商法の不動産投資詐欺では、資産形成や資産運用のプロフェッショナルである「投資コンサルタント」「ファイナンシャルプランナー」などの職業を装い犯行に及ぶことが多い傾向にあります。こうした肩書きの信頼性に加え、個人的な信頼関係を構築することで「この人なら大丈夫だろう」と思わせて、詐欺行為を働くのです。
有効な対策
婚活サイトやマッチングアプリを通して知り合った異性が高額商品をしつこく勧めてきた場合は、疑うのが基本です。契約してしまった場合は、クーリングオフができる可能性もあります。また、2018年の消費者契約法の改正により、デート商法などの不当な勧誘による契約は後から取り消せるという規定が新設されました。条件に該当すればこれらの方法で解決を図ることができます。
ただし、上の規定を適用するには「社会生活上の経験が乏しい」などのいくつかの要件が定められているため、必ずしも契約を取り消せるとは限らない点に注意が必要です。
ロマンス詐欺に限らず、契約に不審な点を感じたら、消費者ホットライン「188」に電話すると、地域の消費生活相談窓口を案内してくれますので、活用しましょう。
婚活サイトやマッチングアプリでは、お互いの素性を隠しながら関係性を深めることも可能であるため、相手に少しでも怪しいところがあれば関係を見直す判断を下したほうがよいでしょう。
【参考】消費者庁「早わかり!消費者契約法」2024年11月14日現在
手口3.サブリース方式による詐欺
サブリース方式とは、一般的には「サブリース会社が物件を一括で借り上げ、毎月一定の賃料を納めることを前提に第三者へ転貸する一連の契約形態」を指します。
※厳密には、不動産会社やサブリース会社が、第三者へ転貸することを目的にオーナーから物件を借りる契約を「マスターリース」、この物件を不動産会社が入居者に貸す契約を「サブリース」と呼びます。
オーナーにとっては、空室があっても一定の家賃収入が保証されること・管理を委託できることなどが、サブリース方式で契約を結ぶメリットです。
サブリースを適正に利用すれば、空室リスクを軽減するのに役立ちます。しかし、サブリースを使ってオーナーを欺く事例が後を絶たないため要注意です。
しかし、実際は契約内容の説明自体に偽りがあったり、設定家賃が相場よりもはるかに安かったりといったトラブルが起きています。オーナーにとってのデメリットを説明されないまま、契約上「借主」であるサブリース会社側が契約弱者として守られてしまうのです。
こうしたケースでは、オーナーが十分な家賃を受け取ることができず、アパートローンの返済に苦しむことになります。
事例紹介
「30年一括借り上げ、家賃保証」といううたい文句に引かれてサブリース契約を結んだオーナーが、突如契約を打ち切られたという事例を紹介しましょう。サブリース契約は、物件所有者が貸主として見なされ、サブリース会社は借主として保護される立場関係にあります。
今回のケースでは、オーナーがサブリース会社より「○年にわたってサブリース家賃は下がらない」というような断定的な説明を受けたにもかかわらず、後日サブリース会社から借地借家法を盾に家賃の減額請求をされました。その後、さらに条件が悪くなり、最終的にはサブリース会社側から一方的に契約解除をされてしまったのです
しかし、その点に関しては契約書に明記されていました。サブリース会社は契約内容説明の際、あえてその点を省略して、メリットだけが目立つように説明を行いました。いざ契約を締結した後は、段階的に家賃を減額していき、収益が下がったタイミングなどで契約期間満了を待たずに契約を打ち切るのです。
国交省、消費者庁、金融庁が連名で作成した注意喚起を促す資料には、契約期間中に契約解除を迫られる事例なども紹介されています。
【参照】国土交通省「賃貸住宅経営(サブリース方式)に関する契約を締結する前に」 2025年2月7日現在
有効な対策
サブリース会社(不動産会社、賃貸管理会社など)は、サブリース契約を交わす前に重要事項について書面を交付して説明を行う義務があります。まずは、その内容をしっかり理解して疑問があったら確認することと、その疑問が払拭されなければ契約しないことが重要です。
また、サブリース会社が「家賃の値下がりがない」「家賃が保証される」といった不実のことを伝える勧誘行為は、賃貸住宅管理業法に抵触し、行政処分や契約の取り消し、損害賠償請求等の対象になる可能性があります。
トラブルに遭った際は、専門機関や不動産に強い弁護士に相談することをおすすめします。(詳細は本記事の後半で解説)
手口4.満室を装って契約を持ちかける詐欺
満室を装って契約を持ちかけられる不動産投資詐欺には、以下の2つのパターンがあります。
事例紹介
1つ目は、物件が売りに出されている間、関係者などに頼んで満室にしておき、物件売却後に関係者を退去させる手口です。
例えば、一棟アパートの購入者が「最初の1カ月は家賃が振り込まれていたのに翌月になると半分近くが退去した」という事例があります。
「満室で十分な家賃収入が見込める」「空室が発生しても他の部屋でフォローできる」という点に惹かれて購入した物件ですが、同時期に複数の世帯で退去が発生しました。これは、売却を有利にするために、売主が仕込んだサクラの入居者です。
しかし、売主が満室であることを偽装していたのかどうかを、証拠を持って立証するのは極めて困難です。このような場合、売主の責任を追及することが難しく、買主は新たな入居付けに追われます。
2つ目は、不動産投資の世界で「カーテンスキーム」と呼ばれる詐欺です。これは、物件を売りに出している間、空き部屋にカーテンを取り付けて入居者がいるように見せかける手口です。
完全に見破ることは難しいですが、いずれにしても契約時に入居者の有無を書類で確認し、具体的にいつ頃から入居しているのかを把握しておきましょう。
有効な対策
満室を装って契約を持ちかける手口は、後から詐欺行為を立証することが困難です。そのため、売買契約を交わす前に見破ることが重要です。
具体的な対策としては、レントロール(各部屋の賃貸借条件や契約の現況をまとめた資料)を確認することが挙げられます。直近数カ月の間に新規契約している部屋が多い場合は、カーテンスキームの可能性を疑いましょう。ただし、レントロール自体を偽装しているケースもあるため注意が必要です。
カーテンスキームを見破るための対策として現地確認も重要です。部屋にカーテンが取り付けられていても、ポストや部屋の入口付近、駐車場の状況などから生活感が感じられないような場合は、安易に契約を進めないようにしましょう。
手口5.海外不動産への投資を持ちかける詐欺
同じ不動産投資でも、海外と国内では商慣習や法律が異なります。一般的に海外、特に発展途上国では詐欺に遭うリスクが高いため注意しましょう。
事例紹介
海外における不動産投資詐欺の事例としては「売買契約を交わしてお金を払ったのに、物件引渡し前に不動産会社との連絡が途絶えて公式サイトもなくなっていた」というようなケースが挙げられます。
海外の新築不動産では「プレビルド(Pre build)」の物件販売も珍しくありません。プレビルドとは、将来物件が完成することを前提に前もってお金を支払う契約方式のことです。
プレビルドでは、「予定していた期日までに物件が完成しない」「物件の引き渡しが受けられない」などのトラブル事例があります。
有効な対策
海外の不動産投資詐欺を見破るのは、上級者でも難しいのが実情です。トラブルが起きても日本の法律が及ばないことが多いため、国内の関係機関や弁護士に相談しても解決できない可能性も高いでしょう。よって、不動産投資の初心者が海外物件を買い付ける場合、国内市場に上場しているような大手デベロッパーを通して取引するのが安全でしょう。
自分が詐欺の当事者になっている3つのパターン
不動産投資では、知らない間に自身が詐欺に加担してしまうケースがあります。この場合、詐欺の被害者は自身が融資を受ける金融機関です。
-
審査書類の改ざん
-
二重売買契約
-
1法人1物件スキーム
自分が詐欺の当事者になっている代表的な上記3つのケースを具体的に解説します。
審査書類の改ざん
よくあるケースとして、ローン審査の通過が厳しいことを理由に不動産会社から促されて、審査書類の改ざんを行うことです。文書偽造はれっきとした詐欺行為の1つですので、絶対にしてはいけません。
例えば、金融機関から審査資料として求められる銀行口座残高のスクリーンショットを、不動産会社が画像編集するケースがあります。口座残高が実際よりも多くあるかのように見せかけて審査に通りやすくするわけです。
仮に偽装を見抜かれずに審査を通過したとしても、後々偽装が発覚した場合には、ローン残債の一括返済を求められます。このようなトラブルに巻き込まれないためにも、審査資料の提出をする際は不動産会社・金融機関・自分の三者が立ち合い、書類の内容に相違がないか確認しながら進めるようにしましょう。
二重売買契約
二重売買契約とは、不動産会社が作成した2パターンの契約書に署名・押印し、契約締結することを指します。具体的には、正式な契約書と、実際の売買価格よりも高い金額を記載した金融機関用のダミーとなる契約書を作成し、より多くの融資を引き出します。
悪質な業者になると、二種類の契約書を作成するリスクの説明もしないまま押印を求めてくることもあります。説明なしで押印をしたとしても、文書偽造に加担したことになってしまい、発覚時には同様に借入金の一括返済を求められる可能性があるので注意が必要です。
このようなトラブルを防止するためにも、最悪のシナリオで起こり得るリスクを理解し、決して不動産会社の言いなりにならないようにしましょう。
1法人1物件スキーム
1法人1物件スキームとは、物件を購入する度に新しく法人を立ち上げ、その都度新しい会社名義で融資を受けることを指します。この手法を用いることで、個人名義で借り入れるよりも多額の融資を受けられるようになります。
短期間のうちに通常は購入できない複数の物件を取得可能なので、事業拡大へ意欲的な人が加担してしまうケースが多いようです。しかし、既存の借り入れの存在を隠ぺいして融資を申し込むことは、詐欺行為に該当するのが通例です。
近年は、銀行同士の合併などによって異なる銀行間での情報共有が進んでいるため、1法人1物件スキームが発覚する可能性は以前より高まっているようです。借入金の一括返済を求められるような事態にならないよう、このようなスキームに加担しないよう気をつけましょう。
2024年本当にあった不動産投資詐欺事件
2024年も不動産投資詐欺に関する事件が後を断ちません。自分が不動産投資詐欺の被害者にも加害者にもならないためには、過去にあった事件の背景や原因を理解し、適切な対策を取っておくことが何よりも大切です。
ここでは、2024年にあった不動産投資詐欺事件の事例を2つ紹介します。
【2024年の事件1】自分の賃貸用物件が性風俗用に契約されていた
1つ目は、不動産仲介会社がマンションの管理会社をだまして、風俗店との賃貸借契約を仲介し、部屋を風俗店として違法に使用させていたという事件です。
この事件では、風俗店を運営するための部屋を探していた風俗店経営者に対して、不動産仲介業を営む男が物件を紹介すると言って接触。風俗店の従業員を住人とする虚偽の申し込み書類を作成して管理会社に送付し、実態と異なる契約を結んだとされています。最終的に、物件を仲介した不動産仲介業を営む男、部屋を使って風俗店を運営していた経営者と従業員の3人が逮捕されました。
この事件のポイントは、舞台となったマンションがサブリース物件だった点です。物件を仲介した男は、マンションオーナーとサブリース契約を締結していた管理会社から入居者審査を任されていたとみられ、賃貸人の情報や部屋の使用目的などを偽って契約できる立場にありました。管理会社やオーナー自身が厳格な入居審査を行う体制になっていれば、このような結果にはなっていなかったかもしれません。
近年、都心では店舗型風俗店への規制が強まっており、新規開業はほとんど不可能となっています。そのような中で違法営業をする物件としてターゲットになっているのが、管理人が常駐しておらず、管理体制が甘いマンションです。こうした事例は近年増加傾向にあるため、都心の投資物件を選ぶ際は、管理体制をしっかりチェックしておく必要があります。
【参考】時事通信ニュース「風俗店と知りながら賃貸契約仲介=容疑で不動産会社社長逮捕―警視庁」2024年9月18日掲載
【参考】livedoor News「隣室が風俗店になることも「夜専門の不動産屋」転貸で風俗営業して逮捕…増殖する「違法マンションエステ」の実態とは」2024年9月20日掲載
【2024年の事件2】高齢の母がインターネットで不動産を購入させられていた
2つ目に紹介するのは、認知症を患う高齢の母が、インターネットで不当に投資用不動産を購入させられていた事例です。
詐欺の被害に遭ったのは、千葉県内で1人暮らしをしていた80代の女性。6年前に認知症の診断を受けましたが、一人で気ままに暮らすことを希望していたため、ヘルパーやケアマネージャーによる支援のもと生活していました。
そんな女性の異変に気付いたのは、定期的に母親のもとを訪れていた娘でした。ある日、母親の預金通帳を見てみると、まったく心当たりのない約300万円の振り込みが記録されていたのです。あらためて振込先を確認したところ、都内にある不動産販売会社であることが判明します。
この会社に問い合わせてみると、母親が神奈川県内の投資用マンションの1室を購入したということを知らされます。しかし、母親に聞いても「買っていない」と話すばかりでした。会社側に契約書を送ってもらうと、確かに母親の直筆の署名と印鑑が押されていました。そして、購入したのがマンションの1室ではなく、持分の一部のみだったことも判明します。
購入した物件は第三者に賃貸されており、母親の口座には月2,500円のわずかな賃料収入が振り込まれる契約になっていたものの、300万円を回収しようとすれば100年はかかる計算になり、80代の母親の投資物件としては到底ふさわしくないものでした。
2024年6月、この物件を販売していた不動産販売会社勤務の4人が逮捕されます。今回の件とは別の80代の認知症を患う女性に、神奈川県内のアパートの部屋を購入させ、5,000万円もの金銭をだまし取った疑いによる逮捕でした。彼らは認知症の高齢者などを狙い、1年間で7億円もの売上を上げていたのです。
この例のように、判断能力の低下した高齢者を狙った不動産投資詐欺事件も増えています。資産管理を本人が行っていると、子どもや親族が気づかない間に、悪質業者の手口にだまされてしまうことも考えられます。
こうした事態を防ぐには、本人が健康で意思表示できるうちに、信頼できる子どもなどの家族・知人に資産管理を任せる、「家族信託」や「民事信託」を利用するのがおすすめです。全資産の管理を任せるのが不安であれば、一部のみ管理を委託することもできます。信託契約を結ぶときに契約内容を公正証書に残すとともに、ほかの信頼できる親族などを監督人としておくことで、トラブルを未然に防げるでしょう。
【参考】NHK「知らないうちにアパートの1室を~認知症高齢者狙う不動産詐欺」2024年7月31日掲載
不動産投資詐欺の業者に共通する特徴
不動産投資詐欺の業者は、以下に挙げる6つの特徴のいくつかが該当することが多いです。
特徴1.断定的にメリットを解説する
不動産投資は投資行為である以上、少なからずリスクが存在します。不動産という資産を手に入れられる点はメリットであるものの、資産価値が下がるリスクもゼロではなく、元本割れを起こす可能性も捨てきれません。
それにもかかわらず、不動産会社から「この物件は将来確実に値上がりする」「このエリアは将来性が期待でき、数年後には何倍の価値が出る」など、確実なリターンをイメージさせるような言葉が出てきたときは要注意です。
不動産投資のコンサルティングで営業担当者がメリットについて解説すること自体は問題ありません。しかし「値上がりする」「絶対に儲かる」といった将来利益の断定は宅地建物取引業法に抵触します。(法第47条の2第1項-不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為)不動産投資の詐欺業者は、こういった断定的な物言いをすることが多いです。
特徴2.事前にデメリットやリスクを伝えない
不動産投資のメリットばかり強調するセールストークも詐欺業者の特徴のひとつです。不動産投資も他の投資と同じようにデメリットやリスクがあります。これらのネガティブな情報についても丁寧に情報提供してくれるのが信頼できる不動産会社です。
例えば「高利回り」というワード。そもそも利回りは「年間家賃収入(または年間収益)÷物件価格」で計算されるものであり、物件価格が低いほど数値は高くなります。反対に、物件価格は「年間家賃収入(または年間収益)÷利回り」で計算できるため(収益還元法といいます)、利回りが高いほど物件価格が低く算出されることになるのです。
一般的に、都心部の物件や築浅の物件などは利回りが低く、反対に郊外の物件や中古物件などは利回りが高くなる傾向にあります。高利回りな物件と聞くと優良物件に感じるかもしれませんが、築年数が古かったり利便性が低かったりして、借り手がつきにくい訳あり物件の可能性もあるでしょう。
利回りだけで判断するリスクを説明することなく、単に「高利回りだから儲けやすい」というような話をされたら、何かしら問題があるのかもしれません。あらかじめ不動産会社に、利回りが低くなっている要因を詳しく聞いておくことをおすすめします。
特徴3.おとり広告などを掲載している
見込客を集めるために売る意思のない物件で釣ることを「おとり広告」、実在しない物件で釣ることを「虚偽広告」といいます。これらの広告は、宅地建物取引業法、不当景品類及び不当表示防止法などで禁止されています。入居者向けの賃貸募集でおとり広告や虚偽広告が使われるのが一般的ですが、不動産投資詐欺で用いられるケースもあります。
誰が見ても好条件の物件をおとり広告として掲出し、問い合わせてきた人に対して「この物件はとても人気ですでに売れてしまった」などと言って、ほかの条件が悪い物件を売りつけるというのがよくあるパターンです。いくら好条件だからといって、周辺地域における物件価格や利回りの相場とかけ離れた物件には、飛びつかないよう注意しましょう。
特徴4.事務所が雑居ビル、または存在しない
不動産投資の詐欺業者は、ある程度儲けた時点で計画倒産をしたり、姿をくらましたりするのを前提としていることも少なくありません。そのため、敷金の安い雑居ビルや、廉価な費用で契約できるレンタルオフィス、シェアオフィスに事務所を構えているケースも多くみられます。より悪質な場合には、虚偽の住所を表示していることもあるため注意が必要です。
特徴5.Webサイトが怪しい
不動産会社のWebサイトを検索してみると、詐欺業者を見分けられる場合もあります。最近は、不動産投資に関する情報もインターネットで仕入れる方が多いため、優良な不動産会社であればWebサイトの整備や更新に力を入れているのが一般的です。
しかし、悪質な不動産会社はWebサイトを詐欺勧誘の入口としか捉えていない節があります。次のような特徴に当てはまる場合、取引は避けたほうが無難です。
- Webサイトがしばらく更新されていない
- 取引事例が十分に掲載されていない
- 事務所の住所や問い合わせ先がどこにもない
- 代表やスタッフの名前や写真が掲載されていない
特徴6.契約締結を急かす
不動産投資詐欺を企てている悪質業者は、「この物件は人気なので早くしないと売れてしまう」「すでに購入を検討している方がいるので早い者勝ち」「今すぐ決断したほうがいい」など、言葉巧みに契約締結を急かす傾向があります。
買主に考える時間や他人に相談する時間を与えてしまうと、契約の問題点に気づいて、成約を逃してしまう恐れがあるからです。違法行為が明るみになる前に契約を成立させ、できるだけ早く代金を回収したいというのが悪質業者の本音でしょう。
本当に顧客のことを考えている不動産会社であれば、じっくり考えたうえで納得のいく物件を購入するよう促すはずです。契約を急がせるような言動があった場合には、その場では決断せず、持ち帰って第三者に相談したほうがいいかもしれません。
不動産投資詐欺を回避する8つの方法
いくつかのポイントを押さえておけば不動産投資詐欺のリスクを軽減できます。悪徳業者の被害に遭わないための主な方法は以下の8つです。
回避方法1.担当者の言動に注意する
不動産投資の詐欺業者の特徴には「断定的にメリットを解説する」「事前にデメリットやリスクを伝えない」などがありました。これらの特徴を踏まえ、営業担当者(コンサルタント)の言動から「いいことばかり言って、上手く乗せようとする」姿勢が見えた場合は契約を見送ることが大切です。物件に関する説明や、質問への回答もそこそこに手付金の支払いや契約締結を急かされた場合も、詐欺の可能性があるため注意しましょう。
回避方法2.不動産会社の事務所の所在を確認する
詐欺業者の事務所は雑居ビルに入居していたり、そもそも存在していなかったりするケースも多いのが実情です。そのため、担当者の名刺に書かれた事務所の住所をGoogle Earthで検索し、入居しているビルの雰囲気を確かめてみるのもよいでしょう。
ただし、「住所を偽っている」「レンタルオフィスやシェアオフィスに入居している」といった可能性もあります。違和感があるようなら、相手先の事務所での打ち合わせを打診して、現場をチェックするのがおすすめです。
回避方法3.不動産投資の基本知識を身につけておく
不動産投資の詐欺に遭った人の多くが、悪徳業者のセールストークを鵜呑みにしてしまっています。詐欺を回避するには、投資家自身が不動産投資に関する最低限の知識を身につけておくことが何より大切です。不動産投資に必要な知識を身につけるには、以下のような方法があります。
-
不動産投資をテーマにした本をなるべく多く読む
-
不動産取引や賃貸管理に関する資格を取得する(宅建士や賃管士など)
-
不動産投資セミナーに複数参加する
本やセミナーは知識を習得するのに有効ですが、著者や講師を限定してしまうと知識に偏りが生まれてしまいます。なるべく複数のプロの話を読み聞きして、多角的な視点を養いましょう。
ただ、勉強が大切なことは承知していても、何から手をつければいいのか疑問に思う方も少なくないはずです。学び方を知りたい不動産投資初心者の方は、こちらの記事をぜひ参考にしてください。
【おすすめ関連記事】不動産投資初心者向け勉強法!学ぶべきポイントや不安解消に役立つ本も紹介
回避方法4.不動産会社の情報を確認して信頼できるか見極める
「好印象の営業担当者だったので信用してしまった」「業者のことを調べずに契約してしまった」というのも不動産投資詐欺に遭う典型的なケースです。
不動産投資詐欺に遭わないためには、パートナーとなる不動産会社を選ぶ際、以下に挙げるような項目もチェックしておきましょう。
宅建業免許を取得しているか
物件仲介などの宅地建物取引業(宅建業)を営むには、事務所のある都道府県もしくは国土交通省による宅建業免許を取得しなければなりません。無免許で仲介業務を行うことは宅建業法に抵触します。特に不動産会社の規模が小さかったり社歴が浅かったりする場合は、念のため宅建業免許を持っているかを確認しましょう。国土交通省の「宅地建物取引業者 検索」を利用すると簡単に宅地建物取引業者を確認できます。
一定期間の社歴があるか
社歴は長いほど安全ですが「創業から10年以上」というのがひとつの目安になるでしょう。創業から10年以内に大半の企業が淘汰されるといわれており、10年以上生き残ってきたのであれば、一定の信頼を獲得してきたと考えられるからです。
社員数や資本金が多いか
不動産業は資本力が重要な業種なので、資本金が1,000万円以下の企業だと不安があります。また、社員数も企業の信用力を測る指標のひとつです。不動産投資初心者が安心して任せられるパートナーを探す場合、100名以上の規模感が目安となります。
過去に行政処分を受けていないか
前述のように、不動産業を営むには宅建業免許を取得する必要があります。宅建業法に違反すると行政処分の対象となり、処分を受けた会社は免許権者である国土交通省や都道府県から、事業者名、処分を受けた日、処分等の種類を公表されます。過去に処分を受けた会社はコンプライアンスに対する意識が希薄な可能性もあるので、取引には慎重になったほうがよいでしょう。
宅建業法に基づく行政処分の内容は、国土交通省や自治体のWebサイトで簡単に検索できます。不動産会社の情報を調べる際は、過去に行政処分を受けていないもチェックしておくのがおすすめです。
一般媒介契約で複数社と契約する
物件の売買にあたっては、不動産会社と媒介契約を締結するケースがほとんどです。媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。3つの契約の違いをまとめると次のとおりです。
|
一般媒介契約 |
専任媒介契約 |
専属専任媒介契約 |
|
|
契約できる会社数 |
複数社 |
1社のみ |
1社のみ |
|
契約期間 |
任意 |
最長3ヵ月まで |
最長3ヵ月まで |
|
業務状況の報告義務 |
なし |
2週間に1回以上 |
1週間に1回以上 |
|
レインズの登録義務 |
なし |
契約締結後7日以内 |
契約締結後5日以内 |
|
自己発見取引 |
できる |
できる |
できない |
専任媒介契約、専属専任媒介契約では1社だけとしか契約できないのに対し、一般媒介契約は複数の不動産会社と締結することができます。
専任媒介契約や専属専任媒介契約を締結すると、契約期間内の成約でほぼ確実に仲介手数料を得ることができるため、不動産会社側のモチベーションが上がるというのはメリットです。しかし、1社と契約するだけでは、サービスや対応の質がいいのか悪いのか判断がつきません。
信頼できる不動産会社なのか見極めたいのであれば、不動産購入時の仲介は一般媒介契約として、複数の会社を比較することをおすすめします。
回避方法5.不明点や納得できないことがある場合は話を進めない
「相手は不動産のプロだから言うことを聞いていればいい」といった受け身な考え方はやめましょう。不動産投資は投資行為であるとともに賃貸経営でもあります。投資も事業も自己責任で行うものであり、損失やリスクも最終的にはオーナーが負わなければなりません。
「何かあったときに困るのは自分」という危機意識を持って、不明点や納得できない点は契約前に解消しておきましょう。どうしても不安や疑問を解消できないなら、それ以上契約を進めるべきではありません。
回避方法6.不動産投資の成功者とつながりを持つ
勉強会や大家の会などのネットワークを通して、ほかの投資家と情報交換することも不動産投資詐欺を回避するのに役立ちます。なぜなら、情報交換を通して先輩大家の失敗談、時代ごとに流行している不動産投資詐欺の手口などを学べるからです。
ただし、大家のネットワーク自体が不動産投資詐欺の温床になっている可能性も否定できません。コミュニティに参加する場合、事前に評判やうわさをリサーチすることが大切です。
回避方法7.契約前に現地調査を行う
本記事の前半でお伝えしたように、不動産投資の詐欺には、満室を装って契約を持ちかける手口があります。契約前に現地調査を行うことで「周辺の物件が空室だらけなのに満室なのはおかしい」「生活実態が感じられないのでカーテンスキームではないか」といったことに気づいて詐欺を回避できる可能性もあります。
しかし、すでに入居者が生活しているオーナーチェンジ物件では、実際に住戸内を見学することはできません。カーテンがついているかどうか外からチェックするのはできるものの、カーテンスキームを完全に見破るのは難しいでしょう。
そういったときは、ガスや電気などインフラのメーターが作動しているか、夜間現地を見に行ったときに明かりのついている瞬間があるか、郵便物や新聞の投函、ベランダの洗濯物など人の住んでいる気配はあるかといった点をチェックするのがおすすめです。
オーナーチェンジ物件における現地調査の具体的な方法は、こちらの記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
回避方法8.過去の常識と今の常識が異なることを意識する
土地の価格が全国的に高騰していたバブル期であれば、不動産といえば高価なものというのが常識でした。その時代の常識を引きずったままだと正しい判断ができなくなり、悪質な不動産会社の餌食になってしまう恐れがあります。過去の常識と今の常識は異なることを理解し、提案された物件におかしなところがあるとき、「これは何だか怪しい」と気付けるようにしておくことも大切です。
実際、最近は相場の数倍にもなる法外な価格で不動産を購入させ、金銭をだまし取る不動産詐欺が後を断ちません。2024年の不動産詐欺事件として2つ目に紹介したケースもそうですが、こうした事件では持分の一部のみを購入させるのがよくある手口です。残りの持分の一部を売主の不動産会社が保有しておくことで、被害者たちと不動産会社の共同所有とし、購入した個人が自由に売却するのを防いでいるのです。
こうした不動産詐欺のターゲットになりやすいのが高齢者です。高齢者はバブル期までの常識を今の常識として考えていることも多く、正しい相場を理解しないまま不動産会社の言い値で購入してしまう傾向があります。契約を疑う視点も乏しいので、問題だらけのずさんな契約書をしっかりチェックせず、成り行きで契約してしまうケースも少なくありません。
昨今、東京都心でマンション価格が歴史的に高騰している一方、郊外や地方では値下がりに歯止めがかからない地域も多くあります。全国的に地価が上がっているのではなく、利便性や将来性によって、地域間の格差が大きくなっているということです。時期による相場の変動も大きいため、常に最新の情報をチェックしておく必要があるでしょう。
これらを「今の常識」として、今一度認識を改めることが、不動産詐欺を回避するために大切なポイントです。
【参考】健美家「横行する不動産投資詐欺にご用心。仕入れ値の10倍で販売。言い値を信じてはいけない」2024年6月7日掲載
不動産投資詐欺に遭ってしまった場合の相談先
どれだけ知識をつけ、パートナーとなる不動産会社を慎重に選んだとしても、詐欺に遭う可能性をゼロにはできません。
「詐欺に遭ってしまった」「詐欺に遭ってしまったかもしれない」と思った時は、すぐに以下のような機関へ相談することをおすすめします。
|
相談先 |
特徴 |
|---|---|
|
国民生活センター(消費生活センター) |
都道府県・市区町村に設置されている消費者トラブルに関する相談窓口。 |
|
保証協会 |
宅建業を営む不動産会社が加盟する団体。 |
|
免許行政庁 |
宅建業免許を交付する国土交通省や都道府県の窓口。 |
|
弁護士 |
法律のスペシャリスト。 |
相談先1.国民生活センター(消費生活センター)
国民生活センターは、消費者トラブルの未然防止やトラブル解決のための支援を行う独立行政法人。相談窓口が各都道府県・市町村に設置されています。
トラブルの内容に対して、適切な相談先の紹介や情報提供を公平な立場から行ってくれるのが特徴です。
国民生活センターの公式サイトによると、不動産投資詐欺に関する相談事例として、以下のものが挙げられています。
-
投資用マンションをしつこく勧誘され、事業者が怖くて契約をしてしまった
-
街頭アンケートに記入したら、投資用マンションを勧誘され契約してしまった
-
家賃保証があると勧誘され投資用マンションを購入したが、赤字になっている
-
事業者に指示されて虚偽申告でローン等を組んだが支払えない
【引用】独立行政法人国民生活センターHP「20歳代に増える投資用マンションの強引な勧誘に注意!-マンションへの投資にはリスクがあり、必ず儲かるわけではありません-」2019年3月28日掲載
局番なし「188(いやや)」の消費者ホットラインに電話すると、お近くの消費者生活相談窓口を案内してくれます。
-
相談内容:手付金やデート商法など
-
相談機関:国民生活センター
-
電話:消費者ホットライン局番なしの188
相談先2.保証協会
保証協会は正式には「宅地建物取引業保証協会」といい、宅建業を営む不動産会社が加盟する団体です。
「全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)」「不動産保証協会」などの公益社団法人は、宅建業者に対する苦情解決や手付金の保管・保証などの業務を行っています。所属する不動産会社に関する相談や苦情を受け付けており、トラブルの相手先が保証協会の会員の場合、相談することで解決に向けたサポートや手付金の保証をしてもらえる可能性があります。
また、不動産会社との間でトラブルが解決しない場合は、生じた債権を上限額まで弁済する制度もあるため消費者の強い味方です。
例えば、「手付金支払い後に業者と連絡が取れなくなった」「二重売買契約を締結された」「審査書類を改ざんされた」などのトラブルが発生した際に、相談を持ち掛けるといいでしょう。不動産会社と取引するにあたっては、事前に保証協会加盟の有無を確認しておくと、トラブルの発生を未然に防げる可能性があります。
- 相談内容:宅建業者に対する苦情解決や手付金の保証など
- 相談機関:全国宅地建物取引業保証協会、不動産保証協会
相談先3.免許行政庁
不動産の仲介やサブリースの広告、勧誘、重要事項説明などの違反については、国土交通省が管轄しており、連絡することで悪徳業者への行政指導や業務停止命令などをしてもらえる可能性があります。
国土交通省の公式サイトでは、以下のような勧誘トラブルは免許行政庁(国土交通省、都道府県)に相談するよう呼び掛けています。
-
断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる
-
長時間にわたって電話を切らせてくれなかった
-
深夜や早朝といった迷惑な時間に電話をかけられた
-
脅迫めいた発言があった
-
自宅に押しかけられ強引に契約を迫られた
-
絶対に儲かるから心配ないと言われた
【引用】国土交通省HP「国土交通省から消費者の皆さんへのお知らせ・注意喚起(マンションの悪質勧誘・訪問、アンケート調査等)」
不動産会社や営業担当者の職務におかしな点があると感じたら、一度相談してみましょう。
- 相談内容:仲介やサブリースに係わる業務
- 相談機関:国土交通省など
- 電話:国土交通省(代表):03-5253-8111
相談先4.弁護士
法律に関するトラブルは、法のスペシャリストである弁護士に相談するのも1つの手段です。弁護士にはそれぞれ得意分野があるので、不動産に詳しい弁護士に相談することが望ましいでしょう。相談事例としては、下記のようなものが挙げられます。
-
契約後に手付解除を申し出たら、違約金の請求をされた
-
執拗・強引な勧誘に押されて物件を購入したが、本意ではなく解約したい
-
サブリース契約で一方的に賃料を引き下げられ、損失を被り改善の余地がない
「弁護士を探す方法が分からない」「弁護士費用が気になる」という場合は、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所「法テラス」に相談してみましょう。無料法律相談や弁護士費用の立て替えも行っているため、経済的に不安がある方でも気軽に利用できます。
- 相談内容:不動産投資のトラブル全般
- 相談機関:日本司法支援センター 法テラス(外部リンク)など
- 電話:法テラス0570−078374(平日9〜21時、土曜9〜17時)
すでに被害が出ている場合や、緊急性が高い場合は警察へ
おどしや暴力を受けるなど身体への危険が生じる場合や、すでに被害が生じている場合は速やかに警察に連絡し、告訴状の提出を検討しましょう。特に、緊急性の高い場合は速やかに110番に通報しましょう。まだ詐欺なのかどうか定かでない場合は、警察相談専用窓口を利用することもできます。
- 警察への通報:110番
- 警察相談専用電話:#9110(平日8:30~17:15)
不動産投資詐欺グループ事件を題材にした映画や書籍
ここ最近、不動産投資詐欺グループによる事件が注目されるきっかけとなっているのが、大きな話題を読んだ映画や書籍の存在です。
特に注目を集めたのが、東京・五反田を舞台にした「積水ハウス地面死詐欺事件」でしょう。この事件は、大手ハウスメーカーが巨額の被害に遭うという被害の大きさもさることながら、「地面師」という存在を明るみにしたことでも話題となりました。当事件を題材にした書籍や映画を観た方も多いのではないでしょうか。
以下では、事件の内容を紹介するとともに、話題になった「地面師」についても解説していきます。
実際にあった積水ハウス地面師詐欺事件
「積水ハウス地面師詐欺事件」とは、大手ハウスメーカーの積水ハウスが、2017年4月から6月にかけて地面師グループによる詐欺の被害に遭い、物件の所有者ではない第三者と売買契約を締結し、最終的に約55億円ものお金をだまし取られた事件のことです。その後、積水ハウスが起こした刑事告訴をきっかけとして10名の地面師たちが起訴され、一部のメンバーが有罪となっています。
地面師たちは、本来の所有者ではない偽の所有者から土地を購入できるかのように見せかけ、積水ハウスと偽の所有者の間で不動産売買契約を締結させ、実際に所有権を移転することができないにもかかわらず、積水ハウスから売買代金などをだまし取ったのです。
この事件の舞台となった東京・五反田の土地は、都内の一等地にありながら古い廃旅館が放置されたままになっていて、デベロッパー各社が取得を狙っていました。しかし、その旅館のオーナーが長年所有し続けており、詐欺まがいの話も飛び交うなど、要注意物件として業界内で広く知られていました。
要注意とされていながら、業界でも有数の規模を誇る積水ハウスが詐欺の被害に遭った背景には、大きく2つの要因があるといわれています。
1つ目は、積水ハウス側のコンプライアンスに問題があったことです。当時の積水ハウスは、都心でのマンション用地買収を弱みとしており、当該物件のような都心の一等地にあるマンション用地を何とか仕入れたいと考えていました。そのため、要注意物件として本来であれば行うべき、所有者の本人確認や提示書類のチェックなどを怠っていたとみられています。また、土地購入の社内決裁も社長の先行承認で進められるなど、社内のチェック体制も機能しませんでした。
厳しい企業間競争にさらされている大手企業だからこそ、都心の一等地を何としても仕入れなければならないというプレッシャーが強くかかり、地面師たちの詐欺の餌食になってしまったとも考えられるのです。
そして、2つ目の要因が地面師たちの手口の巧妙さでした。地面師グループが偽造した書類はかなり精密なもので、公証人役場や司法書士といったプロがチェックしても偽造に気づけないほど、クオリティが高かったといわれています。
どれだけ巧妙な手口であっても、要注意物件であるとして社内のチェック体制がしっかり働いていれば気付ける可能性があったかもしれませんが、当時の積水ハウスのずさんなチェック体制ではなかなか見破ることができませんでした。
上記に挙げた2つの要因が重なったために、大手企業をターゲットにした前代未聞ともいえる巨額詐欺事件が引き起こされたのです。
【参考】笹日新聞DIGITAL「55億円だまし取られた積水ハウス 新旧会長対立の結末」2020年6月15日掲載
【参考】積水ハウス「分譲マンション用地の取引事故に関する総括検証報告書の受領及び公表について」2020年12月7日掲載
【参考】ダイヤモンド不動産研究所「なぜ積水ハウスは「地面師たち」にだまされたのか? 不動産詐欺にだまされないための対策も」2024年10月1日掲載
書籍や映画になった「地面師」
積水ハウス地面師詐欺事件で55億円もの大金をだまし取ったのは、地面師と呼ばれる人物たちのグループでした。地面師とは、不動産の所有者がほかにいるにもかかわらず、本当の所有者であるかのように見せかけて、買主に架空の売買契約を結ばせて金銭をだまし取る詐欺師のことをいいます。
2024年7月、Netflixで配信され話題となった配信ドラマ「地面師たち」でその存在を知った方も多いのではないでしょうか。このドラマおよび原作小説は、どちらも積水ハウス地面師詐欺事件をモデルとして描かれたものです。また、2018年には事件の真相に迫ったノンフィクション作品「地面師 他人の土地を売り飛ばす闇の詐欺集団」が発表されています。
大手企業が地面師たちによる巨額詐欺のターゲットになるということは、それだけ世の中に大きな衝撃を与えた出来事だったのです。
「地面師グループ」と紹介したように、地面師による詐欺は通常グループで行われます。詐欺のスキームを企画する主犯格のほか、対象となる不動産の情報を調査する役、本人確認書類や公的文書を精巧に偽造する役、所有者になりすます役、詐欺集団の窓口として買主と交渉する役、法律の専門家として取引遂行を支える役など、それぞれの役割を果たしながら詐欺を実行します。
地面師の活動は、戦後の混乱期で目立つようになったといわれています。その後、バブル期に土地価格が急激に高騰したことを受け、地面師による詐欺事件も多発しました。バブル崩壊後に一旦は低下した土地価格ですが、近年では東京都心部を中心に価格上昇傾向が強まっています。ここに目をつけた地面師たちは、年々進化する偽造技術とともに手口を巧妙化し、今もなおたびたび詐欺事件を引き起こしているのが現状です。
地面師詐欺のターゲットになりやすい高齢者
積水ハウス地面師詐欺事件で世の中に広く知られるようになった地面師ですが、それ以降も地面師による詐欺事件は発生しています。地面師の厄介なところは、何といっても精密な偽造技術を持っている点です。本来、取引の正当性を確認するのに使われる売買契約書や重要事項説明書、本人確認書類、登記情報などをすべて精巧に偽造するため、あまり不動産の知識のない買主だと簡単にだまされてしまいます。
積水ハウスの事件を踏まえると、地面師たちの標的になるのは企業のみだと考えてしまいがちですが、実際には個人の不動産オーナーが被害に遭うケースも少なくありません。特に、不動産に関する専門知識が不足している高齢者がターゲットになる例が多いといわれています。
中には、信頼性のある大手不動産会社を装って個人に接近し、偽の所有者になりすまして売買契約を締結させ、そのまま消息を断つといった悪質な事例も見られます。一般的に信頼性の高い大手不動産会社であっても、少しでも怪しいところがあれば弁護士などの専門家に相談するなど、日頃から自衛の意識をしっかりと持つことも大切です。
【参考】事業承継ドットコム「地面師とは何者か?驚愕の歴史から最新の巧妙な手口と進化を徹底解明」2024年7月8日掲載
【参考】GRO-BELラボ「【実話・元ネタ】70代女性が63億円詐欺の犯人?…Netflixドラマ「地面師たち」で話題の地面師の手口 モデルとなった積水ハウス詐欺事件の事例を解説」 2024年10月29日更新
まとめ
この記事では、不動産投資詐欺に遭わないために知っておくべき悪徳業者の手口や特徴、回避方法などについて解説しました。
不動産投資詐欺を回避するのに、最も大切なのは「気をつけていても詐欺に遭う可能性がある」というのを認識することです。「自分が詐欺に遭うわけがない」と自信過剰な人ほど、知らぬ間に悪徳業者の策略にはまり、大きな損害を被ってしまうかもしれません。。
投資物件の売買契約を締結する前には、一度立ち止まって「詐欺に遭っている可能性がないか」再度チェックしてみましょう。
ベルテックスでは不動産にまつわるセミナーを開催しています。今回紹介した不動産投資詐欺の対策をはじめ、リスク対策に関しても一から学ぶことが可能です。不動産投資初心者向けのコンテンツもご用意しているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
<法律監修:藤垣法律事務所>
この記事を監修した人
藤垣 圭介
法律監修・弁護士
藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業、東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後、2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。
この記事を書いた人
ベルテックスコラム事務局
不動産コンサルタント・税理士
不動産ソリューションの面白さや基礎、役に立つ情報や体験談などをフラットな目線で分かりやすくご紹介。宅建士・ファイナンシャルプランナー・税理士など有資格者の知見を生かしつつ、経験豊かなライターたちが不動産投資でおさえておきたいポイントをお届けします。
- TOP
- 会社員のための不動産投資マガジン
- 記事一覧
- 不動産投資詐欺の5つの手口!悪徳業者の特徴や回避方法、相談先も解説
2026.02.09
ベルテックスコラム事務局
不動産投資詐欺の5つの手口!悪徳業者の特徴や回避方法、相談先も解説
- リスク
- 詐欺
- 弁護士
- 監修記事
不動産投資は、資産運用の有効な手段のひとつとして注目されています。一方で悪徳業者による詐欺被害が後を絶たないことも事実です。
2024年7月にNetflixで配信されたドラマ「地面師たち」が話題になったこともあり、あらためて不動産にまつわる詐欺事件への注目度が高まっています。投資する金額の大きな不動産投資は、一度詐欺師のターゲットになると大きな損害を負うことになりかねません。不動産投資詐欺に遭わないためには、悪徳業者の手口や特徴、回避方法などを十分に知っておくことが大切です。
不動産投資詐欺のよくある手口として、以下の5つが挙げられます。
|
手口 |
特徴 |
|---|---|
|
手付金を利用した詐欺 |
買い手に手付金を支払わせるが、物件を引き渡さずに音信不通になる。 |
|
婚活サイトやマッチングアプリを利用した詐欺 |
デートを重ねて信頼関係が構築されたタイミングで、収益性が見込めないような投資用不動産を購入するよう勧誘される。購入すると音信不通になる(ロマンス詐欺)。 |
|
サブリース方式による詐欺 |
過大なメリットがあるかのような説明を口頭で行い、実際はオーナーに不利な内容のサブリース方式契約(マスターリース契約)を結ぶ。 マスターリース契約はオーナーが賃貸人、サブリース会社が賃借人となるため、オーナーに不利な契約でも解除するのが難しくなる。 |
|
満室を偽装する詐欺 |
サクラを入居させて満室を装い、投資家に物件を購入させる。 |
|
海外不動産投資詐欺 |
海外の物件を |
この記事では、このような不動産投資で詐欺に遭わないために必要な情報をまとめて解説します。
そもそも詐欺罪とは?定義を確認
不動産投資詐欺を詳しく見ていく前に、まずは詐欺罪の定義や構成要件について確認しておきましょう。詐欺罪は、刑法第246条において次のように定められています。
第二百四十六条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
【引用】e-GOV 法令検索「刑法(明治四十年法律第四十五号)」2024年11月2日現在
上記より詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させる「1項詐欺罪」と、財産上不法な利益を得たり他人に得させたりした場合に適用される「2項詐欺罪(詐欺利得罪)」の2つから構成されます。
不動産投資の例では、「この物件を運用して利益を分配する」と偽って、投資家から資金をだまし取るといった場合が1項詐欺罪にあたります。一方、投資家から貸付を受けている業者が、貸金債権を架空の不動産投資に活用するよう勧誘し、不動産投資と引き換えに貸金の返還義務を免除させた、という場合には2項詐欺罪に該当します。
通説によると、詐欺罪が成立するには、次に挙げる4つの構成要件を満たす必要があります。
-
被害者を欺くこと(加害者による欺罔(ぎもう)行為)
-
被害者が欺かれること(被害者の錯誤)
-
被害者が加害者に対して金銭や財物を交付・移転すること(被害者による交付行為)
-
1〜3までに因果関係があり、連鎖的に起こっていること
とりわけ3において、被害者から加害者への金銭や財物の移転が完了すると、詐欺罪が成立したとみなされる可能性が高まります。なお、1〜3のうち、いずれか1つでも因果関係が認められない場合、詐欺罪ではなく「詐欺未遂罪」が成立するのが通説です。
詐欺罪と窃盗罪はどう違う?
加害者が被害者の金銭や財産を奪うという点では、詐欺罪と窃盗罪は共通しています。この2つの罪の大きな違いは、上で紹介した詐欺罪の構成要件③の部分です。詐欺罪は被害者が自分で金銭や財物を交付することが要件となっているのに対し、窃盗罪は「加害者が被害者の意思に反して金銭や財物を奪い取る」というのが要件です。
また、2項詐欺罪が犯罪として成立する一方、財物上の利益を奪う窃盗は「利益窃盗」と呼ばれ、処罰の対象にならないとされています。
詐欺罪と横領罪はどう違う?
詐欺罪と横領罪の違いは、対象となる財物を加害者が占有しているのか、被害者が占有しているのかという点です。被害者が占有する金銭や財物を加害者に交付させれば詐欺罪、被害者から占有を委託された金銭や財物を勝手に自分のものにすると横領罪が成立するのが通説です。
被害者から金銭を奪い取るケースを例に見ると、加害者が自分の口座に金銭を振り込ませれば詐欺罪、被害者の口座管理を委託された加害者が勝手に自分の口座へ送金すると横領罪が成立するのが通説です。
【参考】弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 札幌支部「詐欺罪とは?不動産投資での事例を交えて解説」2023年10月15日掲載
【参考】横浜ロード法律事務所「窃盗罪」2024年11月2日現在
【参考】ネクスパート法律事務所「横領罪とは何か?他の犯罪との違いや刑罰について解説」2023年10月26日掲載
不動産投資詐欺でよくある5つの手口
上記のように、詐欺の被害に遭うと大切な財産を奪われてしまいます。詐欺師は、1回の詐欺行為でできるだけ多くの財産を手に入れたいと考えるため、取引金額の大きな不動産投資はターゲットになるリスクが高いといえます。詐欺によるリスクを回避し、不動産投資を成功させるには、どのような手口があるのか十分に理解しておくことが大切です。
不動産投資に関する詐欺には、主に以下の5つの手口があります。
手口1.手付金を利用した詐欺
手付金を利用した不動産投資詐欺では、売買契約のために支払った手付金を「持ち逃げされる」「だまし取られる」「返してもらえない」などのパターンがあります。
事例紹介
具体的な手付金詐欺の一例として、手付金の支払いをして売買契約を結んだのに、物件が引き渡されることなく、売主が行方をくらますといったケースが挙げられます。
手付金とは、不動産の売買契約時に買主から売主に支払われるお金です。不動産売買契約における手付金は「解約手付」といわれるもので、契約成立後も物件引渡し前であれば、手付金を放棄することで損害賠償を負うことなく契約の解除が可能となります。また、売主側も手付金の倍額を支払えば契約を解除できます。
このケースでは、不動産の所有権を有する本来の買主が詐欺を働くのではなく、仲介業者などが連携し、グループで計画を企てる場合がほとんどです。後ほど紹介する2017年に大きな話題となった「積水ハウス地面師詐欺事件」のように、地面師と呼ばれる詐欺師が所有権者や仲介業者になりすまし、書類の改ざんや偽の手続きなどを行います。
取引に違和感があれば、不動産会社や所有権者の書類を細かく確認する、近隣の人に本来の所有権者について聞き込みを行う、弁護士や司法書士などの専門家に相談するなどの対策を講じて、詐欺被害を予防するようにしましょう。
有効な対策
悪徳業者に不動産投資の手付金をだまし取られた場合は、取り返すのが困難になるケースも少なくありません。そのため、信頼できない不動産会社などにはそもそも手付金を渡さないことが大切です。なお、手付金をだまし取られた場合、保証協会に加入している宅建業者に対する苦情解決や手付金の保全を行う保証協会に相談することで手付金を取り戻せるケースもあります。(詳細は記事の後半で解説)
手口2.婚活サイトやマッチングアプリを利用した詐欺
「デート商法」「恋人商法」と呼ばれる詐欺は、異性の恋愛感情を利用して不動産などの高額な商品を売りつける詐欺です。一般的に「ロマンス詐欺」とも呼ばれます。
事例紹介
デートを重ねて相手が信用した段階で「2人の将来のために」などの甘い言葉を駆使して物件の契約を結ばせて、その後連絡が途絶えるといった事例があります。デート商法は、昔からある古典的な詐欺手法です。近年では、婚活サイトやマッチングアプリを通して知り合った異性に不動産などの高額商品を購入させる事例が増えています。
デート商法の不動産投資詐欺では、資産形成や資産運用のプロフェッショナルである「投資コンサルタント」「ファイナンシャルプランナー」などの職業を装い犯行に及ぶことが多い傾向にあります。こうした肩書きの信頼性に加え、個人的な信頼関係を構築することで「この人なら大丈夫だろう」と思わせて、詐欺行為を働くのです。
有効な対策
婚活サイトやマッチングアプリを通して知り合った異性が高額商品をしつこく勧めてきた場合は、疑うのが基本です。契約してしまった場合は、クーリングオフができる可能性もあります。また、2018年の消費者契約法の改正により、デート商法などの不当な勧誘による契約は後から取り消せるという規定が新設されました。条件に該当すればこれらの方法で解決を図ることができます。
ただし、上の規定を適用するには「社会生活上の経験が乏しい」などのいくつかの要件が定められているため、必ずしも契約を取り消せるとは限らない点に注意が必要です。
ロマンス詐欺に限らず、契約に不審な点を感じたら、消費者ホットライン「188」に電話すると、地域の消費生活相談窓口を案内してくれますので、活用しましょう。
婚活サイトやマッチングアプリでは、お互いの素性を隠しながら関係性を深めることも可能であるため、相手に少しでも怪しいところがあれば関係を見直す判断を下したほうがよいでしょう。
【参考】消費者庁「早わかり!消費者契約法」2024年11月14日現在
手口3.サブリース方式による詐欺
サブリース方式とは、一般的には「サブリース会社が物件を一括で借り上げ、毎月一定の賃料を納めることを前提に第三者へ転貸する一連の契約形態」を指します。
※厳密には、不動産会社やサブリース会社が、第三者へ転貸することを目的にオーナーから物件を借りる契約を「マスターリース」、この物件を不動産会社が入居者に貸す契約を「サブリース」と呼びます。
オーナーにとっては、空室があっても一定の家賃収入が保証されること・管理を委託できることなどが、サブリース方式で契約を結ぶメリットです。
サブリースを適正に利用すれば、空室リスクを軽減するのに役立ちます。しかし、サブリースを使ってオーナーを欺く事例が後を絶たないため要注意です。
しかし、実際は契約内容の説明自体に偽りがあったり、設定家賃が相場よりもはるかに安かったりといったトラブルが起きています。オーナーにとってのデメリットを説明されないまま、契約上「借主」であるサブリース会社側が契約弱者として守られてしまうのです。
こうしたケースでは、オーナーが十分な家賃を受け取ることができず、アパートローンの返済に苦しむことになります。
事例紹介
「30年一括借り上げ、家賃保証」といううたい文句に引かれてサブリース契約を結んだオーナーが、突如契約を打ち切られたという事例を紹介しましょう。サブリース契約は、物件所有者が貸主として見なされ、サブリース会社は借主として保護される立場関係にあります。
今回のケースでは、オーナーがサブリース会社より「○年にわたってサブリース家賃は下がらない」というような断定的な説明を受けたにもかかわらず、後日サブリース会社から借地借家法を盾に家賃の減額請求をされました。その後、さらに条件が悪くなり、最終的にはサブリース会社側から一方的に契約解除をされてしまったのです
しかし、その点に関しては契約書に明記されていました。サブリース会社は契約内容説明の際、あえてその点を省略して、メリットだけが目立つように説明を行いました。いざ契約を締結した後は、段階的に家賃を減額していき、収益が下がったタイミングなどで契約期間満了を待たずに契約を打ち切るのです。
国交省、消費者庁、金融庁が連名で作成した注意喚起を促す資料には、契約期間中に契約解除を迫られる事例なども紹介されています。
【参照】国土交通省「賃貸住宅経営(サブリース方式)に関する契約を締結する前に」 2025年2月7日現在
有効な対策
サブリース会社(不動産会社、賃貸管理会社など)は、サブリース契約を交わす前に重要事項について書面を交付して説明を行う義務があります。まずは、その内容をしっかり理解して疑問があったら確認することと、その疑問が払拭されなければ契約しないことが重要です。
また、サブリース会社が「家賃の値下がりがない」「家賃が保証される」といった不実のことを伝える勧誘行為は、賃貸住宅管理業法に抵触し、行政処分や契約の取り消し、損害賠償請求等の対象になる可能性があります。
トラブルに遭った際は、専門機関や不動産に強い弁護士に相談することをおすすめします。(詳細は本記事の後半で解説)
手口4.満室を装って契約を持ちかける詐欺
満室を装って契約を持ちかけられる不動産投資詐欺には、以下の2つのパターンがあります。
事例紹介
1つ目は、物件が売りに出されている間、関係者などに頼んで満室にしておき、物件売却後に関係者を退去させる手口です。
例えば、一棟アパートの購入者が「最初の1カ月は家賃が振り込まれていたのに翌月になると半分近くが退去した」という事例があります。
「満室で十分な家賃収入が見込める」「空室が発生しても他の部屋でフォローできる」という点に惹かれて購入した物件ですが、同時期に複数の世帯で退去が発生しました。これは、売却を有利にするために、売主が仕込んだサクラの入居者です。
しかし、売主が満室であることを偽装していたのかどうかを、証拠を持って立証するのは極めて困難です。このような場合、売主の責任を追及することが難しく、買主は新たな入居付けに追われます。
2つ目は、不動産投資の世界で「カーテンスキーム」と呼ばれる詐欺です。これは、物件を売りに出している間、空き部屋にカーテンを取り付けて入居者がいるように見せかける手口です。
完全に見破ることは難しいですが、いずれにしても契約時に入居者の有無を書類で確認し、具体的にいつ頃から入居しているのかを把握しておきましょう。
有効な対策
満室を装って契約を持ちかける手口は、後から詐欺行為を立証することが困難です。そのため、売買契約を交わす前に見破ることが重要です。
具体的な対策としては、レントロール(各部屋の賃貸借条件や契約の現況をまとめた資料)を確認することが挙げられます。直近数カ月の間に新規契約している部屋が多い場合は、カーテンスキームの可能性を疑いましょう。ただし、レントロール自体を偽装しているケースもあるため注意が必要です。
カーテンスキームを見破るための対策として現地確認も重要です。部屋にカーテンが取り付けられていても、ポストや部屋の入口付近、駐車場の状況などから生活感が感じられないような場合は、安易に契約を進めないようにしましょう。
手口5.海外不動産への投資を持ちかける詐欺
同じ不動産投資でも、海外と国内では商慣習や法律が異なります。一般的に海外、特に発展途上国では詐欺に遭うリスクが高いため注意しましょう。
事例紹介
海外における不動産投資詐欺の事例としては「売買契約を交わしてお金を払ったのに、物件引渡し前に不動産会社との連絡が途絶えて公式サイトもなくなっていた」というようなケースが挙げられます。
海外の新築不動産では「プレビルド(Pre build)」の物件販売も珍しくありません。プレビルドとは、将来物件が完成することを前提に前もってお金を支払う契約方式のことです。
プレビルドでは、「予定していた期日までに物件が完成しない」「物件の引き渡しが受けられない」などのトラブル事例があります。
有効な対策
海外の不動産投資詐欺を見破るのは、上級者でも難しいのが実情です。トラブルが起きても日本の法律が及ばないことが多いため、国内の関係機関や弁護士に相談しても解決できない可能性も高いでしょう。よって、不動産投資の初心者が海外物件を買い付ける場合、国内市場に上場しているような大手デベロッパーを通して取引するのが安全でしょう。
自分が詐欺の当事者になっている3つのパターン
不動産投資では、知らない間に自身が詐欺に加担してしまうケースがあります。この場合、詐欺の被害者は自身が融資を受ける金融機関です。
-
審査書類の改ざん
-
二重売買契約
-
1法人1物件スキーム
自分が詐欺の当事者になっている代表的な上記3つのケースを具体的に解説します。
審査書類の改ざん
よくあるケースとして、ローン審査の通過が厳しいことを理由に不動産会社から促されて、審査書類の改ざんを行うことです。文書偽造はれっきとした詐欺行為の1つですので、絶対にしてはいけません。
例えば、金融機関から審査資料として求められる銀行口座残高のスクリーンショットを、不動産会社が画像編集するケースがあります。口座残高が実際よりも多くあるかのように見せかけて審査に通りやすくするわけです。
仮に偽装を見抜かれずに審査を通過したとしても、後々偽装が発覚した場合には、ローン残債の一括返済を求められます。このようなトラブルに巻き込まれないためにも、審査資料の提出をする際は不動産会社・金融機関・自分の三者が立ち合い、書類の内容に相違がないか確認しながら進めるようにしましょう。
二重売買契約
二重売買契約とは、不動産会社が作成した2パターンの契約書に署名・押印し、契約締結することを指します。具体的には、正式な契約書と、実際の売買価格よりも高い金額を記載した金融機関用のダミーとなる契約書を作成し、より多くの融資を引き出します。
悪質な業者になると、二種類の契約書を作成するリスクの説明もしないまま押印を求めてくることもあります。説明なしで押印をしたとしても、文書偽造に加担したことになってしまい、発覚時には同様に借入金の一括返済を求められる可能性があるので注意が必要です。
このようなトラブルを防止するためにも、最悪のシナリオで起こり得るリスクを理解し、決して不動産会社の言いなりにならないようにしましょう。
1法人1物件スキーム
1法人1物件スキームとは、物件を購入する度に新しく法人を立ち上げ、その都度新しい会社名義で融資を受けることを指します。この手法を用いることで、個人名義で借り入れるよりも多額の融資を受けられるようになります。
短期間のうちに通常は購入できない複数の物件を取得可能なので、事業拡大へ意欲的な人が加担してしまうケースが多いようです。しかし、既存の借り入れの存在を隠ぺいして融資を申し込むことは、詐欺行為に該当するのが通例です。
近年は、銀行同士の合併などによって異なる銀行間での情報共有が進んでいるため、1法人1物件スキームが発覚する可能性は以前より高まっているようです。借入金の一括返済を求められるような事態にならないよう、このようなスキームに加担しないよう気をつけましょう。
2024年本当にあった不動産投資詐欺事件
2024年も不動産投資詐欺に関する事件が後を断ちません。自分が不動産投資詐欺の被害者にも加害者にもならないためには、過去にあった事件の背景や原因を理解し、適切な対策を取っておくことが何よりも大切です。
ここでは、2024年にあった不動産投資詐欺事件の事例を2つ紹介します。
【2024年の事件1】自分の賃貸用物件が性風俗用に契約されていた
1つ目は、不動産仲介会社がマンションの管理会社をだまして、風俗店との賃貸借契約を仲介し、部屋を風俗店として違法に使用させていたという事件です。
この事件では、風俗店を運営するための部屋を探していた風俗店経営者に対して、不動産仲介業を営む男が物件を紹介すると言って接触。風俗店の従業員を住人とする虚偽の申し込み書類を作成して管理会社に送付し、実態と異なる契約を結んだとされています。最終的に、物件を仲介した不動産仲介業を営む男、部屋を使って風俗店を運営していた経営者と従業員の3人が逮捕されました。
この事件のポイントは、舞台となったマンションがサブリース物件だった点です。物件を仲介した男は、マンションオーナーとサブリース契約を締結していた管理会社から入居者審査を任されていたとみられ、賃貸人の情報や部屋の使用目的などを偽って契約できる立場にありました。管理会社やオーナー自身が厳格な入居審査を行う体制になっていれば、このような結果にはなっていなかったかもしれません。
近年、都心では店舗型風俗店への規制が強まっており、新規開業はほとんど不可能となっています。そのような中で違法営業をする物件としてターゲットになっているのが、管理人が常駐しておらず、管理体制が甘いマンションです。こうした事例は近年増加傾向にあるため、都心の投資物件を選ぶ際は、管理体制をしっかりチェックしておく必要があります。
【参考】時事通信ニュース「風俗店と知りながら賃貸契約仲介=容疑で不動産会社社長逮捕―警視庁」2024年9月18日掲載
【参考】livedoor News「隣室が風俗店になることも「夜専門の不動産屋」転貸で風俗営業して逮捕…増殖する「違法マンションエステ」の実態とは」2024年9月20日掲載
【2024年の事件2】高齢の母がインターネットで不動産を購入させられていた
2つ目に紹介するのは、認知症を患う高齢の母が、インターネットで不当に投資用不動産を購入させられていた事例です。
詐欺の被害に遭ったのは、千葉県内で1人暮らしをしていた80代の女性。6年前に認知症の診断を受けましたが、一人で気ままに暮らすことを希望していたため、ヘルパーやケアマネージャーによる支援のもと生活していました。
そんな女性の異変に気付いたのは、定期的に母親のもとを訪れていた娘でした。ある日、母親の預金通帳を見てみると、まったく心当たりのない約300万円の振り込みが記録されていたのです。あらためて振込先を確認したところ、都内にある不動産販売会社であることが判明します。
この会社に問い合わせてみると、母親が神奈川県内の投資用マンションの1室を購入したということを知らされます。しかし、母親に聞いても「買っていない」と話すばかりでした。会社側に契約書を送ってもらうと、確かに母親の直筆の署名と印鑑が押されていました。そして、購入したのがマンションの1室ではなく、持分の一部のみだったことも判明します。
購入した物件は第三者に賃貸されており、母親の口座には月2,500円のわずかな賃料収入が振り込まれる契約になっていたものの、300万円を回収しようとすれば100年はかかる計算になり、80代の母親の投資物件としては到底ふさわしくないものでした。
2024年6月、この物件を販売していた不動産販売会社勤務の4人が逮捕されます。今回の件とは別の80代の認知症を患う女性に、神奈川県内のアパートの部屋を購入させ、5,000万円もの金銭をだまし取った疑いによる逮捕でした。彼らは認知症の高齢者などを狙い、1年間で7億円もの売上を上げていたのです。
この例のように、判断能力の低下した高齢者を狙った不動産投資詐欺事件も増えています。資産管理を本人が行っていると、子どもや親族が気づかない間に、悪質業者の手口にだまされてしまうことも考えられます。
こうした事態を防ぐには、本人が健康で意思表示できるうちに、信頼できる子どもなどの家族・知人に資産管理を任せる、「家族信託」や「民事信託」を利用するのがおすすめです。全資産の管理を任せるのが不安であれば、一部のみ管理を委託することもできます。信託契約を結ぶときに契約内容を公正証書に残すとともに、ほかの信頼できる親族などを監督人としておくことで、トラブルを未然に防げるでしょう。
【参考】NHK「知らないうちにアパートの1室を~認知症高齢者狙う不動産詐欺」2024年7月31日掲載
不動産投資詐欺の業者に共通する特徴
不動産投資詐欺の業者は、以下に挙げる6つの特徴のいくつかが該当することが多いです。
特徴1.断定的にメリットを解説する
不動産投資は投資行為である以上、少なからずリスクが存在します。不動産という資産を手に入れられる点はメリットであるものの、資産価値が下がるリスクもゼロではなく、元本割れを起こす可能性も捨てきれません。
それにもかかわらず、不動産会社から「この物件は将来確実に値上がりする」「このエリアは将来性が期待でき、数年後には何倍の価値が出る」など、確実なリターンをイメージさせるような言葉が出てきたときは要注意です。
不動産投資のコンサルティングで営業担当者がメリットについて解説すること自体は問題ありません。しかし「値上がりする」「絶対に儲かる」といった将来利益の断定は宅地建物取引業法に抵触します。(法第47条の2第1項-不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為)不動産投資の詐欺業者は、こういった断定的な物言いをすることが多いです。
特徴2.事前にデメリットやリスクを伝えない
不動産投資のメリットばかり強調するセールストークも詐欺業者の特徴のひとつです。不動産投資も他の投資と同じようにデメリットやリスクがあります。これらのネガティブな情報についても丁寧に情報提供してくれるのが信頼できる不動産会社です。
例えば「高利回り」というワード。そもそも利回りは「年間家賃収入(または年間収益)÷物件価格」で計算されるものであり、物件価格が低いほど数値は高くなります。反対に、物件価格は「年間家賃収入(または年間収益)÷利回り」で計算できるため(収益還元法といいます)、利回りが高いほど物件価格が低く算出されることになるのです。
一般的に、都心部の物件や築浅の物件などは利回りが低く、反対に郊外の物件や中古物件などは利回りが高くなる傾向にあります。高利回りな物件と聞くと優良物件に感じるかもしれませんが、築年数が古かったり利便性が低かったりして、借り手がつきにくい訳あり物件の可能性もあるでしょう。
利回りだけで判断するリスクを説明することなく、単に「高利回りだから儲けやすい」というような話をされたら、何かしら問題があるのかもしれません。あらかじめ不動産会社に、利回りが低くなっている要因を詳しく聞いておくことをおすすめします。
特徴3.おとり広告などを掲載している
見込客を集めるために売る意思のない物件で釣ることを「おとり広告」、実在しない物件で釣ることを「虚偽広告」といいます。これらの広告は、宅地建物取引業法、不当景品類及び不当表示防止法などで禁止されています。入居者向けの賃貸募集でおとり広告や虚偽広告が使われるのが一般的ですが、不動産投資詐欺で用いられるケースもあります。
誰が見ても好条件の物件をおとり広告として掲出し、問い合わせてきた人に対して「この物件はとても人気ですでに売れてしまった」などと言って、ほかの条件が悪い物件を売りつけるというのがよくあるパターンです。いくら好条件だからといって、周辺地域における物件価格や利回りの相場とかけ離れた物件には、飛びつかないよう注意しましょう。
特徴4.事務所が雑居ビル、または存在しない
不動産投資の詐欺業者は、ある程度儲けた時点で計画倒産をしたり、姿をくらましたりするのを前提としていることも少なくありません。そのため、敷金の安い雑居ビルや、廉価な費用で契約できるレンタルオフィス、シェアオフィスに事務所を構えているケースも多くみられます。より悪質な場合には、虚偽の住所を表示していることもあるため注意が必要です。
特徴5.Webサイトが怪しい
不動産会社のWebサイトを検索してみると、詐欺業者を見分けられる場合もあります。最近は、不動産投資に関する情報もインターネットで仕入れる方が多いため、優良な不動産会社であればWebサイトの整備や更新に力を入れているのが一般的です。
しかし、悪質な不動産会社はWebサイトを詐欺勧誘の入口としか捉えていない節があります。次のような特徴に当てはまる場合、取引は避けたほうが無難です。
- Webサイトがしばらく更新されていない
- 取引事例が十分に掲載されていない
- 事務所の住所や問い合わせ先がどこにもない
- 代表やスタッフの名前や写真が掲載されていない
特徴6.契約締結を急かす
不動産投資詐欺を企てている悪質業者は、「この物件は人気なので早くしないと売れてしまう」「すでに購入を検討している方がいるので早い者勝ち」「今すぐ決断したほうがいい」など、言葉巧みに契約締結を急かす傾向があります。
買主に考える時間や他人に相談する時間を与えてしまうと、契約の問題点に気づいて、成約を逃してしまう恐れがあるからです。違法行為が明るみになる前に契約を成立させ、できるだけ早く代金を回収したいというのが悪質業者の本音でしょう。
本当に顧客のことを考えている不動産会社であれば、じっくり考えたうえで納得のいく物件を購入するよう促すはずです。契約を急がせるような言動があった場合には、その場では決断せず、持ち帰って第三者に相談したほうがいいかもしれません。
不動産投資詐欺を回避する8つの方法
いくつかのポイントを押さえておけば不動産投資詐欺のリスクを軽減できます。悪徳業者の被害に遭わないための主な方法は以下の8つです。
回避方法1.担当者の言動に注意する
不動産投資の詐欺業者の特徴には「断定的にメリットを解説する」「事前にデメリットやリスクを伝えない」などがありました。これらの特徴を踏まえ、営業担当者(コンサルタント)の言動から「いいことばかり言って、上手く乗せようとする」姿勢が見えた場合は契約を見送ることが大切です。物件に関する説明や、質問への回答もそこそこに手付金の支払いや契約締結を急かされた場合も、詐欺の可能性があるため注意しましょう。
回避方法2.不動産会社の事務所の所在を確認する
詐欺業者の事務所は雑居ビルに入居していたり、そもそも存在していなかったりするケースも多いのが実情です。そのため、担当者の名刺に書かれた事務所の住所をGoogle Earthで検索し、入居しているビルの雰囲気を確かめてみるのもよいでしょう。
ただし、「住所を偽っている」「レンタルオフィスやシェアオフィスに入居している」といった可能性もあります。違和感があるようなら、相手先の事務所での打ち合わせを打診して、現場をチェックするのがおすすめです。
回避方法3.不動産投資の基本知識を身につけておく
不動産投資の詐欺に遭った人の多くが、悪徳業者のセールストークを鵜呑みにしてしまっています。詐欺を回避するには、投資家自身が不動産投資に関する最低限の知識を身につけておくことが何より大切です。不動産投資に必要な知識を身につけるには、以下のような方法があります。
-
不動産投資をテーマにした本をなるべく多く読む
-
不動産取引や賃貸管理に関する資格を取得する(宅建士や賃管士など)
-
不動産投資セミナーに複数参加する
本やセミナーは知識を習得するのに有効ですが、著者や講師を限定してしまうと知識に偏りが生まれてしまいます。なるべく複数のプロの話を読み聞きして、多角的な視点を養いましょう。
ただ、勉強が大切なことは承知していても、何から手をつければいいのか疑問に思う方も少なくないはずです。学び方を知りたい不動産投資初心者の方は、こちらの記事をぜひ参考にしてください。
【おすすめ関連記事】不動産投資初心者向け勉強法!学ぶべきポイントや不安解消に役立つ本も紹介
回避方法4.不動産会社の情報を確認して信頼できるか見極める
「好印象の営業担当者だったので信用してしまった」「業者のことを調べずに契約してしまった」というのも不動産投資詐欺に遭う典型的なケースです。
不動産投資詐欺に遭わないためには、パートナーとなる不動産会社を選ぶ際、以下に挙げるような項目もチェックしておきましょう。
宅建業免許を取得しているか
物件仲介などの宅地建物取引業(宅建業)を営むには、事務所のある都道府県もしくは国土交通省による宅建業免許を取得しなければなりません。無免許で仲介業務を行うことは宅建業法に抵触します。特に不動産会社の規模が小さかったり社歴が浅かったりする場合は、念のため宅建業免許を持っているかを確認しましょう。国土交通省の「宅地建物取引業者 検索」を利用すると簡単に宅地建物取引業者を確認できます。
一定期間の社歴があるか
社歴は長いほど安全ですが「創業から10年以上」というのがひとつの目安になるでしょう。創業から10年以内に大半の企業が淘汰されるといわれており、10年以上生き残ってきたのであれば、一定の信頼を獲得してきたと考えられるからです。
社員数や資本金が多いか
不動産業は資本力が重要な業種なので、資本金が1,000万円以下の企業だと不安があります。また、社員数も企業の信用力を測る指標のひとつです。不動産投資初心者が安心して任せられるパートナーを探す場合、100名以上の規模感が目安となります。
過去に行政処分を受けていないか
前述のように、不動産業を営むには宅建業免許を取得する必要があります。宅建業法に違反すると行政処分の対象となり、処分を受けた会社は免許権者である国土交通省や都道府県から、事業者名、処分を受けた日、処分等の種類を公表されます。過去に処分を受けた会社はコンプライアンスに対する意識が希薄な可能性もあるので、取引には慎重になったほうがよいでしょう。
宅建業法に基づく行政処分の内容は、国土交通省や自治体のWebサイトで簡単に検索できます。不動産会社の情報を調べる際は、過去に行政処分を受けていないもチェックしておくのがおすすめです。
一般媒介契約で複数社と契約する
物件の売買にあたっては、不動産会社と媒介契約を締結するケースがほとんどです。媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。3つの契約の違いをまとめると次のとおりです。
|
一般媒介契約 |
専任媒介契約 |
専属専任媒介契約 |
|
|
契約できる会社数 |
複数社 |
1社のみ |
1社のみ |
|
契約期間 |
任意 |
最長3ヵ月まで |
最長3ヵ月まで |
|
業務状況の報告義務 |
なし |
2週間に1回以上 |
1週間に1回以上 |
|
レインズの登録義務 |
なし |
契約締結後7日以内 |
契約締結後5日以内 |
|
自己発見取引 |
できる |
できる |
できない |
専任媒介契約、専属専任媒介契約では1社だけとしか契約できないのに対し、一般媒介契約は複数の不動産会社と締結することができます。
専任媒介契約や専属専任媒介契約を締結すると、契約期間内の成約でほぼ確実に仲介手数料を得ることができるため、不動産会社側のモチベーションが上がるというのはメリットです。しかし、1社と契約するだけでは、サービスや対応の質がいいのか悪いのか判断がつきません。
信頼できる不動産会社なのか見極めたいのであれば、不動産購入時の仲介は一般媒介契約として、複数の会社を比較することをおすすめします。
回避方法5.不明点や納得できないことがある場合は話を進めない
「相手は不動産のプロだから言うことを聞いていればいい」といった受け身な考え方はやめましょう。不動産投資は投資行為であるとともに賃貸経営でもあります。投資も事業も自己責任で行うものであり、損失やリスクも最終的にはオーナーが負わなければなりません。
「何かあったときに困るのは自分」という危機意識を持って、不明点や納得できない点は契約前に解消しておきましょう。どうしても不安や疑問を解消できないなら、それ以上契約を進めるべきではありません。
回避方法6.不動産投資の成功者とつながりを持つ
勉強会や大家の会などのネットワークを通して、ほかの投資家と情報交換することも不動産投資詐欺を回避するのに役立ちます。なぜなら、情報交換を通して先輩大家の失敗談、時代ごとに流行している不動産投資詐欺の手口などを学べるからです。
ただし、大家のネットワーク自体が不動産投資詐欺の温床になっている可能性も否定できません。コミュニティに参加する場合、事前に評判やうわさをリサーチすることが大切です。
回避方法7.契約前に現地調査を行う
本記事の前半でお伝えしたように、不動産投資の詐欺には、満室を装って契約を持ちかける手口があります。契約前に現地調査を行うことで「周辺の物件が空室だらけなのに満室なのはおかしい」「生活実態が感じられないのでカーテンスキームではないか」といったことに気づいて詐欺を回避できる可能性もあります。
しかし、すでに入居者が生活しているオーナーチェンジ物件では、実際に住戸内を見学することはできません。カーテンがついているかどうか外からチェックするのはできるものの、カーテンスキームを完全に見破るのは難しいでしょう。
そういったときは、ガスや電気などインフラのメーターが作動しているか、夜間現地を見に行ったときに明かりのついている瞬間があるか、郵便物や新聞の投函、ベランダの洗濯物など人の住んでいる気配はあるかといった点をチェックするのがおすすめです。
オーナーチェンジ物件における現地調査の具体的な方法は、こちらの記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
回避方法8.過去の常識と今の常識が異なることを意識する
土地の価格が全国的に高騰していたバブル期であれば、不動産といえば高価なものというのが常識でした。その時代の常識を引きずったままだと正しい判断ができなくなり、悪質な不動産会社の餌食になってしまう恐れがあります。過去の常識と今の常識は異なることを理解し、提案された物件におかしなところがあるとき、「これは何だか怪しい」と気付けるようにしておくことも大切です。
実際、最近は相場の数倍にもなる法外な価格で不動産を購入させ、金銭をだまし取る不動産詐欺が後を断ちません。2024年の不動産詐欺事件として2つ目に紹介したケースもそうですが、こうした事件では持分の一部のみを購入させるのがよくある手口です。残りの持分の一部を売主の不動産会社が保有しておくことで、被害者たちと不動産会社の共同所有とし、購入した個人が自由に売却するのを防いでいるのです。
こうした不動産詐欺のターゲットになりやすいのが高齢者です。高齢者はバブル期までの常識を今の常識として考えていることも多く、正しい相場を理解しないまま不動産会社の言い値で購入してしまう傾向があります。契約を疑う視点も乏しいので、問題だらけのずさんな契約書をしっかりチェックせず、成り行きで契約してしまうケースも少なくありません。
昨今、東京都心でマンション価格が歴史的に高騰している一方、郊外や地方では値下がりに歯止めがかからない地域も多くあります。全国的に地価が上がっているのではなく、利便性や将来性によって、地域間の格差が大きくなっているということです。時期による相場の変動も大きいため、常に最新の情報をチェックしておく必要があるでしょう。
これらを「今の常識」として、今一度認識を改めることが、不動産詐欺を回避するために大切なポイントです。
【参考】健美家「横行する不動産投資詐欺にご用心。仕入れ値の10倍で販売。言い値を信じてはいけない」2024年6月7日掲載
不動産投資詐欺に遭ってしまった場合の相談先
どれだけ知識をつけ、パートナーとなる不動産会社を慎重に選んだとしても、詐欺に遭う可能性をゼロにはできません。
「詐欺に遭ってしまった」「詐欺に遭ってしまったかもしれない」と思った時は、すぐに以下のような機関へ相談することをおすすめします。
|
相談先 |
特徴 |
|---|---|
|
国民生活センター(消費生活センター) |
都道府県・市区町村に設置されている消費者トラブルに関する相談窓口。 |
|
保証協会 |
宅建業を営む不動産会社が加盟する団体。 |
|
免許行政庁 |
宅建業免許を交付する国土交通省や都道府県の窓口。 |
|
弁護士 |
法律のスペシャリスト。 |
相談先1.国民生活センター(消費生活センター)
国民生活センターは、消費者トラブルの未然防止やトラブル解決のための支援を行う独立行政法人。相談窓口が各都道府県・市町村に設置されています。
トラブルの内容に対して、適切な相談先の紹介や情報提供を公平な立場から行ってくれるのが特徴です。
国民生活センターの公式サイトによると、不動産投資詐欺に関する相談事例として、以下のものが挙げられています。
-
投資用マンションをしつこく勧誘され、事業者が怖くて契約をしてしまった
-
街頭アンケートに記入したら、投資用マンションを勧誘され契約してしまった
-
家賃保証があると勧誘され投資用マンションを購入したが、赤字になっている
-
事業者に指示されて虚偽申告でローン等を組んだが支払えない
【引用】独立行政法人国民生活センターHP「20歳代に増える投資用マンションの強引な勧誘に注意!-マンションへの投資にはリスクがあり、必ず儲かるわけではありません-」2019年3月28日掲載
局番なし「188(いやや)」の消費者ホットラインに電話すると、お近くの消費者生活相談窓口を案内してくれます。
-
相談内容:手付金やデート商法など
-
相談機関:国民生活センター
-
電話:消費者ホットライン局番なしの188
相談先2.保証協会
保証協会は正式には「宅地建物取引業保証協会」といい、宅建業を営む不動産会社が加盟する団体です。
「全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)」「不動産保証協会」などの公益社団法人は、宅建業者に対する苦情解決や手付金の保管・保証などの業務を行っています。所属する不動産会社に関する相談や苦情を受け付けており、トラブルの相手先が保証協会の会員の場合、相談することで解決に向けたサポートや手付金の保証をしてもらえる可能性があります。
また、不動産会社との間でトラブルが解決しない場合は、生じた債権を上限額まで弁済する制度もあるため消費者の強い味方です。
例えば、「手付金支払い後に業者と連絡が取れなくなった」「二重売買契約を締結された」「審査書類を改ざんされた」などのトラブルが発生した際に、相談を持ち掛けるといいでしょう。不動産会社と取引するにあたっては、事前に保証協会加盟の有無を確認しておくと、トラブルの発生を未然に防げる可能性があります。
- 相談内容:宅建業者に対する苦情解決や手付金の保証など
- 相談機関:全国宅地建物取引業保証協会、不動産保証協会
相談先3.免許行政庁
不動産の仲介やサブリースの広告、勧誘、重要事項説明などの違反については、国土交通省が管轄しており、連絡することで悪徳業者への行政指導や業務停止命令などをしてもらえる可能性があります。
国土交通省の公式サイトでは、以下のような勧誘トラブルは免許行政庁(国土交通省、都道府県)に相談するよう呼び掛けています。
-
断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる
-
長時間にわたって電話を切らせてくれなかった
-
深夜や早朝といった迷惑な時間に電話をかけられた
-
脅迫めいた発言があった
-
自宅に押しかけられ強引に契約を迫られた
-
絶対に儲かるから心配ないと言われた
【引用】国土交通省HP「国土交通省から消費者の皆さんへのお知らせ・注意喚起(マンションの悪質勧誘・訪問、アンケート調査等)」
不動産会社や営業担当者の職務におかしな点があると感じたら、一度相談してみましょう。
- 相談内容:仲介やサブリースに係わる業務
- 相談機関:国土交通省など
- 電話:国土交通省(代表):03-5253-8111
相談先4.弁護士
法律に関するトラブルは、法のスペシャリストである弁護士に相談するのも1つの手段です。弁護士にはそれぞれ得意分野があるので、不動産に詳しい弁護士に相談することが望ましいでしょう。相談事例としては、下記のようなものが挙げられます。
-
契約後に手付解除を申し出たら、違約金の請求をされた
-
執拗・強引な勧誘に押されて物件を購入したが、本意ではなく解約したい
-
サブリース契約で一方的に賃料を引き下げられ、損失を被り改善の余地がない
「弁護士を探す方法が分からない」「弁護士費用が気になる」という場合は、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所「法テラス」に相談してみましょう。無料法律相談や弁護士費用の立て替えも行っているため、経済的に不安がある方でも気軽に利用できます。
- 相談内容:不動産投資のトラブル全般
- 相談機関:日本司法支援センター 法テラス(外部リンク)など
- 電話:法テラス0570−078374(平日9〜21時、土曜9〜17時)
すでに被害が出ている場合や、緊急性が高い場合は警察へ
おどしや暴力を受けるなど身体への危険が生じる場合や、すでに被害が生じている場合は速やかに警察に連絡し、告訴状の提出を検討しましょう。特に、緊急性の高い場合は速やかに110番に通報しましょう。まだ詐欺なのかどうか定かでない場合は、警察相談専用窓口を利用することもできます。
- 警察への通報:110番
- 警察相談専用電話:#9110(平日8:30~17:15)
不動産投資詐欺グループ事件を題材にした映画や書籍
ここ最近、不動産投資詐欺グループによる事件が注目されるきっかけとなっているのが、大きな話題を読んだ映画や書籍の存在です。
特に注目を集めたのが、東京・五反田を舞台にした「積水ハウス地面死詐欺事件」でしょう。この事件は、大手ハウスメーカーが巨額の被害に遭うという被害の大きさもさることながら、「地面師」という存在を明るみにしたことでも話題となりました。当事件を題材にした書籍や映画を観た方も多いのではないでしょうか。
以下では、事件の内容を紹介するとともに、話題になった「地面師」についても解説していきます。
実際にあった積水ハウス地面師詐欺事件
「積水ハウス地面師詐欺事件」とは、大手ハウスメーカーの積水ハウスが、2017年4月から6月にかけて地面師グループによる詐欺の被害に遭い、物件の所有者ではない第三者と売買契約を締結し、最終的に約55億円ものお金をだまし取られた事件のことです。その後、積水ハウスが起こした刑事告訴をきっかけとして10名の地面師たちが起訴され、一部のメンバーが有罪となっています。
地面師たちは、本来の所有者ではない偽の所有者から土地を購入できるかのように見せかけ、積水ハウスと偽の所有者の間で不動産売買契約を締結させ、実際に所有権を移転することができないにもかかわらず、積水ハウスから売買代金などをだまし取ったのです。
この事件の舞台となった東京・五反田の土地は、都内の一等地にありながら古い廃旅館が放置されたままになっていて、デベロッパー各社が取得を狙っていました。しかし、その旅館のオーナーが長年所有し続けており、詐欺まがいの話も飛び交うなど、要注意物件として業界内で広く知られていました。
要注意とされていながら、業界でも有数の規模を誇る積水ハウスが詐欺の被害に遭った背景には、大きく2つの要因があるといわれています。
1つ目は、積水ハウス側のコンプライアンスに問題があったことです。当時の積水ハウスは、都心でのマンション用地買収を弱みとしており、当該物件のような都心の一等地にあるマンション用地を何とか仕入れたいと考えていました。そのため、要注意物件として本来であれば行うべき、所有者の本人確認や提示書類のチェックなどを怠っていたとみられています。また、土地購入の社内決裁も社長の先行承認で進められるなど、社内のチェック体制も機能しませんでした。
厳しい企業間競争にさらされている大手企業だからこそ、都心の一等地を何としても仕入れなければならないというプレッシャーが強くかかり、地面師たちの詐欺の餌食になってしまったとも考えられるのです。
そして、2つ目の要因が地面師たちの手口の巧妙さでした。地面師グループが偽造した書類はかなり精密なもので、公証人役場や司法書士といったプロがチェックしても偽造に気づけないほど、クオリティが高かったといわれています。
どれだけ巧妙な手口であっても、要注意物件であるとして社内のチェック体制がしっかり働いていれば気付ける可能性があったかもしれませんが、当時の積水ハウスのずさんなチェック体制ではなかなか見破ることができませんでした。
上記に挙げた2つの要因が重なったために、大手企業をターゲットにした前代未聞ともいえる巨額詐欺事件が引き起こされたのです。
【参考】笹日新聞DIGITAL「55億円だまし取られた積水ハウス 新旧会長対立の結末」2020年6月15日掲載
【参考】積水ハウス「分譲マンション用地の取引事故に関する総括検証報告書の受領及び公表について」2020年12月7日掲載
【参考】ダイヤモンド不動産研究所「なぜ積水ハウスは「地面師たち」にだまされたのか? 不動産詐欺にだまされないための対策も」2024年10月1日掲載
書籍や映画になった「地面師」
積水ハウス地面師詐欺事件で55億円もの大金をだまし取ったのは、地面師と呼ばれる人物たちのグループでした。地面師とは、不動産の所有者がほかにいるにもかかわらず、本当の所有者であるかのように見せかけて、買主に架空の売買契約を結ばせて金銭をだまし取る詐欺師のことをいいます。
2024年7月、Netflixで配信され話題となった配信ドラマ「地面師たち」でその存在を知った方も多いのではないでしょうか。このドラマおよび原作小説は、どちらも積水ハウス地面師詐欺事件をモデルとして描かれたものです。また、2018年には事件の真相に迫ったノンフィクション作品「地面師 他人の土地を売り飛ばす闇の詐欺集団」が発表されています。
大手企業が地面師たちによる巨額詐欺のターゲットになるということは、それだけ世の中に大きな衝撃を与えた出来事だったのです。
「地面師グループ」と紹介したように、地面師による詐欺は通常グループで行われます。詐欺のスキームを企画する主犯格のほか、対象となる不動産の情報を調査する役、本人確認書類や公的文書を精巧に偽造する役、所有者になりすます役、詐欺集団の窓口として買主と交渉する役、法律の専門家として取引遂行を支える役など、それぞれの役割を果たしながら詐欺を実行します。
地面師の活動は、戦後の混乱期で目立つようになったといわれています。その後、バブル期に土地価格が急激に高騰したことを受け、地面師による詐欺事件も多発しました。バブル崩壊後に一旦は低下した土地価格ですが、近年では東京都心部を中心に価格上昇傾向が強まっています。ここに目をつけた地面師たちは、年々進化する偽造技術とともに手口を巧妙化し、今もなおたびたび詐欺事件を引き起こしているのが現状です。
地面師詐欺のターゲットになりやすい高齢者
積水ハウス地面師詐欺事件で世の中に広く知られるようになった地面師ですが、それ以降も地面師による詐欺事件は発生しています。地面師の厄介なところは、何といっても精密な偽造技術を持っている点です。本来、取引の正当性を確認するのに使われる売買契約書や重要事項説明書、本人確認書類、登記情報などをすべて精巧に偽造するため、あまり不動産の知識のない買主だと簡単にだまされてしまいます。
積水ハウスの事件を踏まえると、地面師たちの標的になるのは企業のみだと考えてしまいがちですが、実際には個人の不動産オーナーが被害に遭うケースも少なくありません。特に、不動産に関する専門知識が不足している高齢者がターゲットになる例が多いといわれています。
中には、信頼性のある大手不動産会社を装って個人に接近し、偽の所有者になりすまして売買契約を締結させ、そのまま消息を断つといった悪質な事例も見られます。一般的に信頼性の高い大手不動産会社であっても、少しでも怪しいところがあれば弁護士などの専門家に相談するなど、日頃から自衛の意識をしっかりと持つことも大切です。
【参考】事業承継ドットコム「地面師とは何者か?驚愕の歴史から最新の巧妙な手口と進化を徹底解明」2024年7月8日掲載
【参考】GRO-BELラボ「【実話・元ネタ】70代女性が63億円詐欺の犯人?…Netflixドラマ「地面師たち」で話題の地面師の手口 モデルとなった積水ハウス詐欺事件の事例を解説」 2024年10月29日更新
まとめ
この記事では、不動産投資詐欺に遭わないために知っておくべき悪徳業者の手口や特徴、回避方法などについて解説しました。
不動産投資詐欺を回避するのに、最も大切なのは「気をつけていても詐欺に遭う可能性がある」というのを認識することです。「自分が詐欺に遭うわけがない」と自信過剰な人ほど、知らぬ間に悪徳業者の策略にはまり、大きな損害を被ってしまうかもしれません。。
投資物件の売買契約を締結する前には、一度立ち止まって「詐欺に遭っている可能性がないか」再度チェックしてみましょう。
ベルテックスでは不動産にまつわるセミナーを開催しています。今回紹介した不動産投資詐欺の対策をはじめ、リスク対策に関しても一から学ぶことが可能です。不動産投資初心者向けのコンテンツもご用意しているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
<法律監修:藤垣法律事務所>
この記事を監修した人
藤垣 圭介
法律監修・弁護士
藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業、東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後、2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。
この記事を書いた人
ベルテックスコラム事務局
不動産コンサルタント・税理士
不動産ソリューションの面白さや基礎、役に立つ情報や体験談などをフラットな目線で分かりやすくご紹介。宅建士・ファイナンシャルプランナー・税理士など有資格者の知見を生かしつつ、経験豊かなライターたちが不動産投資でおさえておきたいポイントをお届けします。