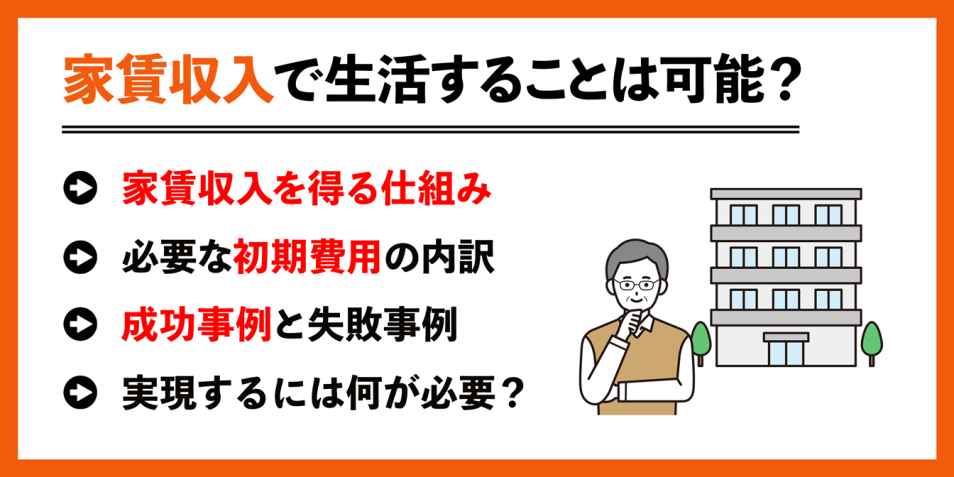- TOP
- 会社員のための不動産投資マガジン
- 記事一覧
- 【最新版】日本人の投資割合はどれくらい?世界との比較や人気の投資先を徹底解説
2026.01.30
ベルテックスコラム事務局
【最新版】日本人の投資割合はどれくらい?世界との比較や人気の投資先を徹底解説
- 日本の現状
- NISA
- iDeCo
日本では、まだまだ投資をしている人が少なく、個人資産の多くが預貯金に偏っています。
世界の主要国と比較すると、この傾向はより顕著です。
しかし、低金利の影響で預貯金のままでは資産がほとんど増えません。さらに、インフレが進むと現金の価値が目減りし、実質的な資産の価値が低下するリスクもあります。
そのため、資産を守り増やすには投資が重要です。
では、なぜ日本では投資が広がりにくいのでしょうか?
その背景には、長年の「貯蓄文化」や「投資=リスクが高い」というイメージ、金融教育の遅れなど、さまざまな要因があります。 しかし、近年はNISAや金融教育の拡充が進み、投資をとりまく環境が大きく変わりつつあります。
本記事では、日本の投資人口の現状や世界との比較を詳しく解説するとともに、これから投資を始める人に向けて、注目の投資方法をご紹介します。
今こそ、資産形成に取り組む絶好のチャンスですので、見ていきましょう。
【2025年版】日本人の投資割合の最新データ
まずは、どのくらいの日本人が投資をしているのか、最新のデータをもとに解説します。
株式・投資信託の保有率
日本証券業協会が全国18歳以上の7,000人を対象に実施した「証券投資に関する全国調査」(2024年)によると、株式、投資信託、公社債のいずれかを保有している人の割合(有価証券保有率)は24.1%に達しました。
前回調査の19.6%からは4.5ポイント増加し、投資への関心が高まっていることがわかります。
【有価証券の保有実態】
|
2024年 |
2021年(前回調査) |
差分 |
|
|---|---|---|---|
|
有価証券(※) |
24.1% |
19.6% |
4.5%増 |
|
株式 |
14.1% |
13.3% |
0.8%増 |
|
投資信託 |
12.6% |
10.1% |
2.5%増 |
※株式、投資信託、公社債のいずれかを保有する者の割合
日本証券業協会「証券投資に関する全国調調査」有価証券(株式・投資信託・公社債)の保有実態を基に表作成
さらに詳しく見ていくと、株式の保有率は前回の13.3%から14.1%へと0.8ポイント増加しています。投資信託の保有率はさらに顕著で、10.1%から12.6%へと2.5ポイント上昇しました。特に、投資信託の利用が支持されつつあるようです。
興味深いのは、同調査で行われた証券投資の必要性に関する意識の変化です。
証券投資を「必要だと思う」と回答した人の割合は、前回調査の30.9%から42.6%へと、11.7ポイントも増加しました。
【証券投資に対する意識・必要性】
|
2024年 |
2021年度(前回調査) |
差分 |
|
|---|---|---|---|
|
必要だと思う |
42.6% |
30.9% |
11.7%増 |
|
必要だとは思わない |
57.1% |
68.9% |
11.8%減 |
|
無回答 |
0.2% |
0.2% |
- |
日本証券業協会「証券投資に関する全国調査」証券投資に対する意識・必要性を基に表作成
証券投資が必要だと考える割合が増えてきているのは、将来への備えや資産形成への意識が大きく変わってきていることの表れです。
数字からも明らかなように、日本人の投資に対する姿勢は変化しつつあります。
【参考】日本証券業協会「証券投資に関する全国調査」2024年10月16日発表
投資信託の積立投資利用率
続いて、投資信託の積立利用率を確認していきましょう。
一般社団法人投資信託協会が実施した「投資信託に関するアンケート調査」の最新版(2023年)によれば、投資信託保有者のうち、積立投資を利用している人の割合は64.6%で、前年から7.2ポイント増加しました。
【投資信託の積立投資を「利用している」と回答した割合】
|
2023年 |
2022年 |
差分 |
|
|---|---|---|---|
|
全体 |
64.6% |
57.4% |
7.2%増加 |
|
20代 |
82.5 |
86.0% |
3.5%減少 |
|
30代 |
82.4 |
78.7 |
3.7%増加 |
|
40代 |
77.2 |
67.2 |
10%増加 |
|
50代 |
65.0 |
61.1 |
3.9%増加 |
|
60代 |
47.4 |
37.8 |
9.6%増加 |
|
70代 |
34.2 |
28.7 |
5.5%増加 |
一般社団法人投資信託協会「2023年 投資信託に関するアンケート調査」投資信託の積立投資の利用状況を基に表作成
年齢別で見てみると、20代と30代では積立投資の利用率が80%を超えており、若年層への浸透が目立ちます。
また、30代から70代の世代では前年より利用率が増加しており、積立投資が幅広い世代に受け入れられていることが示されています。
積立投資の特徴である「少額から始められる手軽さ」や「長期的な資産形成」が、多くの方に受け入れられつつあるといえるでしょう。
さらに、投資信託を保有する口座の中で、「つみたてNISA」の利用が大きく増加しています。2023年には42.6%がつみたてNISAを利用しており、前年の32.0%から大きく伸びました。
【つみたてNISA口座を保有している人の割合(投資信託保有者を対象に調査)】
|
2023年 |
2022年 |
差分 |
|---|---|---|
|
42.6% |
32.0% |
10.6%増加 |
一般社団法人投資信託協会「2023年 投資信託に関するアンケート調査」投資信託の保有口座を基に表作成
つみたてNISAの利用増加は、税制優遇措置を活かした資産形成の手段という認識が高まってきていることの表れだと考えられます。
【参考】一般社団法人投資信託協会「2023年 投資信託に関するアンケート調査」2024年1月発表
いかなる投資も行っていない人の割合
日本の投資事情を語るうえで見逃せないのが、まだ投資をしていない人たちの存在です。
野村アセットマネジメント株式会社が実施した調査によると、日本では投資を行っていない人の割合が53%に上ります。
つまり、日本人の半数以上はまだ投資の世界に足を踏み入れていないということです。
さらに、同じ調査で投資をしていない人に「どのような条件がそろったら投資を始めたいと思いますか」という質問をしたところ、最も多かった回答は「どんなことがあっても投資はしない」の31%でした。約3割の人が投資に対して強い抵抗感を持っているという結果です。
次に多かったのは「絶対に損をしなければ」という回答で29%、そして「給料・所得が増えたら」と答えた人が24%と続きます。これらの回答から見えてくるのは、多くの人が元本割れや資産の減少に対する不安を抱えているということでしょう。
投資未経験者の半数以上は、条件次第では投資を検討する可能性があるものの、リスクへの不安が大きな壁となっているようです。金融教育や、リスクを抑えた投資方法の周知がもっと広がれば、この数字も変わってくる可能性があります。
【参考】野村アセットマネジメント株式会社「金融教育に関する意識調査2023」2023年7月6日発表
日本人の投資割合が低い理由
世界の主要国と比較すると、日本人の投資割合は低いと言われています。
この章では、欧米と日本の投資割合を比較しつつ、日本人の投資割合が低い理由を掘り下げていきます。
日本とアメリカの投資割合差は2倍以上
まずは、日本と他国の投資割合を比べてみましょう。
日銀が2024年8月末に発表した日本と欧米の家計金融資産割合を比較すると、その傾向が明らかになります。
【日本・米国・ユーロエリアの家計金融資産割合】
|
現金・預金 |
投資信託と株式等の合計 |
保険・年金 |
その他 | |
|---|---|---|---|---|
|
日本 |
50.9% |
19.6% |
24.6% | 4.9% |
|
アメリカ |
11.7% |
53.3% |
27.7% | 7.3% |
|
ユーロエリア |
34.1% |
32.1% |
28.7% | 5.1% |
日本の家計金融資産のうち、最も多くを占めるのは「現金・預金」で50.9%です。一般的に「投資」と言われる投資信託と株式等を合わせた割合は19.6%にとどまります。
一方、米国で最も多いのは「株式等」の割合で40.5%あり、投資信託と株式等を合わせると53.3%となります。この数値を比較すると、日本は米国に比べて投資割合に2倍以上の開きがあることがわかります。
また、ユーロエリアと比べても、日本の投資割合は低い結果となっています。ユーロエリアでは、日本と同じく「現金・預金」が34.1%と最も多いものの、投資信託と株式等を合わせた割合は32.1%と、日本よりもはるかに高い水準です。
このデータが示すように欧米では株式や投資信託を保有することが当たり前となっています。
では、なぜ日本と欧米では投資割合に大きな差が生まれるのでしょうか?
次の章で日本人の投資割合が低い理由を解説します。
【参考】日本銀行調査統計局「資金循環の日米欧比較」2024年8月30日発表
消極性とリスク回避志向
日本の投資人口が少ない理由の1つ目は、多くの人が安全志向や保守的な価値観を持っているからです。
株式会社電通グループが実施した世界主要国価値観調査によると、日本人が最も重視する価値観は「安全」であり、「自由」や「平等」よりも優先されることがわかっています。この安全志向の強さが、投資のようなリスクを伴う行動を敬遠する要因になっていると考えられます。
また、日本人の礼儀正しさや温厚さといった特性は、慎重な意思決定を促す一方で、消極性としても表れやすい傾向があります。この性格的な特徴が投資行動にも影響し、安定した現金・預金の保有を好む一因になっているのです。
さらに、日本社会には「お金に対する消極性」という独特の国民性も存在します。「お金の話はあまりしない」という暗黙のルールがあり、投資について話すことを避けがちです。投資という言葉を聞いただけで「ギャンブル」や「怪しいもの」といったネガティブなイメージを持つ人も少なくありません。
こうしたお金に対するタブー視や投資へのマイナスイメージが、投資への積極性にブレーキをかけています。欧米では投資について友人同士で気軽に情報交換する文化がありますが、日本ではそうした機会も限られているため、投資への第一歩を踏み出すハードルが高くなっているのです。
【参考】株式会社電通グループ「世界価値観調査分析から浮かび上がった“日本の9つの特徴”を発表」2021年3月22日掲載
金融リテラシーと金融教育の不足
日本人の投資割合が低い2つ目の理由は、お金に関する知識や金融教育が不足しているためです。
野村アセットマネジメント株式会社の調査によると、金融教育を受けたことがある人はわずか14%で、実に86%の人が金融教育を受けた経験がないことが明らかになっています。つまり、ほとんどの人が投資や資産運用に関する知識を学ぶ機会を得られずに、社会に出ているのです。
その一方で金融広報中央委員会の調査において、学校で金融教育を「行うべき」との意見は71.8%と高い数値を示し、多くの人が金融教育の重要性を認識しています。
しかし、金融教育を行う側である教員のうち、金融教育を「受ける機会があり、受けた」と回答している人はわずか8.2%にとどまっています。
2022年からは高校での金融教育が拡充されたものの、教える側の教員も十分な金融教育を受けてきたとは言いがたい状況です。
【参考】野村アセットマネジメント株式会社「金融教育に関する意識調査2023」2023年7月6日発表
公的年金制度の充実
日本人の投資割合が低い3つ目の理由は、公的年金制度が充実していることがあげられます。
日本の年金制度は国民皆年金を基本とし、サラリーマンや公務員には厚生年金も加わる二階建て構造となっています。また、多くの企業では退職金制度も整っているため、働き盛りの世代は「老後の資金はある程度確保できる」と考えがちです。
この公的な保障の充実が、皮肉にも日本人の投資意欲を後退させている可能性があります。「年金があるから大丈夫」という安心感が、自ら資産形成に取り組む必要性を薄れさせているのです。
この点で、イギリスの例は非常に興味深いものがあります。
イギリスではかつて日本と同様に公的年金が充実していましたが、高齢化によって支給金額が減り、制度そのものが縮小していきました。その結果、国民は積極的に私的年金を充実させることになり、「老後の備えは自分で行うもの」という意識が国全体に浸透していったのです。
日本も今後、少子高齢化の進行により公的年金の給付水準の低下が避けられない状況です。また、終身雇用の崩壊とともに、以前のような手厚い退職金も減少傾向にあります。
こうした変化の中でより豊かな老後を送るためには、公的保障に頼るだけでなく自助努力による資産形成がますます重要になってくるでしょう。
若者の投資人口が増えている理由
世界と比較して日本人の投資人口はまだまだ低い割合にとどまっていますが、若者の投資人口は増加傾向にあり、早期から資産形成に取り組む傾向がみられます。
若年層が投資に関心を示している理由を、順番に見ていきましょう。
コロナ禍による生活防衛意識の高まり
若者の投資人口が増えた理由の1つ目は、コロナ禍をきっかけにお金を守る意識が高まったからです。
新型コロナウイルスによるパンデックは生活様式を変えただけでなく、お金に対する考え方にも大きな影響を与えました。コロナ禍以降は若い世代を中心に、「単なる預金だけでは将来の生活を守れない」という危機感が生まれています。
その結果、生活防衛の手段として、投資に関心を持つ若者が急増し、株式や仮想通貨への注目が一気に高まりました。
実際、多くのネット証券会社ではコロナ禍をきっかけに口座開設数が急増し、特に20代〜30代の若年層の新規参入が目立っています。
また、リモートワークや外出制限が続いたことで、ネットで投資に関する情報に触れる機会も多くなりました。
コロナ禍は多くの人に経済的な不安をもたらしましたが、その一方で、若者の投資意識を高める大きな分岐点にもなったのです。
【参考】日本証券業協会「インターネット取引に関する調査結果(2024年9月末)について」2024年12月19日発表
SNSやオンライン媒体の影響
若者の投資参入が増加した理由の2つ目は、SNSやオンライン媒体の影響があげられます。YouTubeやX(旧Twitter)、インスタグラム、ブログなどを通じて投資情報が拡散され、これまで一部の専門家しかアクセスできなかった情報が一般層にも広く行き渡るようになりました。
特に「投資系ユーチューバー」や「フィンフルエンサー」と呼ばれる存在の台頭は大きな変化です。彼らは専門的な金融知識を若者にも理解しやすい言葉で解説し、時にはリアルタイムで自分の投資状況を公開することで、若い世代の関心を引きつけています。
さらに見逃せないのが、SNS上で生まれる「仲間意識」の影響です。投資に関する情報がネット上で飛び交う中で、「周りも始めている」「みんなが投資をしている」という意識が生まれ、投資参入へのハードルを下げています。
仮想通貨や米国株投資がSNSでバズることも、投資ブームのきっかけになっています。過去には、ビットコインの急騰や米国株の個別銘柄が大きな話題になり、若者の間で「投資をしないと損をするかもしれない」という意識が広がりました。こうした情報の拡散が、若者の投資人口増加に大きく貢献しています。
少額投資商品の普及と認知度向上
若者の投資が増えた3つ目の理由は、少額投資の商品が増え認知度が広まったからです。
これまで「投資には大金が必要」というイメージが強かったのですが、今や100円や1,000円といった小額で投資を始められるサービスが次々と登場しています。
ネット証券を中心に、「ポイント投資」や「スマホ投資」と呼ばれる手軽なサービスが広がり、投資の敷居を大きく下げました。もはや投資=金融機関の窓口に行くという認識は古いものとなり、多くの若者はスマートフォン一つで投資を始めています。証券会社や銀行も競うようにアプリの使いやすさを向上させ、初心者でも直感的に操作できる環境を整えています。
さらに、「長期・分散投資」がリスクを抑える投資手法であるという考え方が徐々に浸透してきました。インデックス投資や積立投資が推奨されることで、「投資=ギャンブル」というネガティブなイメージも薄れつつあります。
こうした変化に伴い、「少ない金額であっても若いうちに投資を始めた方が得」という認識が広がり、早期から資産形成を目指す若者が増えているのです。
日本人に人気の投資先と今後の注目分野
ここまで、日本の投資人口や投資に対する価値観について解説しました。
では、日本人が好む「安定性」や「将来に備えた資産形成」といった保守的な投資動機を満たすにはどんな資産や運用方法が適切なのでしょうか。
人気の投資先や注目分野について見ていきましょう。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは「個人型確定拠出年金」の略称で、老後の資金形成に特化した制度です。
最大の魅力は次の「3つの税制優遇」です。
- 毎月の掛金が全額所得控除される
- 運用中の利益は非課税となる
- 受け取り時にも大きな控除がある
ただし注意点もあります。iDeCoは従来の年金を補強する意味合いが強いため、原則60歳まで引き出しができません。長期的な視点で老後資金を着実に増やしていくための制度だということを理解しておきましょう。
つみたてNISA(少額投資非課税制度)
投資初心者の強い味方として人気を集めているのが「つみたてNISA」です。積立投資専用の非課税制度で、購入した投資信託の分配金や売却益にかかる約20%の税金がゼロになります。
つみたてNISAは非課税以外にも、見逃せない魅力があります。
まず「買いのタイミングを見極めないといけない」という心理的な負担が軽減されます。
毎月決まった日に自動的に買付が行われるので、「今は買い時なのか?」と悩む必要がありません。
次に、定期的に一定額で買い付ける「ドルコスト平均法」が自然と実現できるため、価格変動リスクを抑えられます。
さらに安心なのは、利用できる商品が厳選されていることです。
つみたてNISAで購入できる投資信託は、金融庁が「積立投資に適している」と判断した低コストの分散投資型商品に限定されています。
そのため、過度にリスクの高い商品に手を出してしまう心配がありません。
「堅実に長期運用したい」と考えている方にとって、つみたてNISAは最初の一歩として最適な選択といえるでしょう。
不動産投資
不動産投資とは、アパートやマンションなどの物件を購入し、第三者に貸し出すことで家賃収入を得る投資方法です。入居者がいる限り継続的な収入が期待できるため、安定した資産形成手段として注目を集めています。
株式投資と比較したときのメリットは、価格変動が比較的少なく、毎月の収入見込みが立てやすい点です。
例えば人気エリアのマンションであれば、空室リスクも低く長期的に安定した家賃収入が見込めます。また、立地の良い物件であれば、将来的に不動産価値が上昇して売却益を得られる可能性もあります。
さらに税制面でも魅力があります。不動産投資で生じた経費(ローン金利、管理費、修繕費など)は、確定申告をすることで、所得税や住民税の負担が軽減される可能性があるのです。
また、不動産はインフレに強い資産としても知られています。物価上昇時には家賃も上がる傾向があるため、インフレヘッジ(インフレによる資産価値の目減りを防ぐ)としての役割も果たします。
不動産は、株式や投資信託以外の資産の一つとして検討する価値があり、今後も注目される投資先といえるでしょう。
一般NISA
一般NISAは、投資から得られる利益にかかる税金が非課税になる制度です。通常、株式や投資信託の売却益や分配金には約20%の税金がかかりますが、NISA口座での取引なら税金はゼロになります。
例えば10万円の利益が出た場合、約2万円を税金として支払います。しかし、NISA口座で取引をすれば、税金が発生せず額面どおり10万円をそのまま受け取れるのです。わずかな利益であっても税金が引かれないため、投資で利益を得る手ごたえを感じやすいのも魅力のひとつです。
2024年からスタートした新NISA制度では、非課税保有期間が無期限になり、年間投資枠も大幅に拡大したことで、資産の成長をより強く後押しできるようになりました。
また、つみたて投資枠と成長投資枠の2つを使い分けることで、ニーズに応じた柔軟な投資戦略が可能になっています。
ポートフォリオの例
ここでは、投資ニーズ別のポートフォリオ例を紹介します。
安定を重視するローリスク型、バランスを取るミドルリスク型、高リターンを狙うハイリスク型の3つから、自分に合った運用方法を見つけましょう。
安定重視のローリスク型
【こんな人におすすめ】
- 安定性を確保しながらも、一定のリターンは狙いたい
- 短期の値動きにはある程度耐えられるが、大きなリスクは避けたい
- 将来の資産形成のために、分散投資を意識したい
【資産配分】
- 国内債券:40%
- 海外債券:20%
- 投資信託(インデックス型):20%
- 国内株式:10%
- 不動産ファンド:10%
【資産配分のポイント】
安定性を優先した資産配分が特徴です。
全体の60%を債券に振り分けることで、価格変動リスクを抑制しました。
国内債券を中心に為替リスクを軽減しつつ、一部海外債券を組み入れることで金利環境の違いによる分散効果も期待できます。
投資信託は低コストのインデックス型を選ぶことで、市場平均のリターンを効率的に獲得していきます。
株式や不動産ファンドへの配分は控えめですが、長期的な資産成長の可能性や定期的な分配金による収入も確保できる設計になっています。
リスクとリターンのバランスを取るミドルリスク型
【こんな人におすすめ】
- 投資の知識を深めながら、安定と成長のバランスを取りたい方
- 長期的に資産を増やしたいが、過度なリスクは避けたい方
- 株式や債券、不動産など幅広く分散投資を考えている方
【資産配分】
- 国内株式:25%
- 海外株式:20%
- 投資信託(インデックス型):20%
- 不動産(現物):20%
- 国内債券:15%
【資産配分のポイント】
成長性と安定性のバランスを重視したポートフォリオです。
国内外の株式を合わせて45%配分することで、経済成長の恩恵を受けながらも国際分散投資によるリスク軽減を図ります。そして、インデックス型の投資信託20%を組み入れることで、個別銘柄の偏重リスクを避けつつ市場全体の成長を取り込む戦略としました。
特徴的なのは、不動産現物への20%の配分です。
区分マンションなどの実物資産を保有することで、家賃収入という安定したキャッシュフローと長期的な資産価値の上昇が期待できます。
また、国内債券15%は市場急変時のゆとりとして機能し、ポートフォリオ全体の変動を緩和します。
このバランス型は投資初心者から中級者まで幅広く対応でき、年1〜2回のリバランスで効果的な運用が可能です。
高リターンを狙うハイリスク型
【こんな人におすすめ】
- 高いリターンを目指し、リスクを許容できる方
- 長期視点で資産を運用し、一時的な価格変動に動じない方
- 株式や不動産など成長性の高い資産に積極的に投資したい方
【資産配分】
- 海外株式:35%
- 国内株式:20%
- 不動産(現物):25%
- 投資信託(アクティブ型):20%
【資産配分のポイント】
高いリターンを追求するポートフォリオで、株式と不動産を中心とした積極的な資産配分が特徴です。
海外株式を35%と高めに設定し、特に成長が期待される新興国市場や革新的な産業銘柄への投資を強化することで、高い成長性を取り込みます。
国内株式20%との組み合わせにより、合計55%を株式市場に配分し、株価上昇による利益の最大化を図るのが狙いです。
不動産現物25%の配分は、実物資産によるインフレ対策に加え、レバレッジを活用した投資効率の向上や家賃収入による安定的なキャッシュフローも期待できます。
さらに、市場平均を上回るパフォーマンスを目指すアクティブ型投資信託を20%組み入れることで、専門家の運用ノウハウも活用します。
このポートフォリオは短期的には大きな価格変動があるため、最低5年以上の長期運用が前提です。
投資家自身が、市場変動に動じない強い意志を持つことが成功の鍵となります。
日本人の投資割合は今後どう変わるのか
長らく「預金大国」として知られてきた日本ですが、社会環境の変化や制度改革によって、今後は日本人の投資スタイルにも大きな変化がやってきそうです。
これからの日本人の投資割合の変化について、詳しく解説します。
インフレと世界情勢の影響
2022年以降、日本でも長年経験していなかったインフレが顕在化しています。「お金を銀行に預けておけば安心」という従来の常識が揺らぎ始め、多くの人が「現金のままでは価値が目減りしてしまう」という現実に直面しています。こうしたインフレリスクに対応できる金融商品への注目は、今後さらに高まっていくでしょう。
特に、教育資金や老後資金など、ある程度使途や時期が特定できる資金需要については、預金から投資信託や株式などの金融商品を利用する傾向が強まると予想されます。
インフレが常態化すれば、「貯蓄から投資へ」の流れは加速することになるでしょう。この流れは日本人の金融資産構成を、欧米型に近づける大きな転換点となるかもしれません。
また、円安の加速も日本人の投資行動に変化をもたらす要因です。円の価値が下がり続ける中で、資産の一部を外貨で持つという選択肢を検討する人が増えています。実際、海外ETFや外国株への投資も少しずつ身近になってきており、この傾向は今後も続くと考えられます。
一方で、懸念されるのは金融リテラシーの格差です。投資の必要性を理解し、積極的に行動に移す人が増える一方で、知識不足やお金に対する嫌悪感から投資を避ける層も一定数残るかもしれません。こうした「投資格差」が新たな社会課題となる可能性もあります。
投資促進策と金融教育の拡充
政府の政策や金融機関の取り組みによる投資環境の整備も、日本人の投資割合を引き上げる一助になると考えられます
特に2024年から始まった新NISA制度は、年間投資枠の大幅な拡大や非課税期間の無期限化によって、多くの人にとって投資のハードルを大きく下げることになりました。今後は「投資=資産形成の当たり前」という認識が広がり、従来の預貯金から投資への資金シフトが加速するでしょう。
また、証券会社各社による手数料引き下げの競争も活発化しています。株式売買手数料の無料化や投資信託の購入時手数料の撤廃など、投資コストの削減が進み、より幅広い層が投資を始めやすくなっています。
さらに、金融教育の拡充も進んでいます。2022年から高校の家庭科で資産形成に関する教育が必修化されたほか、無料のオンラインセミナーやSNSを活用した金融知識の普及活動も活発化しており、若い世代が早期から投資に関心を持つきっかけとなっています。
こうした多方面からの取り組みによって、「投資は富裕層のもの」という固定観念は徐々に薄れつつあります。先進国の中でまだ投資人口が少ない日本は、今後大きく伸びる余地を残しているのです。
まとめ
日本の投資人口は増えつつありますが、欧米と比べるとまだ低い水準です。依然として現金・預金を重視する傾向は強く、投資への意識が遅れています。
しかし、長期的な資産形成の観点からも、早い段階で投資を始めることが重要です。投資にはリスクが伴いますが、正しい知識を身につけることでリスクを抑えながら運用できます。「投資=怖い」と捉えるのではなく、リスク管理を理解し、堅実な資産形成を目指しましょう。
その手段の一つとして、不動産投資も有効です。 不動産は価格変動が比較的少なく、安定した家賃収入が期待できるため、資産の一部に組み入れることでリスク分散にもつながります。
投資についてもっと詳しく学びたい方は、ベルテックスが開催する資産形成セミナーへの参加がおすすめです。初心者にも分かりやすく、オンラインでも気軽に受講できます。ぜひこちらから詳細をご確認ください。
この記事を書いた人
ベルテックスコラム事務局
不動産コンサルタント・税理士
不動産ソリューションの面白さや基礎、役に立つ情報や体験談などをフラットな目線で分かりやすくご紹介。宅建士・ファイナンシャルプランナー・税理士など有資格者の知見を生かしつつ、経験豊かなライターたちが不動産投資でおさえておきたいポイントをお届けします。
- TOP
- 会社員のための不動産投資マガジン
- 記事一覧
- 【最新版】日本人の投資割合はどれくらい?世界との比較や人気の投資先を徹底解説
2026.01.30
ベルテックスコラム事務局
【最新版】日本人の投資割合はどれくらい?世界との比較や人気の投資先を徹底解説
- 日本の現状
- NISA
- iDeCo
日本では、まだまだ投資をしている人が少なく、個人資産の多くが預貯金に偏っています。
世界の主要国と比較すると、この傾向はより顕著です。
しかし、低金利の影響で預貯金のままでは資産がほとんど増えません。さらに、インフレが進むと現金の価値が目減りし、実質的な資産の価値が低下するリスクもあります。
そのため、資産を守り増やすには投資が重要です。
では、なぜ日本では投資が広がりにくいのでしょうか?
その背景には、長年の「貯蓄文化」や「投資=リスクが高い」というイメージ、金融教育の遅れなど、さまざまな要因があります。 しかし、近年はNISAや金融教育の拡充が進み、投資をとりまく環境が大きく変わりつつあります。
本記事では、日本の投資人口の現状や世界との比較を詳しく解説するとともに、これから投資を始める人に向けて、注目の投資方法をご紹介します。
今こそ、資産形成に取り組む絶好のチャンスですので、見ていきましょう。
【2025年版】日本人の投資割合の最新データ
まずは、どのくらいの日本人が投資をしているのか、最新のデータをもとに解説します。
株式・投資信託の保有率
日本証券業協会が全国18歳以上の7,000人を対象に実施した「証券投資に関する全国調査」(2024年)によると、株式、投資信託、公社債のいずれかを保有している人の割合(有価証券保有率)は24.1%に達しました。
前回調査の19.6%からは4.5ポイント増加し、投資への関心が高まっていることがわかります。
【有価証券の保有実態】
|
2024年 |
2021年(前回調査) |
差分 |
|
|---|---|---|---|
|
有価証券(※) |
24.1% |
19.6% |
4.5%増 |
|
株式 |
14.1% |
13.3% |
0.8%増 |
|
投資信託 |
12.6% |
10.1% |
2.5%増 |
※株式、投資信託、公社債のいずれかを保有する者の割合
日本証券業協会「証券投資に関する全国調調査」有価証券(株式・投資信託・公社債)の保有実態を基に表作成
さらに詳しく見ていくと、株式の保有率は前回の13.3%から14.1%へと0.8ポイント増加しています。投資信託の保有率はさらに顕著で、10.1%から12.6%へと2.5ポイント上昇しました。特に、投資信託の利用が支持されつつあるようです。
興味深いのは、同調査で行われた証券投資の必要性に関する意識の変化です。
証券投資を「必要だと思う」と回答した人の割合は、前回調査の30.9%から42.6%へと、11.7ポイントも増加しました。
【証券投資に対する意識・必要性】
|
2024年 |
2021年度(前回調査) |
差分 |
|
|---|---|---|---|
|
必要だと思う |
42.6% |
30.9% |
11.7%増 |
|
必要だとは思わない |
57.1% |
68.9% |
11.8%減 |
|
無回答 |
0.2% |
0.2% |
- |
日本証券業協会「証券投資に関する全国調査」証券投資に対する意識・必要性を基に表作成
証券投資が必要だと考える割合が増えてきているのは、将来への備えや資産形成への意識が大きく変わってきていることの表れです。
数字からも明らかなように、日本人の投資に対する姿勢は変化しつつあります。
【参考】日本証券業協会「証券投資に関する全国調査」2024年10月16日発表
投資信託の積立投資利用率
続いて、投資信託の積立利用率を確認していきましょう。
一般社団法人投資信託協会が実施した「投資信託に関するアンケート調査」の最新版(2023年)によれば、投資信託保有者のうち、積立投資を利用している人の割合は64.6%で、前年から7.2ポイント増加しました。
【投資信託の積立投資を「利用している」と回答した割合】
|
2023年 |
2022年 |
差分 |
|
|---|---|---|---|
|
全体 |
64.6% |
57.4% |
7.2%増加 |
|
20代 |
82.5 |
86.0% |
3.5%減少 |
|
30代 |
82.4 |
78.7 |
3.7%増加 |
|
40代 |
77.2 |
67.2 |
10%増加 |
|
50代 |
65.0 |
61.1 |
3.9%増加 |
|
60代 |
47.4 |
37.8 |
9.6%増加 |
|
70代 |
34.2 |
28.7 |
5.5%増加 |
一般社団法人投資信託協会「2023年 投資信託に関するアンケート調査」投資信託の積立投資の利用状況を基に表作成
年齢別で見てみると、20代と30代では積立投資の利用率が80%を超えており、若年層への浸透が目立ちます。
また、30代から70代の世代では前年より利用率が増加しており、積立投資が幅広い世代に受け入れられていることが示されています。
積立投資の特徴である「少額から始められる手軽さ」や「長期的な資産形成」が、多くの方に受け入れられつつあるといえるでしょう。
さらに、投資信託を保有する口座の中で、「つみたてNISA」の利用が大きく増加しています。2023年には42.6%がつみたてNISAを利用しており、前年の32.0%から大きく伸びました。
【つみたてNISA口座を保有している人の割合(投資信託保有者を対象に調査)】
|
2023年 |
2022年 |
差分 |
|---|---|---|
|
42.6% |
32.0% |
10.6%増加 |
一般社団法人投資信託協会「2023年 投資信託に関するアンケート調査」投資信託の保有口座を基に表作成
つみたてNISAの利用増加は、税制優遇措置を活かした資産形成の手段という認識が高まってきていることの表れだと考えられます。
【参考】一般社団法人投資信託協会「2023年 投資信託に関するアンケート調査」2024年1月発表
いかなる投資も行っていない人の割合
日本の投資事情を語るうえで見逃せないのが、まだ投資をしていない人たちの存在です。
野村アセットマネジメント株式会社が実施した調査によると、日本では投資を行っていない人の割合が53%に上ります。
つまり、日本人の半数以上はまだ投資の世界に足を踏み入れていないということです。
さらに、同じ調査で投資をしていない人に「どのような条件がそろったら投資を始めたいと思いますか」という質問をしたところ、最も多かった回答は「どんなことがあっても投資はしない」の31%でした。約3割の人が投資に対して強い抵抗感を持っているという結果です。
次に多かったのは「絶対に損をしなければ」という回答で29%、そして「給料・所得が増えたら」と答えた人が24%と続きます。これらの回答から見えてくるのは、多くの人が元本割れや資産の減少に対する不安を抱えているということでしょう。
投資未経験者の半数以上は、条件次第では投資を検討する可能性があるものの、リスクへの不安が大きな壁となっているようです。金融教育や、リスクを抑えた投資方法の周知がもっと広がれば、この数字も変わってくる可能性があります。
【参考】野村アセットマネジメント株式会社「金融教育に関する意識調査2023」2023年7月6日発表
日本人の投資割合が低い理由
世界の主要国と比較すると、日本人の投資割合は低いと言われています。
この章では、欧米と日本の投資割合を比較しつつ、日本人の投資割合が低い理由を掘り下げていきます。
日本とアメリカの投資割合差は2倍以上
まずは、日本と他国の投資割合を比べてみましょう。
日銀が2024年8月末に発表した日本と欧米の家計金融資産割合を比較すると、その傾向が明らかになります。
【日本・米国・ユーロエリアの家計金融資産割合】
|
現金・預金 |
投資信託と株式等の合計 |
保険・年金 |
その他 | |
|---|---|---|---|---|
|
日本 |
50.9% |
19.6% |
24.6% | 4.9% |
|
アメリカ |
11.7% |
53.3% |
27.7% | 7.3% |
|
ユーロエリア |
34.1% |
32.1% |
28.7% | 5.1% |
日本の家計金融資産のうち、最も多くを占めるのは「現金・預金」で50.9%です。一般的に「投資」と言われる投資信託と株式等を合わせた割合は19.6%にとどまります。
一方、米国で最も多いのは「株式等」の割合で40.5%あり、投資信託と株式等を合わせると53.3%となります。この数値を比較すると、日本は米国に比べて投資割合に2倍以上の開きがあることがわかります。
また、ユーロエリアと比べても、日本の投資割合は低い結果となっています。ユーロエリアでは、日本と同じく「現金・預金」が34.1%と最も多いものの、投資信託と株式等を合わせた割合は32.1%と、日本よりもはるかに高い水準です。
このデータが示すように欧米では株式や投資信託を保有することが当たり前となっています。
では、なぜ日本と欧米では投資割合に大きな差が生まれるのでしょうか?
次の章で日本人の投資割合が低い理由を解説します。
【参考】日本銀行調査統計局「資金循環の日米欧比較」2024年8月30日発表
消極性とリスク回避志向
日本の投資人口が少ない理由の1つ目は、多くの人が安全志向や保守的な価値観を持っているからです。
株式会社電通グループが実施した世界主要国価値観調査によると、日本人が最も重視する価値観は「安全」であり、「自由」や「平等」よりも優先されることがわかっています。この安全志向の強さが、投資のようなリスクを伴う行動を敬遠する要因になっていると考えられます。
また、日本人の礼儀正しさや温厚さといった特性は、慎重な意思決定を促す一方で、消極性としても表れやすい傾向があります。この性格的な特徴が投資行動にも影響し、安定した現金・預金の保有を好む一因になっているのです。
さらに、日本社会には「お金に対する消極性」という独特の国民性も存在します。「お金の話はあまりしない」という暗黙のルールがあり、投資について話すことを避けがちです。投資という言葉を聞いただけで「ギャンブル」や「怪しいもの」といったネガティブなイメージを持つ人も少なくありません。
こうしたお金に対するタブー視や投資へのマイナスイメージが、投資への積極性にブレーキをかけています。欧米では投資について友人同士で気軽に情報交換する文化がありますが、日本ではそうした機会も限られているため、投資への第一歩を踏み出すハードルが高くなっているのです。
【参考】株式会社電通グループ「世界価値観調査分析から浮かび上がった“日本の9つの特徴”を発表」2021年3月22日掲載
金融リテラシーと金融教育の不足
日本人の投資割合が低い2つ目の理由は、お金に関する知識や金融教育が不足しているためです。
野村アセットマネジメント株式会社の調査によると、金融教育を受けたことがある人はわずか14%で、実に86%の人が金融教育を受けた経験がないことが明らかになっています。つまり、ほとんどの人が投資や資産運用に関する知識を学ぶ機会を得られずに、社会に出ているのです。
その一方で金融広報中央委員会の調査において、学校で金融教育を「行うべき」との意見は71.8%と高い数値を示し、多くの人が金融教育の重要性を認識しています。
しかし、金融教育を行う側である教員のうち、金融教育を「受ける機会があり、受けた」と回答している人はわずか8.2%にとどまっています。
2022年からは高校での金融教育が拡充されたものの、教える側の教員も十分な金融教育を受けてきたとは言いがたい状況です。
【参考】野村アセットマネジメント株式会社「金融教育に関する意識調査2023」2023年7月6日発表
公的年金制度の充実
日本人の投資割合が低い3つ目の理由は、公的年金制度が充実していることがあげられます。
日本の年金制度は国民皆年金を基本とし、サラリーマンや公務員には厚生年金も加わる二階建て構造となっています。また、多くの企業では退職金制度も整っているため、働き盛りの世代は「老後の資金はある程度確保できる」と考えがちです。
この公的な保障の充実が、皮肉にも日本人の投資意欲を後退させている可能性があります。「年金があるから大丈夫」という安心感が、自ら資産形成に取り組む必要性を薄れさせているのです。
この点で、イギリスの例は非常に興味深いものがあります。
イギリスではかつて日本と同様に公的年金が充実していましたが、高齢化によって支給金額が減り、制度そのものが縮小していきました。その結果、国民は積極的に私的年金を充実させることになり、「老後の備えは自分で行うもの」という意識が国全体に浸透していったのです。
日本も今後、少子高齢化の進行により公的年金の給付水準の低下が避けられない状況です。また、終身雇用の崩壊とともに、以前のような手厚い退職金も減少傾向にあります。
こうした変化の中でより豊かな老後を送るためには、公的保障に頼るだけでなく自助努力による資産形成がますます重要になってくるでしょう。
若者の投資人口が増えている理由
世界と比較して日本人の投資人口はまだまだ低い割合にとどまっていますが、若者の投資人口は増加傾向にあり、早期から資産形成に取り組む傾向がみられます。
若年層が投資に関心を示している理由を、順番に見ていきましょう。
コロナ禍による生活防衛意識の高まり
若者の投資人口が増えた理由の1つ目は、コロナ禍をきっかけにお金を守る意識が高まったからです。
新型コロナウイルスによるパンデックは生活様式を変えただけでなく、お金に対する考え方にも大きな影響を与えました。コロナ禍以降は若い世代を中心に、「単なる預金だけでは将来の生活を守れない」という危機感が生まれています。
その結果、生活防衛の手段として、投資に関心を持つ若者が急増し、株式や仮想通貨への注目が一気に高まりました。
実際、多くのネット証券会社ではコロナ禍をきっかけに口座開設数が急増し、特に20代〜30代の若年層の新規参入が目立っています。
また、リモートワークや外出制限が続いたことで、ネットで投資に関する情報に触れる機会も多くなりました。
コロナ禍は多くの人に経済的な不安をもたらしましたが、その一方で、若者の投資意識を高める大きな分岐点にもなったのです。
【参考】日本証券業協会「インターネット取引に関する調査結果(2024年9月末)について」2024年12月19日発表
SNSやオンライン媒体の影響
若者の投資参入が増加した理由の2つ目は、SNSやオンライン媒体の影響があげられます。YouTubeやX(旧Twitter)、インスタグラム、ブログなどを通じて投資情報が拡散され、これまで一部の専門家しかアクセスできなかった情報が一般層にも広く行き渡るようになりました。
特に「投資系ユーチューバー」や「フィンフルエンサー」と呼ばれる存在の台頭は大きな変化です。彼らは専門的な金融知識を若者にも理解しやすい言葉で解説し、時にはリアルタイムで自分の投資状況を公開することで、若い世代の関心を引きつけています。
さらに見逃せないのが、SNS上で生まれる「仲間意識」の影響です。投資に関する情報がネット上で飛び交う中で、「周りも始めている」「みんなが投資をしている」という意識が生まれ、投資参入へのハードルを下げています。
仮想通貨や米国株投資がSNSでバズることも、投資ブームのきっかけになっています。過去には、ビットコインの急騰や米国株の個別銘柄が大きな話題になり、若者の間で「投資をしないと損をするかもしれない」という意識が広がりました。こうした情報の拡散が、若者の投資人口増加に大きく貢献しています。
少額投資商品の普及と認知度向上
若者の投資が増えた3つ目の理由は、少額投資の商品が増え認知度が広まったからです。
これまで「投資には大金が必要」というイメージが強かったのですが、今や100円や1,000円といった小額で投資を始められるサービスが次々と登場しています。
ネット証券を中心に、「ポイント投資」や「スマホ投資」と呼ばれる手軽なサービスが広がり、投資の敷居を大きく下げました。もはや投資=金融機関の窓口に行くという認識は古いものとなり、多くの若者はスマートフォン一つで投資を始めています。証券会社や銀行も競うようにアプリの使いやすさを向上させ、初心者でも直感的に操作できる環境を整えています。
さらに、「長期・分散投資」がリスクを抑える投資手法であるという考え方が徐々に浸透してきました。インデックス投資や積立投資が推奨されることで、「投資=ギャンブル」というネガティブなイメージも薄れつつあります。
こうした変化に伴い、「少ない金額であっても若いうちに投資を始めた方が得」という認識が広がり、早期から資産形成を目指す若者が増えているのです。
日本人に人気の投資先と今後の注目分野
ここまで、日本の投資人口や投資に対する価値観について解説しました。
では、日本人が好む「安定性」や「将来に備えた資産形成」といった保守的な投資動機を満たすにはどんな資産や運用方法が適切なのでしょうか。
人気の投資先や注目分野について見ていきましょう。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは「個人型確定拠出年金」の略称で、老後の資金形成に特化した制度です。
最大の魅力は次の「3つの税制優遇」です。
- 毎月の掛金が全額所得控除される
- 運用中の利益は非課税となる
- 受け取り時にも大きな控除がある
ただし注意点もあります。iDeCoは従来の年金を補強する意味合いが強いため、原則60歳まで引き出しができません。長期的な視点で老後資金を着実に増やしていくための制度だということを理解しておきましょう。
つみたてNISA(少額投資非課税制度)
投資初心者の強い味方として人気を集めているのが「つみたてNISA」です。積立投資専用の非課税制度で、購入した投資信託の分配金や売却益にかかる約20%の税金がゼロになります。
つみたてNISAは非課税以外にも、見逃せない魅力があります。
まず「買いのタイミングを見極めないといけない」という心理的な負担が軽減されます。
毎月決まった日に自動的に買付が行われるので、「今は買い時なのか?」と悩む必要がありません。
次に、定期的に一定額で買い付ける「ドルコスト平均法」が自然と実現できるため、価格変動リスクを抑えられます。
さらに安心なのは、利用できる商品が厳選されていることです。
つみたてNISAで購入できる投資信託は、金融庁が「積立投資に適している」と判断した低コストの分散投資型商品に限定されています。
そのため、過度にリスクの高い商品に手を出してしまう心配がありません。
「堅実に長期運用したい」と考えている方にとって、つみたてNISAは最初の一歩として最適な選択といえるでしょう。
不動産投資
不動産投資とは、アパートやマンションなどの物件を購入し、第三者に貸し出すことで家賃収入を得る投資方法です。入居者がいる限り継続的な収入が期待できるため、安定した資産形成手段として注目を集めています。
株式投資と比較したときのメリットは、価格変動が比較的少なく、毎月の収入見込みが立てやすい点です。
例えば人気エリアのマンションであれば、空室リスクも低く長期的に安定した家賃収入が見込めます。また、立地の良い物件であれば、将来的に不動産価値が上昇して売却益を得られる可能性もあります。
さらに税制面でも魅力があります。不動産投資で生じた経費(ローン金利、管理費、修繕費など)は、確定申告をすることで、所得税や住民税の負担が軽減される可能性があるのです。
また、不動産はインフレに強い資産としても知られています。物価上昇時には家賃も上がる傾向があるため、インフレヘッジ(インフレによる資産価値の目減りを防ぐ)としての役割も果たします。
不動産は、株式や投資信託以外の資産の一つとして検討する価値があり、今後も注目される投資先といえるでしょう。
一般NISA
一般NISAは、投資から得られる利益にかかる税金が非課税になる制度です。通常、株式や投資信託の売却益や分配金には約20%の税金がかかりますが、NISA口座での取引なら税金はゼロになります。
例えば10万円の利益が出た場合、約2万円を税金として支払います。しかし、NISA口座で取引をすれば、税金が発生せず額面どおり10万円をそのまま受け取れるのです。わずかな利益であっても税金が引かれないため、投資で利益を得る手ごたえを感じやすいのも魅力のひとつです。
2024年からスタートした新NISA制度では、非課税保有期間が無期限になり、年間投資枠も大幅に拡大したことで、資産の成長をより強く後押しできるようになりました。
また、つみたて投資枠と成長投資枠の2つを使い分けることで、ニーズに応じた柔軟な投資戦略が可能になっています。
ポートフォリオの例
ここでは、投資ニーズ別のポートフォリオ例を紹介します。
安定を重視するローリスク型、バランスを取るミドルリスク型、高リターンを狙うハイリスク型の3つから、自分に合った運用方法を見つけましょう。
安定重視のローリスク型
【こんな人におすすめ】
- 安定性を確保しながらも、一定のリターンは狙いたい
- 短期の値動きにはある程度耐えられるが、大きなリスクは避けたい
- 将来の資産形成のために、分散投資を意識したい
【資産配分】
- 国内債券:40%
- 海外債券:20%
- 投資信託(インデックス型):20%
- 国内株式:10%
- 不動産ファンド:10%
【資産配分のポイント】
安定性を優先した資産配分が特徴です。
全体の60%を債券に振り分けることで、価格変動リスクを抑制しました。
国内債券を中心に為替リスクを軽減しつつ、一部海外債券を組み入れることで金利環境の違いによる分散効果も期待できます。
投資信託は低コストのインデックス型を選ぶことで、市場平均のリターンを効率的に獲得していきます。
株式や不動産ファンドへの配分は控えめですが、長期的な資産成長の可能性や定期的な分配金による収入も確保できる設計になっています。
リスクとリターンのバランスを取るミドルリスク型
【こんな人におすすめ】
- 投資の知識を深めながら、安定と成長のバランスを取りたい方
- 長期的に資産を増やしたいが、過度なリスクは避けたい方
- 株式や債券、不動産など幅広く分散投資を考えている方
【資産配分】
- 国内株式:25%
- 海外株式:20%
- 投資信託(インデックス型):20%
- 不動産(現物):20%
- 国内債券:15%
【資産配分のポイント】
成長性と安定性のバランスを重視したポートフォリオです。
国内外の株式を合わせて45%配分することで、経済成長の恩恵を受けながらも国際分散投資によるリスク軽減を図ります。そして、インデックス型の投資信託20%を組み入れることで、個別銘柄の偏重リスクを避けつつ市場全体の成長を取り込む戦略としました。
特徴的なのは、不動産現物への20%の配分です。
区分マンションなどの実物資産を保有することで、家賃収入という安定したキャッシュフローと長期的な資産価値の上昇が期待できます。
また、国内債券15%は市場急変時のゆとりとして機能し、ポートフォリオ全体の変動を緩和します。
このバランス型は投資初心者から中級者まで幅広く対応でき、年1〜2回のリバランスで効果的な運用が可能です。
高リターンを狙うハイリスク型
【こんな人におすすめ】
- 高いリターンを目指し、リスクを許容できる方
- 長期視点で資産を運用し、一時的な価格変動に動じない方
- 株式や不動産など成長性の高い資産に積極的に投資したい方
【資産配分】
- 海外株式:35%
- 国内株式:20%
- 不動産(現物):25%
- 投資信託(アクティブ型):20%
【資産配分のポイント】
高いリターンを追求するポートフォリオで、株式と不動産を中心とした積極的な資産配分が特徴です。
海外株式を35%と高めに設定し、特に成長が期待される新興国市場や革新的な産業銘柄への投資を強化することで、高い成長性を取り込みます。
国内株式20%との組み合わせにより、合計55%を株式市場に配分し、株価上昇による利益の最大化を図るのが狙いです。
不動産現物25%の配分は、実物資産によるインフレ対策に加え、レバレッジを活用した投資効率の向上や家賃収入による安定的なキャッシュフローも期待できます。
さらに、市場平均を上回るパフォーマンスを目指すアクティブ型投資信託を20%組み入れることで、専門家の運用ノウハウも活用します。
このポートフォリオは短期的には大きな価格変動があるため、最低5年以上の長期運用が前提です。
投資家自身が、市場変動に動じない強い意志を持つことが成功の鍵となります。
日本人の投資割合は今後どう変わるのか
長らく「預金大国」として知られてきた日本ですが、社会環境の変化や制度改革によって、今後は日本人の投資スタイルにも大きな変化がやってきそうです。
これからの日本人の投資割合の変化について、詳しく解説します。
インフレと世界情勢の影響
2022年以降、日本でも長年経験していなかったインフレが顕在化しています。「お金を銀行に預けておけば安心」という従来の常識が揺らぎ始め、多くの人が「現金のままでは価値が目減りしてしまう」という現実に直面しています。こうしたインフレリスクに対応できる金融商品への注目は、今後さらに高まっていくでしょう。
特に、教育資金や老後資金など、ある程度使途や時期が特定できる資金需要については、預金から投資信託や株式などの金融商品を利用する傾向が強まると予想されます。
インフレが常態化すれば、「貯蓄から投資へ」の流れは加速することになるでしょう。この流れは日本人の金融資産構成を、欧米型に近づける大きな転換点となるかもしれません。
また、円安の加速も日本人の投資行動に変化をもたらす要因です。円の価値が下がり続ける中で、資産の一部を外貨で持つという選択肢を検討する人が増えています。実際、海外ETFや外国株への投資も少しずつ身近になってきており、この傾向は今後も続くと考えられます。
一方で、懸念されるのは金融リテラシーの格差です。投資の必要性を理解し、積極的に行動に移す人が増える一方で、知識不足やお金に対する嫌悪感から投資を避ける層も一定数残るかもしれません。こうした「投資格差」が新たな社会課題となる可能性もあります。
投資促進策と金融教育の拡充
政府の政策や金融機関の取り組みによる投資環境の整備も、日本人の投資割合を引き上げる一助になると考えられます
特に2024年から始まった新NISA制度は、年間投資枠の大幅な拡大や非課税期間の無期限化によって、多くの人にとって投資のハードルを大きく下げることになりました。今後は「投資=資産形成の当たり前」という認識が広がり、従来の預貯金から投資への資金シフトが加速するでしょう。
また、証券会社各社による手数料引き下げの競争も活発化しています。株式売買手数料の無料化や投資信託の購入時手数料の撤廃など、投資コストの削減が進み、より幅広い層が投資を始めやすくなっています。
さらに、金融教育の拡充も進んでいます。2022年から高校の家庭科で資産形成に関する教育が必修化されたほか、無料のオンラインセミナーやSNSを活用した金融知識の普及活動も活発化しており、若い世代が早期から投資に関心を持つきっかけとなっています。
こうした多方面からの取り組みによって、「投資は富裕層のもの」という固定観念は徐々に薄れつつあります。先進国の中でまだ投資人口が少ない日本は、今後大きく伸びる余地を残しているのです。
まとめ
日本の投資人口は増えつつありますが、欧米と比べるとまだ低い水準です。依然として現金・預金を重視する傾向は強く、投資への意識が遅れています。
しかし、長期的な資産形成の観点からも、早い段階で投資を始めることが重要です。投資にはリスクが伴いますが、正しい知識を身につけることでリスクを抑えながら運用できます。「投資=怖い」と捉えるのではなく、リスク管理を理解し、堅実な資産形成を目指しましょう。
その手段の一つとして、不動産投資も有効です。 不動産は価格変動が比較的少なく、安定した家賃収入が期待できるため、資産の一部に組み入れることでリスク分散にもつながります。
投資についてもっと詳しく学びたい方は、ベルテックスが開催する資産形成セミナーへの参加がおすすめです。初心者にも分かりやすく、オンラインでも気軽に受講できます。ぜひこちらから詳細をご確認ください。
この記事を書いた人
ベルテックスコラム事務局
不動産コンサルタント・税理士
不動産ソリューションの面白さや基礎、役に立つ情報や体験談などをフラットな目線で分かりやすくご紹介。宅建士・ファイナンシャルプランナー・税理士など有資格者の知見を生かしつつ、経験豊かなライターたちが不動産投資でおさえておきたいポイントをお届けします。