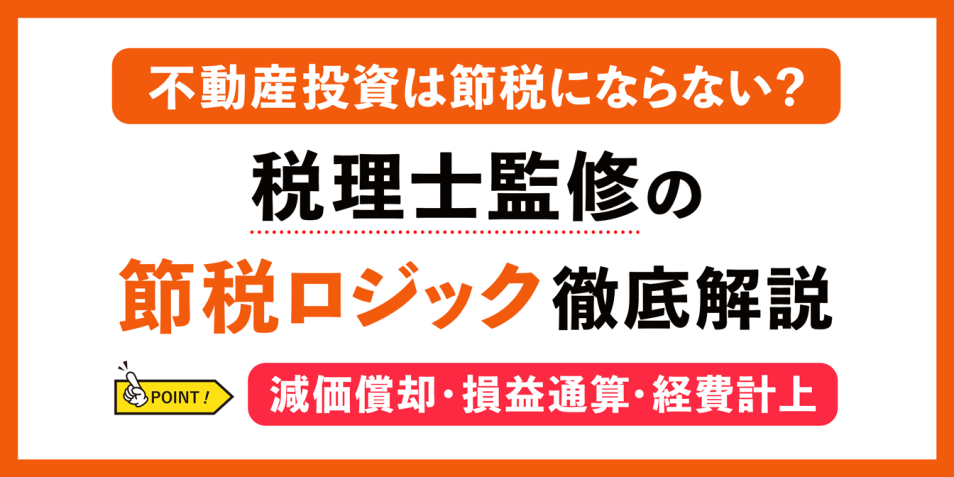- TOP
- 会社員のための不動産投資マガジン
- 記事一覧
- 不動産投資のメリットとデメリットを検証|ポートフォリオにどう組み込む?
2026.02.10
ベルテックスコラム事務局
不動産投資のメリットとデメリットを検証|ポートフォリオにどう組み込む?
- はじめ方・基礎知識
- メリット
- リスク
- ポートフォリオ
不動産投資は、ある程度の投資額で、少なくない利益が期待できる「ミドルリスク・ミドルリターン」の投資方法として、サラリーマンを中心に大きな注目を集めています。しかし、物件選びや賃貸経営への不安などから、いつか始めてみたいと思いつつ、なかなかチャレンジするまで至らないという方もいるかもしれません。
そこで今回は、不動産投資のプロの視点から、実際に運用したときのメリットと、気をつけるべきデメリットを詳しく解説します。失敗しないためのポイントや、他の投資方法と比べたときの特徴についても紹介するので、資産運用に迷っている方はぜひ参考にしてください。
不動産投資で期待できるメリット12選
不動産投資のメリットは、主に次のとおりです。
-
副収入を得られる
-
節税効果がある
-
相続対策になる
-
貯蓄効果がある
-
生命保険の役割を果たす
-
年金の補完になる
-
少ない自己資金で始められる
-
他人の資金で大きく稼げる
-
資金計画を立てやすい
-
現物資産を所有できる
-
インフレ対策になり得る
-
手間がかからない
それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。
(1)副収入を得られる
不動産投資を始めると、入居者からの家賃が毎月入ってくるようになり、安定した副収入を継続的に得られるメリットがあります。
もちろん、前提として「所有するアパート・マンションに入居者がいる」「家賃滞納が起きていない」などの条件が必要ですが、計画どおりに運用できていれば、毎月決まった額の収益をコンスタントに上げられる点は大きな魅力です。
また、不動産はこつこつと利益を出し続けるロングリターンの側面も併せ持ちます。人生100歳時代と言われる昨今、所有し続けることで、老後においても長期的な収入源としても重宝するでしょう。
(2)節税効果がある
不動産投資は、関連する支出の経費化により、所得税や住民税の節税にもつながります。
ここでいう関連支出とは、たとえば不動産の取得にかかった費用や設備の修繕費など、家賃収入を得るために必要な支出のことを指します。それらを確定申告の際に経費として計上すれば、そのぶん帳簿上の支出も増加することに。それにより、課税対象となる全体の収益を下げることができるため、納税額も減らすことができるのです。
経費の種類はさまざまで、不動産そのものにかかる支出だけでなく、不動産会社との交際費や、内見等にかかった旅費・交通費、情報収集や勉強のための新聞・書籍代といったものも含まれます。賢く経費化することで、納税額を抑えながら資産形成ができる点は不動産投資の大きなメリットでしょう。
減価償却による節税も可能
また不動産は、時間の経過とともに価値が低減していく資産でもあります。そのため法令では、木造なら22年、鉄筋コンクリート造なら47年というように、あらかじめ種類ごとに法定耐用年数が設けられています。
節税に話を戻すと、物件や設備の購入費用は基本的に経費にすることができます。しかし、会計処理上は、購入した年に一括計上するのではなく、法廷耐用年数の期間内で一年ごとに割り振ったうえで毎年の不動産所得から控除することになります。この仕組みを「減価償却」といいます。
これにより不動産投資では、建物・設備の法定耐用年数が残る間は、減価償却費の分だけ収益を少なくし、所得税や住民税の額を減らすことができるのです。
もちろん、減価償却はあくまでも会計上の処理にすぎず、実際に物件購入費用がかかるのは最初のみ。つまり、「会計上は赤字でも、手元のキャッシュフローは黒字」という状態を作ることができるため、しっかりと収益を上げながら節税することが可能です。
(3)相続対策になる
不動産投資は、将来に向けた相続対策としても有効です。
預貯金を相続する場合、課税対象となる評価額は額面どおりとなります。たとえば、1,000万円の預貯金を相続するとなれば、1,000万円に相続税が丸々課されることになります。
また、投資手法として一般的な上場株式についても、「被相続人の死亡日の最終価格」、もしくは「所定の月の平均額」で評価することになっており、相続税額が大きくなりがちです。
一方、不動産は土地、建物ともに独自の計算で評価額が決まります。それぞれの評価の根拠になる価格の種類と評価額の目安は次のとおりです。
|
|
評価に使われる価格の種類 |
評価額の目安 |
|---|---|---|
|
土地 |
(相続税)路線価 |
時価の8割程度 |
|
建物 |
固定資産税評価額 |
時価の7割程度 |
表を見ると、土地・建物どちらも、実際の価格よりも2〜3割ほど低く評価されることがわかります。そのため、額面どおりか、それに近い評価額で課税される預貯金や有価証券より相続税を節税できるわけです。
(4)貯蓄効果がある
不動産投資は貯蓄効果を期待できる点もメリットです。
物件購入にあたっては、不動産投資ローンを利用するのが一般的であり、毎月の家賃収入から返済していく必要があります。毎月のローン返済額は、金利に応じて金融機関へ支払う利息分と、当初に借り入れた資金を返済する元金分から構成されます。
ここで、物件を売却することを考えてみましょう。例として、5,000万円で購入した物件の資産価値が大きく下落せずに推移し、5,000万円で売れたとします。売却時点でローンを2,000万円返済していたとすると、残債の3,000万円を差し引いた2,000万円が手元に入ります。この2,000万円は、過去に返済した金額のうちの元金返済分と同じです。言い換えれば、ローン返済のうち元金分を毎月貯蓄していたことと同じ意味を持つのです。
投資ニーズが高い物件に投資しておけば、いざというときに売却しやすいため、貯蓄としての役割をしっかり果たしてくれるでしょう。
(5)生命保険の役割を果たす
不動産投資は、生命保険の役割も果たすといわれています。
多くの不動産投資ローンは、住宅ローンと同様、融資を受けるにあたって団体信用生命保険(団信)への加入を求められます。団信とは、ローンの返済中に債務者が亡くなったり、高度障害を負ったりして返済が困難になったとき、それ以降の返済が免除される保険です。免除後も物件を家族に引き継げるため、生命保険としての役割が期待できます。
家族は、相続した物件を引き続き所有して家賃収入を得ることができるほか、売却して現金化することも可能です。どちらにしてもまとまった資金が入ってくるので、生命保険や死亡保険代わりとして、家族の経済的な支えになるでしょう。
(6)年金の補完になる
老後の生活を見据えて、若いうちから不動産投資を始めるのも効果的です。不動産投資は、毎月安定した家賃収入が継続的に入ってくるため、年金の補完的な役割も期待できるからです。
公益財団法人生命保険文化センターの調べによると、夫婦2人で最低限の老後生活を送るにあたって必要な生活費は月額平均23.2万円。ゆとりある老後生活を送るには、月額平均37.9万円が必要になるといいます。
これに対し、どちらも無職の夫婦世帯における可処分所得は月額約21.3万円。ゆとりを持って暮らすには、月に16万円以上も不足するというのが現実です。
上記を踏まえると、不動産投資による家賃収入が、どれだけ大きなメリットになるか分かるでしょう。
もちろん賃貸経営を続けていれば、毎月のローン返済、修繕積立金、固定資産税・都市計画税の支払いも発生します。しかし、ローンさえ完済してしまえば、月々の支出も大きく減り、諸費用を除いた金額を丸々私的年金として活用できるでしょう。
ただし、物件の築年数が古くなると、大規模修繕だけでなく突発的なメンテナンスの必要性も高まります。急な出費でキャッシュフローがマイナスにならないよう、早いうちから計画的に修繕費を積み立てておくことが大切です。
(7)少ない初期投資で始められる
不動産投資は、物件の購入費用を準備しなければならないため、初期コストが高くて大変と考える方もいるかもしれません。しかし、不動産投資では、スタート時に金融機関からの融資を活用できるため、実は少ない初期投資で始められるのも魅力です。
株式投資などの他の投資方法では、信用取引などの例外を除いて、基本的には自己資金の範囲内で投資をスタートする必要があります。当然、金融機関からの融資は使えないので、一定以上の自己資金がある方でなければ、十分なリターンを期待できません。
不動産投資の場合、金融機関による融資を活用すれば、物件購入価格の1〜2割程度の自己資金で投資を始められます。5,000万円の物件に投資するケースでも、500〜1,000万円を用意すればいいことになり、誰でもチャレンジしやすいのが魅力といえるでしょう。
(8)他人の資金で大きく稼げる
不動産投資のメリットとしてよく語られるのが、投資の「レバレッジ効果」です。レバレッジとは「てこ」のことで、小さな力で大きな物を動かせる「てこ」のように、少ない投資金で大きな投資効果を得られることを指します。
不動産投資でレバレッジ効果を得られる理由は、物件購入時に金融機関からの融資を利用できるからです。
たとえば、自己資金を500万円持っている方が投資するケースを見てみましょう。株式投資など一般的な投資方法では、自己資金の範囲内でしか投資をスタートできないのが原則なので、最大でも500万円の投資しかできません。一方の不動産投資では、自己資金500万円と融資金を組み合わせて2,000万円の物件を購入する、といったことも可能です。
同じ投資利回りで考えた場合、当然500万円の投資よりも2,000万円の投資のほうが、大きなリターンを獲得できます。つまり、融資という他人の資金を活用することで、少ない自己資金でも収益の期待値を大きくできるのです。
(9)資金計画を立てやすい
不動産投資は物件購入時の条件設定により、将来の収入や支出がある程度見通せるため、投資でありながら資金計画が立てやすいのも大きな特長です。
不動産投資における収入の大半は、物件の入居者から毎月支払われる家賃によるものです。購入時の条件設定で適切な家賃を設定していれば、年月が経過したり、入居者が変わったりしても、収入額が大きく変わることはありません。
支出に関しても同様です。変動金利型で市場金利が極端に上下するようなことがない限り、毎月の返済額はある程度予測できます。さらに、固定金利型であれば返済額は常に一定です。管理会社に支払う管理委託費、修繕積立金なども毎月固定でかかるものなので、基本的に変動しません。
このように、不動産投資は収支の見通しが立てやすく、当初の資金計画に沿った安定収入が得やすいのです。
(10)現物資産を所有できる
現金や有価証券などの金融資産と異なり、不動産は実体のある現物資産です。現物資産は物としての価値が一定程度保証されるため、物件のあるエリアのニーズが大きく低下するような事態にならない限り、金融資産に比べて価値が下落しにくいといわれています。
たとえば、金融危機などがあると金融資産の価値は大きく下落するのに対し、現物資産の下落幅は小さく抑えられることから、比較的安定した資産価値が見込めます。
価値が安定している分、株式で見られるような急激な価格上昇は期待できないものの、分散投資によるリスクヘッジの効果は大きいでしょう。現預金、株式投資などと不動産投資を上手に組み合わせることにより、バランスのよい資産運用が可能になります。
(11)インフレ対策になり得る
近年、ウクライナ戦争や緊迫化する中東情勢を発端とする「資源価格の高騰」、日本と欧米の金利差による「歴史的な円安」などを背景に、物価が上昇傾向にあります。毎月のように身近な商品が値上げされ、インフレを実感している方も多いのではないでしょうか。
インフレになると、同じ商品を購入するのにより多くのお金が必要となるため、現金の価値は相対的に目減りしてしまいます。一方、現物資産である不動産の価格は、ほかの商品と同様、インフレで上昇するのが一般的。さらに、物件のある地域や入居状況によっては、毎月の家賃も増額しやすくなります。
このため、資産を現預金から不動産に換えておくことで、インフレが起きたときの資産価値の目減りを抑えることが期待できるのです。物価が上昇するほど所有物件の売却価格も高まると考えられるため、大きな売却益を狙うこともできるでしょう。
(12)手間がかからない
マンションやアパートを第三者に貸すとなると手間がかかるように感じるかもしれませんが、むしろ、あまり手間や時間をかけずに運用できるのも不動産投資の魅力とされます。
不動産投資は株式投資のような値動きがあまりないため、常にチャートを確認する必要がありません。また、入居者募集や日々の物件管理の手間はありますが、賃貸管理会社に管理を委託してしまえば、ほとんど手をかけずに済みます。
本業の忙しい会社員や公務員でも、不動産投資なら副業として取り組みやすいでしょう。
【参考】ウェルスハック「不動産投資のメリット一覧!注意すべきデメリットとあなたに最適な投資法も解説」2024年4月25日掲載
【参考】投資のトーシン「不動産投資のメリット・デメリット|成功させるためのポイントや成功事例もご紹介!」2024年12月6日現在
【参考】makes100年不動産ナビ「不動産投資の10のメリットと7のデメリットを徹底解説!」2023年4月20日掲載
【参考】国税庁「No.4632 上場株式の評価」2024年12月6日現在
【参考】公益財団法人生命保険文化センター「老後の生活費はどれくらい?」2024年12月7日現在
【参考】公益財団法人生命保険文化センター「老後の生活費はいくらくらい必要と考える?」2024年12月7日現在
不動産投資で気をつけるべきデメリット5選
不動産投資には多くのメリットがある反面、取り組むうえで気をつけたいデメリットも存在します。
-
さまざまなリスクへの対処が求められる
-
売りたいときに売れないことがある
-
ランニングコストがかかる
-
一定の自己資金を準備する必要がある
-
短期で大きな収益を上げられるわけではない
続いて、各項目を詳しく見ていきましょう。
(1)さまざまなリスクへの対処が求められる
不動産投資は、他の投資よりも比較的リスクが低いとされるものの、それでも気をつけなければならないリスクは存在します。以下に挙げるのが、不動産投資における代表的なリスクです。
|
リスクの種類 |
内容 |
|---|---|
|
空室リスク |
空室がなかなか埋まらず家賃収入が入らなくなる |
|
家賃滞納リスク |
入居者の家賃滞納により家賃収入が入らなくなる |
|
家賃下落リスク |
物件の築年数経過、近隣家賃相場の下落などにより、当初想定していたより家賃収入が減ってしまう |
|
修繕・老朽化リスク |
修繕費が想定以上にかかったり、老朽化によって物件の魅力が下がったりしてしまう |
|
災害リスク |
地震や火災によって物件が損壊して、家賃収入が入らなくなったり、修繕費がかかったりする |
|
金利上昇リスク |
ローン返済中に金利が上昇して、返済負担が増え、収支が悪化する |
|
入居者トラブル |
騒音やゴミ出しのルール違反など、入居者によるトラブルで解決に手間がかかったり、家賃収入が減ったりしてしまう |
|
不動産価格下落リスク |
物件の賃貸ニーズが落ちたり、事故物件になったりして、物件売却時の価格が下がってしまう |
このように不動産投資にも多くのリスクがあります。ただ、大半のリスクがある程度予測できるものであるうえ、事前の対策によりリスクヘッジできるものがほとんどです。
上記のリスクが存在するというのを十分に理解し、必要な対策をあらかじめ講じておくことが、不動産投資を成功させる近道といえるでしょう。
(2)売りたいときに売れないことがある
不動産は、現預金や上場株式などの資産と比べ、流動性の低さがデメリットとされます。流動性が低いというのは、すぐに売却できるとは限らないということです。
不動産を売却するには、不動産会社による物件の査定、売却活動、買主との売買契約締結や引き渡しなど、短くても数ヵ月かかるのが一般的です。また、物件の種類や立地によってはニーズが小さく、売りたくても売れない可能性もあります。
少しでも流動性を担保するには、同じ不動産投資でも、ワンルームマンション投資(区分投資)を選ぶのがおすすめです。一棟投資は期待できる収益が大きい反面、購入価格が高いので売却先が限られ、流動性が低くなりやすいデメリットがあります。
(3)ランニングコストがかかる
不動産投資は毎月の家賃収入を得られる一方、一定のランニングコストを常に負担しなければなりません。主なランニングコストは次のとおりです。
・管理費、修繕積立金(ワンルームマンション投資の場合)
・固定資産税、都市計画税
・管理委託費(管理会社に管理業務を委託する場合)
・退去発生時の原状回復費用
家賃収入からこうした費用を差し引いても、手元に十分な利益が残るよう、慎重な物件選びと余裕のある収支計画を心がけましょう。
(4)一定の自己資金を準備する必要がある
不動産投資のメリットとして「比較的少ない初期投資で始められる」ことを紹介しましたが、不動産投資ローンを活用するとしても、数百万円程度の頭金を準備するのが一般的です。全体の投資額に比べればわずかな金額であるものの、ある程度の自己資金は用意しなければなりません。
「自己資金をすぐに準備するのが難しいけれど、不動産投資にチャレンジしたい」場合には、少ない頭金で始められるサービスを活用することをおすすめします。
ベルテックスの不動産投資なら、たった10万円の頭金から投資をスタートできます。また、提携金融機関を豊富にご用意しており、お客様の資産状況によっては金利1%台の不動産投資ローンを組むことも可能。自己資金や月々の資金余力を残したい方でも不動産投資にチャレンジできます。
(5)短期で大きな収益を上げられるわけではない
上述のように、不動産投資は初期投資額が他の投資と比べて多いものの、家賃収入による利回りは決して高いとはいえません。そのため、短期で大きな収益を上げたいと考える方には向いておらず、あくまでも長期継続で安定的に収入を得ていきたい方向けの投資手法といえるでしょう。
一方で、1軒目で得た家賃収入を元手に新たな融資を受ければ、2軒目、3軒目と投資規模を計画的に拡大することが可能です。1軒あたりの利回りがそれほど高くなくても、所有する物件数が増えると、短期的に得られる収入も大きくなります。
【参考】プレファン「不動産投資のメリットとデメリット・向いている人」2024年12月8日現在
【参考】RENOSYマガジン「不動産投資のメリットとは?知らないと損するデメリットも併せて解説」2023年7月19日掲載
【参考】住まいとお金の知恵袋「不動産投資とは?仕組みやメリット・デメリット、始め方を解説」2023年1月18日掲載
NISAなど他の投資と比較してどっちがいい?
不動産投資の他にも、資産運用の方法はさまざまあります。主要な投資手法と比べたとき、不動産投資にはどのような特徴があるのでしょうか。ここでは「NISA(投資信託)」「株式・FX」「国債・定期預金」と不動産投資を6つの観点で比較します。
|
|
不動産投資 |
NISA (投資信託) |
株式・FX |
国債・ 定期預金 |
|---|---|---|---|---|
|
①始めやすさ |
◯ |
◎ |
◯ |
◎ |
|
②安定性 |
◎ |
◯ |
× |
◎ |
|
③節税効果 |
◎ |
◯ |
△ |
△ |
|
④将来の備え |
◎ |
◯ |
△ |
△ |
|
⑤働けなくなったときのリスクヘッジ |
◎ |
△ |
△ |
△ |
|
⑥管理のしやすさ |
◎ |
◯ |
△ |
◎ |
比較①始めやすさ
各投資の始めやすさを比較すると、どの投資もハードルはそれほど高くありません。NISA、株式・FX、国債・定期預金のいずれも少額での投資が可能であり、証券口座の準備など所定の手続きを行えば、すぐにでもスタートできるでしょう。
上場株式は100株単位での購入が基本なので、単価の高い企業の株式に投資しようとすると数十万〜数百万円単位の費用がかかるケースもあります。ただし、多くの証券会社で1株ごとや10株単位などの「単位未満株」を扱っており、この仕組みを利用すれば初期投資額を抑えられます。
一方、不動産投資は物件価格が高いものの、金融機関の融資を活用することで初期費用を抑えることが可能です。レバレッジ効果が期待できるうえ、管理会社に業務を委託すれば手間なく運用できるため、運用中の負担も小さいのは大きなメリットといえるでしょう。
比較②安定性
株式・FXは、短期間で大きな利益を得られる可能性がある反面、反対に短期間でマイナスが拡大する恐れもあり、安定性には欠けます。これが、株式・FXがハイリスク・ハイリターンとされるゆえんです。
NISAで投資信託に投資する場合、中長期的な積立による利益を目的とする商品であることから、個別株に投資するよりも安定性に優れています。
国債や定期預金は、国・金融機関が元本を保証してくれるため元本割れになるリスクが低く、安定性を求める方にはおすすめの投資手法といえるでしょう。ただし、他の投資に比べて利回りが低く、少ない投資額ではまとまったリターンが期待できない点はネックです。
不動産投資は、定期的・継続的に家賃収入を得られるため、安定性に優れています。また、リスクとリターンのバランスがよいというのもポイントです。
不動産投資は「ハイリスク・ローリターンな投資」と思われることもありますが、実際は物件のエリアと投資対象によって実態が大きく異なります。たとえば、首都圏のワンルームマンション投資であれば、月々の家賃収入は控えめながら、賃貸ニーズの高さと初期投資の少なさからリスクを抑えることができ、「ローリスク・ローリターン」の投資に分類できるでしょう。
長期運用を前提とする不動産投資は、ロングリターンである点も特徴です。長期継続的に安定収入を得たいのであれば、不動産投資が適しています。
比較③節税効果
損益通算による所得税・住民税の節税、相続税評価額の圧縮による相続対策効果で比較します。
結論からいうと、不動産投資以外の投資手法では、給与所得や事業所得との損益通算が認められていません。損益通算そのものは可能ですが、あくまでも上場株式による譲渡益と国債による譲渡損など、投資による譲渡所得同士での相殺しかできないのです。NISA口座で発生した譲渡益や配当収入は原則非課税ですが、他の所得にまで節税効果が及ぶものではありません。
相続税評価額に関しても、金融資産は所定のタイミングにおける時価がそのまま評価されるため、相続対策としての効果はあまり期待できません。
これに対し、不動産投資で赤字が出たときには、給与所得や事業所得との損益通算ができます。損益通算によって所得税の課税所得が下がれば、累進課税制度を採っている所得税の税率のテーブルが下がり、より大きな節税効果を得られることもあるでしょう。
現金や金融資産から不動産に資産を振り替えれば、相続税評価額を圧縮できるため、相続対策としても大きな効果が期待できます。
比較④将来の備え
株式・FXは、短期で大きな収益を狙える反面、安定性が低いため、将来に備えるべく長期運用するのには適していません。国債・定期預金はローリスクでの長期運用が可能ですが、利回りが低いので、老後の私的年金として活用するのは難しいのが実情です。
NISAを使った投資信託への投資に関しては、毎月配当型の商品を選ぶなどすれば、非課税で安定的に収入を得ることもできます。
インフレ対策の観点で見た場合、国債・定期預金は現預金と同じく価値が目減りする傾向にあり、有効な対策にはなりません。株式や投資信託はインフレに伴って値上がりする傾向があるので、一定のインフレ対策効果が期待できるでしょう。
長期運用による私的年金の役割、インフレ対策効果どちらも兼ね備えているのが不動産投資です。毎月の家賃収入が年金代わりになるうえ、現物資産でインフレに強いので、インフレの続く昨今の経済情勢でも強さを発揮します。
比較⑤働けなくなったときのリスクヘッジ
不動産投資は、団信による保険効果、相続税評価額の圧縮による相続対策効果が期待できることから、死亡したり重度障害になったりして働けなくなったときのリスクヘッジとしても有効と紹介しました。
この点について、他の3つの投資に同じ効果を期待することはできません。たとえば、被相続人のNISA口座にあった株式や投資信託を相続すること自体は可能ですが、相続人のNISA口座への移管は認められません。つまり、NISAの強みである非課税によるメリットは受けられないのです。
上記より、働けなくなったときのリスクヘッジとしての役割を求めるなら、不動産投資を行うのが適しているといえます。
比較⑥管理のしやすさ
本業の忙しい会社員・公務員の方にとって、いかに手間や時間をかけずに運用できるかというのも重要なポイントです。
株やFXは日々の値動きが大きいため、配当収入目的の長期保有でない限り、常にチャートを追い続けていなければなりません。スタート時の手間はかからないものの、運用し始めてからの手間は大きいと考えられます。
国債・定期預金、投資信託はほったらかし投資も可能ですが、経済情勢や運用実績に応じて定期的なリバランス(ポートフォリオの見直し)が求められます。
一方の不動産投資は、管理会社に管理業務を委託してしまえば、運用の手間がほとんどかかりません。特にワンルームマンション投資の場合、かなりの部分を管理会社に委ねることができるため、会社員や公務員の方でも本業に専念しながら運用できるでしょう。
【参考】不動産の入口「何が違う?不動産投資と他の投資商品を比べてみました!」2021年4月26日掲載
【参考】モゲチェック「不動産投資の成功率は?他投資方法との比較や成功のポイントを解説」2024年11月27日掲載
【参考】東急リバブル ウェルスアドバイザリー本部「不動産投資と金融投資の違いとは?それぞれのメリット・デメリットや不動産投資がおすすめするケースを解説」2024年7月31日掲載
【参考】伊予銀行 iyomemo「【初心者対象】国債って何?仕組みや利回りを分かりやすく解説」2021年8月19日掲載
【参考】みずほ証券「上場株式等の譲渡損失は、給与や年金と通算することはできますか?」2024年12月8日現在
【参考】SMBC日興証券「損益通算(そんえきつうさん)」2024年12月8日現在
【参考】みずほ不動産販売「不動産投資における「損益通算」とは」2024年12月8日現在
【参考】マネーフォワード クラウド確定申告「個人向け国債にかかる税金は確定申告が必要?」2022年1月27日掲載
【参考】NISAセンター「【インフレ対策】インフレに負けないための資産運用とは?NISAで投資できる商品も合わせて解説」2024年9月30日掲載
【参考】みんなのマネ活「NISA(ニーサ)口座にある金融商品は、離婚、破産、死亡の場合にどうなる?」2024年9月2日掲載
【参考】岡三証券「なぜ長期投資には「リバランス」が必要?」2024年12月8日現在
金など他の実物投資と比較してどっちがいい?
不動産投資は実物投資の代表例ですが、他に貴金属(金、銀、プラチナなど)やコレクション品(アート、陶芸品、酒類など)も、投資対象になり得る現物資産です。「貴金属」「コレクション品」への投資と不動産投資を3項目で比較してみると、次のようにまとめられます。
|
|
不動産投資 |
貴金属 |
コレクション品 |
|---|---|---|---|
|
①安定性 |
◎ |
◎ |
◯ |
|
②継続収入 |
◎ |
× |
× |
|
③保管の手間・コスト |
◯ |
△ |
△ |
①安定性
不動産、貴金属、コレクション品のいずれも現物資産であるため、金融資産のような価値の急落は考えにくいでしょう。価値の安定性はどの資産も優れています。特に、金やプラチナなどの貴金属は安全資産としての人気が高く、金融市場が急落している状況でも、反対に相場が上昇することもあるほどです。
コレクション品も価値が比較的安定しているものの、一定の価値があると認められているものは購入費用が非常に高く、一般的な会社員や公務員が購入するにはハードルが高いケースが多いでしょう。
②継続収入
貴金属やコレクション品は、基本的に売却して初めて収益をもたらします。第三者に貸し出すようなことがない限り、継続的な収入は見込めません。
一方、現物資産でありながら、安定的なインカムゲイン(保有することによる利益)を見込めるのが不動産です。不動産投資は実物投資としての安定性を担保しつつ、も得ることができます。もちろん、売却時には大きなキャピタルゲイン(売却益と購入金額の差益)も期待できます。
③保管の手間・コスト
現物資産は、保管に手間やコストがかかる点は注意が必要です。
とりわけ貴金属やコレクション品は、不動産よりも盗難や損傷のリスクが高いため、セキュリティや保管環境の維持などに多くの手間とコストがかかります。保管用のスペースを借りる場合、毎月の利用料も支払わなければなりません。
不動産投資は、他の2つに比べれば手間がかからないものの、固定資産税や修繕費、管理委託費などの固定費は常に発生します。こうした費用はある程度想定できるものなので、資金計画にしっかりと盛り込んでおくことが大切です。
【参考】ウェルスハック「実物資産とは?金融資産との違いと具体例、おすすめの実物資産を解説」2024年9月20日掲載
【参考】オリックス銀行「キャピタルゲインとは?【初心者向け】インカムゲインとどちらが良いのか、違いを解説」2024年3月27日掲載
まとめ
不動産投資は定期的な家賃収入を得られるほか、節税効果や相続対策など多くのメリットがあります。少ない初期投資でも始められるうえ、手間をかけずに運用できるので、なかなかまとまった時間を取れない会社員・公務員の方にもおすすめの投資手法です。
不動産投資で安定的な収益を上げるには、適切な物件選びと緻密な資金計画が欠かせません。ご自身だけで検討するのが難しい場合には、不動産投資のプロに相談しながら進めるとよいでしょう。
ベルテックスでは、不動産投資の専門家によるオンラインセミナーを開催中です。投資初心者の方向けのセミナーも開催していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた人
ベルテックスコラム事務局
不動産コンサルタント・税理士
不動産ソリューションの面白さや基礎、役に立つ情報や体験談などをフラットな目線で分かりやすくご紹介。宅建士・ファイナンシャルプランナー・税理士など有資格者の知見を生かしつつ、経験豊かなライターたちが不動産投資でおさえておきたいポイントをお届けします。
- TOP
- 会社員のための不動産投資マガジン
- 記事一覧
- 不動産投資のメリットとデメリットを検証|ポートフォリオにどう組み込む?
2026.02.10
ベルテックスコラム事務局
不動産投資のメリットとデメリットを検証|ポートフォリオにどう組み込む?
- はじめ方・基礎知識
- メリット
- リスク
- ポートフォリオ
不動産投資は、ある程度の投資額で、少なくない利益が期待できる「ミドルリスク・ミドルリターン」の投資方法として、サラリーマンを中心に大きな注目を集めています。しかし、物件選びや賃貸経営への不安などから、いつか始めてみたいと思いつつ、なかなかチャレンジするまで至らないという方もいるかもしれません。
そこで今回は、不動産投資のプロの視点から、実際に運用したときのメリットと、気をつけるべきデメリットを詳しく解説します。失敗しないためのポイントや、他の投資方法と比べたときの特徴についても紹介するので、資産運用に迷っている方はぜひ参考にしてください。
不動産投資で期待できるメリット12選
不動産投資のメリットは、主に次のとおりです。
-
副収入を得られる
-
節税効果がある
-
相続対策になる
-
貯蓄効果がある
-
生命保険の役割を果たす
-
年金の補完になる
-
少ない自己資金で始められる
-
他人の資金で大きく稼げる
-
資金計画を立てやすい
-
現物資産を所有できる
-
インフレ対策になり得る
-
手間がかからない
それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。
(1)副収入を得られる
不動産投資を始めると、入居者からの家賃が毎月入ってくるようになり、安定した副収入を継続的に得られるメリットがあります。
もちろん、前提として「所有するアパート・マンションに入居者がいる」「家賃滞納が起きていない」などの条件が必要ですが、計画どおりに運用できていれば、毎月決まった額の収益をコンスタントに上げられる点は大きな魅力です。
また、不動産はこつこつと利益を出し続けるロングリターンの側面も併せ持ちます。人生100歳時代と言われる昨今、所有し続けることで、老後においても長期的な収入源としても重宝するでしょう。
(2)節税効果がある
不動産投資は、関連する支出の経費化により、所得税や住民税の節税にもつながります。
ここでいう関連支出とは、たとえば不動産の取得にかかった費用や設備の修繕費など、家賃収入を得るために必要な支出のことを指します。それらを確定申告の際に経費として計上すれば、そのぶん帳簿上の支出も増加することに。それにより、課税対象となる全体の収益を下げることができるため、納税額も減らすことができるのです。
経費の種類はさまざまで、不動産そのものにかかる支出だけでなく、不動産会社との交際費や、内見等にかかった旅費・交通費、情報収集や勉強のための新聞・書籍代といったものも含まれます。賢く経費化することで、納税額を抑えながら資産形成ができる点は不動産投資の大きなメリットでしょう。
減価償却による節税も可能
また不動産は、時間の経過とともに価値が低減していく資産でもあります。そのため法令では、木造なら22年、鉄筋コンクリート造なら47年というように、あらかじめ種類ごとに法定耐用年数が設けられています。
節税に話を戻すと、物件や設備の購入費用は基本的に経費にすることができます。しかし、会計処理上は、購入した年に一括計上するのではなく、法廷耐用年数の期間内で一年ごとに割り振ったうえで毎年の不動産所得から控除することになります。この仕組みを「減価償却」といいます。
これにより不動産投資では、建物・設備の法定耐用年数が残る間は、減価償却費の分だけ収益を少なくし、所得税や住民税の額を減らすことができるのです。
もちろん、減価償却はあくまでも会計上の処理にすぎず、実際に物件購入費用がかかるのは最初のみ。つまり、「会計上は赤字でも、手元のキャッシュフローは黒字」という状態を作ることができるため、しっかりと収益を上げながら節税することが可能です。
(3)相続対策になる
不動産投資は、将来に向けた相続対策としても有効です。
預貯金を相続する場合、課税対象となる評価額は額面どおりとなります。たとえば、1,000万円の預貯金を相続するとなれば、1,000万円に相続税が丸々課されることになります。
また、投資手法として一般的な上場株式についても、「被相続人の死亡日の最終価格」、もしくは「所定の月の平均額」で評価することになっており、相続税額が大きくなりがちです。
一方、不動産は土地、建物ともに独自の計算で評価額が決まります。それぞれの評価の根拠になる価格の種類と評価額の目安は次のとおりです。
|
|
評価に使われる価格の種類 |
評価額の目安 |
|---|---|---|
|
土地 |
(相続税)路線価 |
時価の8割程度 |
|
建物 |
固定資産税評価額 |
時価の7割程度 |
表を見ると、土地・建物どちらも、実際の価格よりも2〜3割ほど低く評価されることがわかります。そのため、額面どおりか、それに近い評価額で課税される預貯金や有価証券より相続税を節税できるわけです。
(4)貯蓄効果がある
不動産投資は貯蓄効果を期待できる点もメリットです。
物件購入にあたっては、不動産投資ローンを利用するのが一般的であり、毎月の家賃収入から返済していく必要があります。毎月のローン返済額は、金利に応じて金融機関へ支払う利息分と、当初に借り入れた資金を返済する元金分から構成されます。
ここで、物件を売却することを考えてみましょう。例として、5,000万円で購入した物件の資産価値が大きく下落せずに推移し、5,000万円で売れたとします。売却時点でローンを2,000万円返済していたとすると、残債の3,000万円を差し引いた2,000万円が手元に入ります。この2,000万円は、過去に返済した金額のうちの元金返済分と同じです。言い換えれば、ローン返済のうち元金分を毎月貯蓄していたことと同じ意味を持つのです。
投資ニーズが高い物件に投資しておけば、いざというときに売却しやすいため、貯蓄としての役割をしっかり果たしてくれるでしょう。
(5)生命保険の役割を果たす
不動産投資は、生命保険の役割も果たすといわれています。
多くの不動産投資ローンは、住宅ローンと同様、融資を受けるにあたって団体信用生命保険(団信)への加入を求められます。団信とは、ローンの返済中に債務者が亡くなったり、高度障害を負ったりして返済が困難になったとき、それ以降の返済が免除される保険です。免除後も物件を家族に引き継げるため、生命保険としての役割が期待できます。
家族は、相続した物件を引き続き所有して家賃収入を得ることができるほか、売却して現金化することも可能です。どちらにしてもまとまった資金が入ってくるので、生命保険や死亡保険代わりとして、家族の経済的な支えになるでしょう。
(6)年金の補完になる
老後の生活を見据えて、若いうちから不動産投資を始めるのも効果的です。不動産投資は、毎月安定した家賃収入が継続的に入ってくるため、年金の補完的な役割も期待できるからです。
公益財団法人生命保険文化センターの調べによると、夫婦2人で最低限の老後生活を送るにあたって必要な生活費は月額平均23.2万円。ゆとりある老後生活を送るには、月額平均37.9万円が必要になるといいます。
これに対し、どちらも無職の夫婦世帯における可処分所得は月額約21.3万円。ゆとりを持って暮らすには、月に16万円以上も不足するというのが現実です。
上記を踏まえると、不動産投資による家賃収入が、どれだけ大きなメリットになるか分かるでしょう。
もちろん賃貸経営を続けていれば、毎月のローン返済、修繕積立金、固定資産税・都市計画税の支払いも発生します。しかし、ローンさえ完済してしまえば、月々の支出も大きく減り、諸費用を除いた金額を丸々私的年金として活用できるでしょう。
ただし、物件の築年数が古くなると、大規模修繕だけでなく突発的なメンテナンスの必要性も高まります。急な出費でキャッシュフローがマイナスにならないよう、早いうちから計画的に修繕費を積み立てておくことが大切です。
(7)少ない初期投資で始められる
不動産投資は、物件の購入費用を準備しなければならないため、初期コストが高くて大変と考える方もいるかもしれません。しかし、不動産投資では、スタート時に金融機関からの融資を活用できるため、実は少ない初期投資で始められるのも魅力です。
株式投資などの他の投資方法では、信用取引などの例外を除いて、基本的には自己資金の範囲内で投資をスタートする必要があります。当然、金融機関からの融資は使えないので、一定以上の自己資金がある方でなければ、十分なリターンを期待できません。
不動産投資の場合、金融機関による融資を活用すれば、物件購入価格の1〜2割程度の自己資金で投資を始められます。5,000万円の物件に投資するケースでも、500〜1,000万円を用意すればいいことになり、誰でもチャレンジしやすいのが魅力といえるでしょう。
(8)他人の資金で大きく稼げる
不動産投資のメリットとしてよく語られるのが、投資の「レバレッジ効果」です。レバレッジとは「てこ」のことで、小さな力で大きな物を動かせる「てこ」のように、少ない投資金で大きな投資効果を得られることを指します。
不動産投資でレバレッジ効果を得られる理由は、物件購入時に金融機関からの融資を利用できるからです。
たとえば、自己資金を500万円持っている方が投資するケースを見てみましょう。株式投資など一般的な投資方法では、自己資金の範囲内でしか投資をスタートできないのが原則なので、最大でも500万円の投資しかできません。一方の不動産投資では、自己資金500万円と融資金を組み合わせて2,000万円の物件を購入する、といったことも可能です。
同じ投資利回りで考えた場合、当然500万円の投資よりも2,000万円の投資のほうが、大きなリターンを獲得できます。つまり、融資という他人の資金を活用することで、少ない自己資金でも収益の期待値を大きくできるのです。
(9)資金計画を立てやすい
不動産投資は物件購入時の条件設定により、将来の収入や支出がある程度見通せるため、投資でありながら資金計画が立てやすいのも大きな特長です。
不動産投資における収入の大半は、物件の入居者から毎月支払われる家賃によるものです。購入時の条件設定で適切な家賃を設定していれば、年月が経過したり、入居者が変わったりしても、収入額が大きく変わることはありません。
支出に関しても同様です。変動金利型で市場金利が極端に上下するようなことがない限り、毎月の返済額はある程度予測できます。さらに、固定金利型であれば返済額は常に一定です。管理会社に支払う管理委託費、修繕積立金なども毎月固定でかかるものなので、基本的に変動しません。
このように、不動産投資は収支の見通しが立てやすく、当初の資金計画に沿った安定収入が得やすいのです。
(10)現物資産を所有できる
現金や有価証券などの金融資産と異なり、不動産は実体のある現物資産です。現物資産は物としての価値が一定程度保証されるため、物件のあるエリアのニーズが大きく低下するような事態にならない限り、金融資産に比べて価値が下落しにくいといわれています。
たとえば、金融危機などがあると金融資産の価値は大きく下落するのに対し、現物資産の下落幅は小さく抑えられることから、比較的安定した資産価値が見込めます。
価値が安定している分、株式で見られるような急激な価格上昇は期待できないものの、分散投資によるリスクヘッジの効果は大きいでしょう。現預金、株式投資などと不動産投資を上手に組み合わせることにより、バランスのよい資産運用が可能になります。
(11)インフレ対策になり得る
近年、ウクライナ戦争や緊迫化する中東情勢を発端とする「資源価格の高騰」、日本と欧米の金利差による「歴史的な円安」などを背景に、物価が上昇傾向にあります。毎月のように身近な商品が値上げされ、インフレを実感している方も多いのではないでしょうか。
インフレになると、同じ商品を購入するのにより多くのお金が必要となるため、現金の価値は相対的に目減りしてしまいます。一方、現物資産である不動産の価格は、ほかの商品と同様、インフレで上昇するのが一般的。さらに、物件のある地域や入居状況によっては、毎月の家賃も増額しやすくなります。
このため、資産を現預金から不動産に換えておくことで、インフレが起きたときの資産価値の目減りを抑えることが期待できるのです。物価が上昇するほど所有物件の売却価格も高まると考えられるため、大きな売却益を狙うこともできるでしょう。
(12)手間がかからない
マンションやアパートを第三者に貸すとなると手間がかかるように感じるかもしれませんが、むしろ、あまり手間や時間をかけずに運用できるのも不動産投資の魅力とされます。
不動産投資は株式投資のような値動きがあまりないため、常にチャートを確認する必要がありません。また、入居者募集や日々の物件管理の手間はありますが、賃貸管理会社に管理を委託してしまえば、ほとんど手をかけずに済みます。
本業の忙しい会社員や公務員でも、不動産投資なら副業として取り組みやすいでしょう。
【参考】ウェルスハック「不動産投資のメリット一覧!注意すべきデメリットとあなたに最適な投資法も解説」2024年4月25日掲載
【参考】投資のトーシン「不動産投資のメリット・デメリット|成功させるためのポイントや成功事例もご紹介!」2024年12月6日現在
【参考】makes100年不動産ナビ「不動産投資の10のメリットと7のデメリットを徹底解説!」2023年4月20日掲載
【参考】国税庁「No.4632 上場株式の評価」2024年12月6日現在
【参考】公益財団法人生命保険文化センター「老後の生活費はどれくらい?」2024年12月7日現在
【参考】公益財団法人生命保険文化センター「老後の生活費はいくらくらい必要と考える?」2024年12月7日現在
不動産投資で気をつけるべきデメリット5選
不動産投資には多くのメリットがある反面、取り組むうえで気をつけたいデメリットも存在します。
-
さまざまなリスクへの対処が求められる
-
売りたいときに売れないことがある
-
ランニングコストがかかる
-
一定の自己資金を準備する必要がある
-
短期で大きな収益を上げられるわけではない
続いて、各項目を詳しく見ていきましょう。
(1)さまざまなリスクへの対処が求められる
不動産投資は、他の投資よりも比較的リスクが低いとされるものの、それでも気をつけなければならないリスクは存在します。以下に挙げるのが、不動産投資における代表的なリスクです。
|
リスクの種類 |
内容 |
|---|---|
|
空室リスク |
空室がなかなか埋まらず家賃収入が入らなくなる |
|
家賃滞納リスク |
入居者の家賃滞納により家賃収入が入らなくなる |
|
家賃下落リスク |
物件の築年数経過、近隣家賃相場の下落などにより、当初想定していたより家賃収入が減ってしまう |
|
修繕・老朽化リスク |
修繕費が想定以上にかかったり、老朽化によって物件の魅力が下がったりしてしまう |
|
災害リスク |
地震や火災によって物件が損壊して、家賃収入が入らなくなったり、修繕費がかかったりする |
|
金利上昇リスク |
ローン返済中に金利が上昇して、返済負担が増え、収支が悪化する |
|
入居者トラブル |
騒音やゴミ出しのルール違反など、入居者によるトラブルで解決に手間がかかったり、家賃収入が減ったりしてしまう |
|
不動産価格下落リスク |
物件の賃貸ニーズが落ちたり、事故物件になったりして、物件売却時の価格が下がってしまう |
このように不動産投資にも多くのリスクがあります。ただ、大半のリスクがある程度予測できるものであるうえ、事前の対策によりリスクヘッジできるものがほとんどです。
上記のリスクが存在するというのを十分に理解し、必要な対策をあらかじめ講じておくことが、不動産投資を成功させる近道といえるでしょう。
(2)売りたいときに売れないことがある
不動産は、現預金や上場株式などの資産と比べ、流動性の低さがデメリットとされます。流動性が低いというのは、すぐに売却できるとは限らないということです。
不動産を売却するには、不動産会社による物件の査定、売却活動、買主との売買契約締結や引き渡しなど、短くても数ヵ月かかるのが一般的です。また、物件の種類や立地によってはニーズが小さく、売りたくても売れない可能性もあります。
少しでも流動性を担保するには、同じ不動産投資でも、ワンルームマンション投資(区分投資)を選ぶのがおすすめです。一棟投資は期待できる収益が大きい反面、購入価格が高いので売却先が限られ、流動性が低くなりやすいデメリットがあります。
(3)ランニングコストがかかる
不動産投資は毎月の家賃収入を得られる一方、一定のランニングコストを常に負担しなければなりません。主なランニングコストは次のとおりです。
・管理費、修繕積立金(ワンルームマンション投資の場合)
・固定資産税、都市計画税
・管理委託費(管理会社に管理業務を委託する場合)
・退去発生時の原状回復費用
家賃収入からこうした費用を差し引いても、手元に十分な利益が残るよう、慎重な物件選びと余裕のある収支計画を心がけましょう。
(4)一定の自己資金を準備する必要がある
不動産投資のメリットとして「比較的少ない初期投資で始められる」ことを紹介しましたが、不動産投資ローンを活用するとしても、数百万円程度の頭金を準備するのが一般的です。全体の投資額に比べればわずかな金額であるものの、ある程度の自己資金は用意しなければなりません。
「自己資金をすぐに準備するのが難しいけれど、不動産投資にチャレンジしたい」場合には、少ない頭金で始められるサービスを活用することをおすすめします。
ベルテックスの不動産投資なら、たった10万円の頭金から投資をスタートできます。また、提携金融機関を豊富にご用意しており、お客様の資産状況によっては金利1%台の不動産投資ローンを組むことも可能。自己資金や月々の資金余力を残したい方でも不動産投資にチャレンジできます。
(5)短期で大きな収益を上げられるわけではない
上述のように、不動産投資は初期投資額が他の投資と比べて多いものの、家賃収入による利回りは決して高いとはいえません。そのため、短期で大きな収益を上げたいと考える方には向いておらず、あくまでも長期継続で安定的に収入を得ていきたい方向けの投資手法といえるでしょう。
一方で、1軒目で得た家賃収入を元手に新たな融資を受ければ、2軒目、3軒目と投資規模を計画的に拡大することが可能です。1軒あたりの利回りがそれほど高くなくても、所有する物件数が増えると、短期的に得られる収入も大きくなります。
【参考】プレファン「不動産投資のメリットとデメリット・向いている人」2024年12月8日現在
【参考】RENOSYマガジン「不動産投資のメリットとは?知らないと損するデメリットも併せて解説」2023年7月19日掲載
【参考】住まいとお金の知恵袋「不動産投資とは?仕組みやメリット・デメリット、始め方を解説」2023年1月18日掲載
NISAなど他の投資と比較してどっちがいい?
不動産投資の他にも、資産運用の方法はさまざまあります。主要な投資手法と比べたとき、不動産投資にはどのような特徴があるのでしょうか。ここでは「NISA(投資信託)」「株式・FX」「国債・定期預金」と不動産投資を6つの観点で比較します。
|
|
不動産投資 |
NISA (投資信託) |
株式・FX |
国債・ 定期預金 |
|---|---|---|---|---|
|
①始めやすさ |
◯ |
◎ |
◯ |
◎ |
|
②安定性 |
◎ |
◯ |
× |
◎ |
|
③節税効果 |
◎ |
◯ |
△ |
△ |
|
④将来の備え |
◎ |
◯ |
△ |
△ |
|
⑤働けなくなったときのリスクヘッジ |
◎ |
△ |
△ |
△ |
|
⑥管理のしやすさ |
◎ |
◯ |
△ |
◎ |
比較①始めやすさ
各投資の始めやすさを比較すると、どの投資もハードルはそれほど高くありません。NISA、株式・FX、国債・定期預金のいずれも少額での投資が可能であり、証券口座の準備など所定の手続きを行えば、すぐにでもスタートできるでしょう。
上場株式は100株単位での購入が基本なので、単価の高い企業の株式に投資しようとすると数十万〜数百万円単位の費用がかかるケースもあります。ただし、多くの証券会社で1株ごとや10株単位などの「単位未満株」を扱っており、この仕組みを利用すれば初期投資額を抑えられます。
一方、不動産投資は物件価格が高いものの、金融機関の融資を活用することで初期費用を抑えることが可能です。レバレッジ効果が期待できるうえ、管理会社に業務を委託すれば手間なく運用できるため、運用中の負担も小さいのは大きなメリットといえるでしょう。
比較②安定性
株式・FXは、短期間で大きな利益を得られる可能性がある反面、反対に短期間でマイナスが拡大する恐れもあり、安定性には欠けます。これが、株式・FXがハイリスク・ハイリターンとされるゆえんです。
NISAで投資信託に投資する場合、中長期的な積立による利益を目的とする商品であることから、個別株に投資するよりも安定性に優れています。
国債や定期預金は、国・金融機関が元本を保証してくれるため元本割れになるリスクが低く、安定性を求める方にはおすすめの投資手法といえるでしょう。ただし、他の投資に比べて利回りが低く、少ない投資額ではまとまったリターンが期待できない点はネックです。
不動産投資は、定期的・継続的に家賃収入を得られるため、安定性に優れています。また、リスクとリターンのバランスがよいというのもポイントです。
不動産投資は「ハイリスク・ローリターンな投資」と思われることもありますが、実際は物件のエリアと投資対象によって実態が大きく異なります。たとえば、首都圏のワンルームマンション投資であれば、月々の家賃収入は控えめながら、賃貸ニーズの高さと初期投資の少なさからリスクを抑えることができ、「ローリスク・ローリターン」の投資に分類できるでしょう。
長期運用を前提とする不動産投資は、ロングリターンである点も特徴です。長期継続的に安定収入を得たいのであれば、不動産投資が適しています。
比較③節税効果
損益通算による所得税・住民税の節税、相続税評価額の圧縮による相続対策効果で比較します。
結論からいうと、不動産投資以外の投資手法では、給与所得や事業所得との損益通算が認められていません。損益通算そのものは可能ですが、あくまでも上場株式による譲渡益と国債による譲渡損など、投資による譲渡所得同士での相殺しかできないのです。NISA口座で発生した譲渡益や配当収入は原則非課税ですが、他の所得にまで節税効果が及ぶものではありません。
相続税評価額に関しても、金融資産は所定のタイミングにおける時価がそのまま評価されるため、相続対策としての効果はあまり期待できません。
これに対し、不動産投資で赤字が出たときには、給与所得や事業所得との損益通算ができます。損益通算によって所得税の課税所得が下がれば、累進課税制度を採っている所得税の税率のテーブルが下がり、より大きな節税効果を得られることもあるでしょう。
現金や金融資産から不動産に資産を振り替えれば、相続税評価額を圧縮できるため、相続対策としても大きな効果が期待できます。
比較④将来の備え
株式・FXは、短期で大きな収益を狙える反面、安定性が低いため、将来に備えるべく長期運用するのには適していません。国債・定期預金はローリスクでの長期運用が可能ですが、利回りが低いので、老後の私的年金として活用するのは難しいのが実情です。
NISAを使った投資信託への投資に関しては、毎月配当型の商品を選ぶなどすれば、非課税で安定的に収入を得ることもできます。
インフレ対策の観点で見た場合、国債・定期預金は現預金と同じく価値が目減りする傾向にあり、有効な対策にはなりません。株式や投資信託はインフレに伴って値上がりする傾向があるので、一定のインフレ対策効果が期待できるでしょう。
長期運用による私的年金の役割、インフレ対策効果どちらも兼ね備えているのが不動産投資です。毎月の家賃収入が年金代わりになるうえ、現物資産でインフレに強いので、インフレの続く昨今の経済情勢でも強さを発揮します。
比較⑤働けなくなったときのリスクヘッジ
不動産投資は、団信による保険効果、相続税評価額の圧縮による相続対策効果が期待できることから、死亡したり重度障害になったりして働けなくなったときのリスクヘッジとしても有効と紹介しました。
この点について、他の3つの投資に同じ効果を期待することはできません。たとえば、被相続人のNISA口座にあった株式や投資信託を相続すること自体は可能ですが、相続人のNISA口座への移管は認められません。つまり、NISAの強みである非課税によるメリットは受けられないのです。
上記より、働けなくなったときのリスクヘッジとしての役割を求めるなら、不動産投資を行うのが適しているといえます。
比較⑥管理のしやすさ
本業の忙しい会社員・公務員の方にとって、いかに手間や時間をかけずに運用できるかというのも重要なポイントです。
株やFXは日々の値動きが大きいため、配当収入目的の長期保有でない限り、常にチャートを追い続けていなければなりません。スタート時の手間はかからないものの、運用し始めてからの手間は大きいと考えられます。
国債・定期預金、投資信託はほったらかし投資も可能ですが、経済情勢や運用実績に応じて定期的なリバランス(ポートフォリオの見直し)が求められます。
一方の不動産投資は、管理会社に管理業務を委託してしまえば、運用の手間がほとんどかかりません。特にワンルームマンション投資の場合、かなりの部分を管理会社に委ねることができるため、会社員や公務員の方でも本業に専念しながら運用できるでしょう。
【参考】不動産の入口「何が違う?不動産投資と他の投資商品を比べてみました!」2021年4月26日掲載
【参考】モゲチェック「不動産投資の成功率は?他投資方法との比較や成功のポイントを解説」2024年11月27日掲載
【参考】東急リバブル ウェルスアドバイザリー本部「不動産投資と金融投資の違いとは?それぞれのメリット・デメリットや不動産投資がおすすめするケースを解説」2024年7月31日掲載
【参考】伊予銀行 iyomemo「【初心者対象】国債って何?仕組みや利回りを分かりやすく解説」2021年8月19日掲載
【参考】みずほ証券「上場株式等の譲渡損失は、給与や年金と通算することはできますか?」2024年12月8日現在
【参考】SMBC日興証券「損益通算(そんえきつうさん)」2024年12月8日現在
【参考】みずほ不動産販売「不動産投資における「損益通算」とは」2024年12月8日現在
【参考】マネーフォワード クラウド確定申告「個人向け国債にかかる税金は確定申告が必要?」2022年1月27日掲載
【参考】NISAセンター「【インフレ対策】インフレに負けないための資産運用とは?NISAで投資できる商品も合わせて解説」2024年9月30日掲載
【参考】みんなのマネ活「NISA(ニーサ)口座にある金融商品は、離婚、破産、死亡の場合にどうなる?」2024年9月2日掲載
【参考】岡三証券「なぜ長期投資には「リバランス」が必要?」2024年12月8日現在
金など他の実物投資と比較してどっちがいい?
不動産投資は実物投資の代表例ですが、他に貴金属(金、銀、プラチナなど)やコレクション品(アート、陶芸品、酒類など)も、投資対象になり得る現物資産です。「貴金属」「コレクション品」への投資と不動産投資を3項目で比較してみると、次のようにまとめられます。
|
|
不動産投資 |
貴金属 |
コレクション品 |
|---|---|---|---|
|
①安定性 |
◎ |
◎ |
◯ |
|
②継続収入 |
◎ |
× |
× |
|
③保管の手間・コスト |
◯ |
△ |
△ |
①安定性
不動産、貴金属、コレクション品のいずれも現物資産であるため、金融資産のような価値の急落は考えにくいでしょう。価値の安定性はどの資産も優れています。特に、金やプラチナなどの貴金属は安全資産としての人気が高く、金融市場が急落している状況でも、反対に相場が上昇することもあるほどです。
コレクション品も価値が比較的安定しているものの、一定の価値があると認められているものは購入費用が非常に高く、一般的な会社員や公務員が購入するにはハードルが高いケースが多いでしょう。
②継続収入
貴金属やコレクション品は、基本的に売却して初めて収益をもたらします。第三者に貸し出すようなことがない限り、継続的な収入は見込めません。
一方、現物資産でありながら、安定的なインカムゲイン(保有することによる利益)を見込めるのが不動産です。不動産投資は実物投資としての安定性を担保しつつ、も得ることができます。もちろん、売却時には大きなキャピタルゲイン(売却益と購入金額の差益)も期待できます。
③保管の手間・コスト
現物資産は、保管に手間やコストがかかる点は注意が必要です。
とりわけ貴金属やコレクション品は、不動産よりも盗難や損傷のリスクが高いため、セキュリティや保管環境の維持などに多くの手間とコストがかかります。保管用のスペースを借りる場合、毎月の利用料も支払わなければなりません。
不動産投資は、他の2つに比べれば手間がかからないものの、固定資産税や修繕費、管理委託費などの固定費は常に発生します。こうした費用はある程度想定できるものなので、資金計画にしっかりと盛り込んでおくことが大切です。
【参考】ウェルスハック「実物資産とは?金融資産との違いと具体例、おすすめの実物資産を解説」2024年9月20日掲載
【参考】オリックス銀行「キャピタルゲインとは?【初心者向け】インカムゲインとどちらが良いのか、違いを解説」2024年3月27日掲載
まとめ
不動産投資は定期的な家賃収入を得られるほか、節税効果や相続対策など多くのメリットがあります。少ない初期投資でも始められるうえ、手間をかけずに運用できるので、なかなかまとまった時間を取れない会社員・公務員の方にもおすすめの投資手法です。
不動産投資で安定的な収益を上げるには、適切な物件選びと緻密な資金計画が欠かせません。ご自身だけで検討するのが難しい場合には、不動産投資のプロに相談しながら進めるとよいでしょう。
ベルテックスでは、不動産投資の専門家によるオンラインセミナーを開催中です。投資初心者の方向けのセミナーも開催していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた人
ベルテックスコラム事務局
不動産コンサルタント・税理士
不動産ソリューションの面白さや基礎、役に立つ情報や体験談などをフラットな目線で分かりやすくご紹介。宅建士・ファイナンシャルプランナー・税理士など有資格者の知見を生かしつつ、経験豊かなライターたちが不動産投資でおさえておきたいポイントをお届けします。